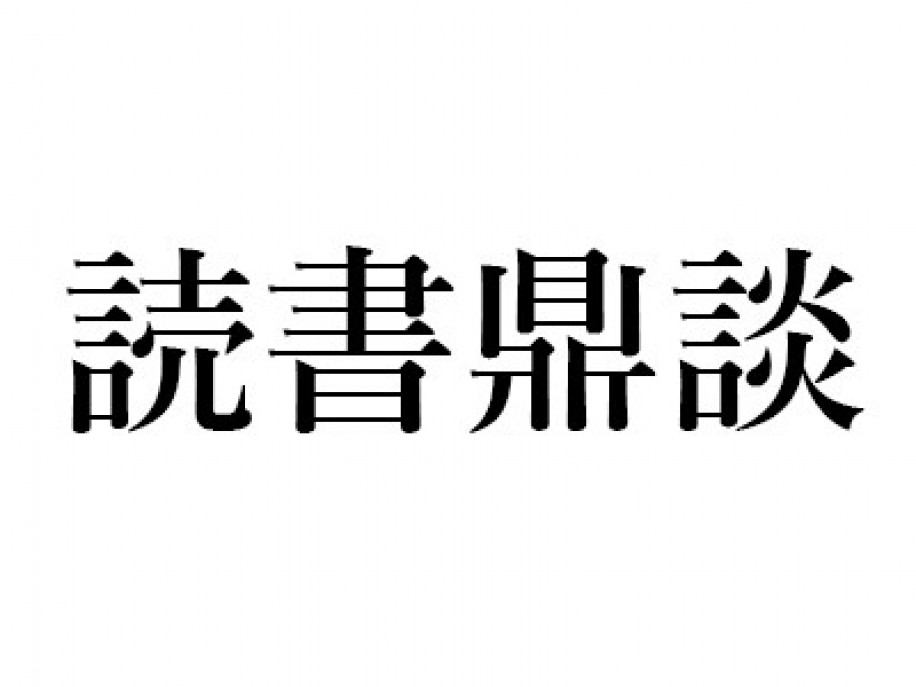書評
『芸術と青春』(光文社)
批評家、岡本太郎が語る一平とかの子
われわれの世代にとって、岡本太郎といえば、なによりも大阪万博の「太陽の塔」の作者であり、CMで「グラスの底に顔があってもいいじゃないかあー」と画面に向かって叫んでいたヘンなおじさんである。ところが、今回文庫に入った「青春回想」と「父母を憶う」(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は2002年)、とりわけ岡本一平と岡本かの子の関係を考察した後者を読んで愕然とした。そこには類いまれな「批評家」がいたからである。
まず、いきなり驚かされるのが、岡本かの子の文学に対する次のような逆説的な定義。
かの子は特異な作家であるように考えられているが、実は日本文学史上では極めて正統派であると私は考える。「文学に憧れる文学」という、現代日本文学発生から宿命的な雰囲気から外れてはいないからである
うーん、これはすごい。「文学に憧れる文学」というメタ批評でかの子と現代日本文学を背中合わせにして一刀両断にしてしまったからである。これ一つだけで小林秀雄も平野謙もすっ飛んでしまう。しかし、そんなことで驚いてはいけない。太郎は父母の間には本当の意味での恋愛はなかったと喝破する。
芸術を志す若もののヴァニティ(虚栄心)がこの異質を結びつける大きな要素だったようである
すなわち芸術に憧れるかの子にとってモダンで美男子の画家岡本一平は「芸術」のイメージそのものだった。ところが実際の一平は「若い時分から大人びて世智に鋭く、苦労人型だった」。かの子は兄に告白する。「所詮、一平は芸術家ではないのです」
いっぽう、一平は「かの子の重厚で深刻な性質にひかれた」。こちらはかの子の「文学性」に魅せられたのである。だが、いざ生活を始めてみると、そのあまりの子供っぽさに呆れ返ってしまう。
岡本かの子には生涯を通じて極めて未熟な稚純性があった。豊かに円熟した晩年に至っても、遂に童女のような馬鹿馬鹿しさを失うことがなかった
その結果、二人の生活は破綻しかける。
しかし、ここで逆転が生まれる。かの子の「成熟した人間以上の凄みと恐しさ」に気づいた一平が、夫が妻を愛するのではなく、信徒が教祖を崇めるような気持ちでかの子を愛するようになるからである。
つまり一平はかの子に賭けた。ところがかの子は一平には賭けなかったのである。己の生命の炎ともいうべきものに賭けていたのだが。しかしそういったのではまだ正確ではない。実は一平の賭けていた「かの子」に賭けてしまったのだ。そしてそれはあくまでも「一平かの子」なのである
ここに太郎はかの子の芸術の本質を見る。
岡本かの子の芸術があれだけ陶酔的な自我を貫いていながら、塵ほども狭さ、一個人の卑小さ、みだらさを感じさせない理由はそこにある
だが、こう総括したうえで、太郎はかの子と一平の「合体芸術」を否定する。理由は、それが関係の「凄み」に基づく芸術でしかないためである。
明治、大正以来、わが国の特殊なヒューマニズムを土台にした芸術意識は、常に人間の内面関係だけを基調にしている。ところで、そこに芸術の堕落が生れると私は考える
ようするに、芸術は個人に対してでなく「非情な社会に対して、更に、世界に対してこそ賭けるべきだ」というのである。
ふうむ。「太陽の塔」は父母の近代的自我の相克を乗り越えようとして生まれたポスト・モダンの非情芸術の結晶だったのか。岡本太郎、恐るべし。絶妙の復権企画である。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする