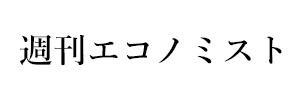書評
『ルンタ』(講談社)
「筋が通らない」世界を軽快に読ませる山下澄人
先日。ドルチェ&ガッバーナという銘柄のジーンズを穿いて家にいたところ、家の者に注意された。家にいてシシャモを食べたり、植木に水をやったり、ウッドデッキの修理をしたりするのに、ドルチェ&ガッバーナを穿くことはないではないか。もっと廉(やす)いユニクロのとかを穿いたらどうだ、と言われたのである。しかし私とて無駄にドルチェ&ガッバーナを穿いていたわけではなく、それ相応の理由があって、それはいくつもの前提や考えが積み重なって段階的にそうなった理由であった。
しかし、私は家の者にその理由を説明をしなかった。説明しないで口の中で「モゴモゴ」と言った。それは不明瞭な音声という意味ではなく、実際に、「モゴモゴ」と言った。
「モゴモゴ」「はあっ?」「モゴモゴ」「はあっ?」みたいな遣(や)り取りを数回繰り仮して、家の者は呆(あき)れて口をきかなくなり、どこかへ行ってしまった。
それで私は忠告に随(したが)って廉い服に着替えることなく、香の物をコチコチ刻んだり、ゴミ集積場にゴミを運んだりすることができた。
けれども私はなぜ家の者に説明をしなかったのだろうか。説明くらいすればよいではないか。けれども私はしなかった。なぜか。それは、その理由が筋の通らない理由で、説明をしても理解して貰えないと思ったからである。
と言うと、筋の通らないことを言っては駄目じゃないかと怒る人が出てくるかも知れないが、違う、筋は自分のなかでは通っている。通っているのだけれども、それは自分だけがわかる筋で、それを人に説明するためには膨大な言葉を費やす必要があって、でもその言葉を自分は持っていないし、聞く時間を相手は持っていない、と判断したからである。
つまり、このように人になにかを伝え、それをわかって貰うためには、そうした自分にしかわからない筋ではなく、誰が聞いても納得するわかりやすい筋が必要で、劇的な要素のまったくない日常においてすらそうなのだから、フィクション、特に小説やなんかにおいてこれは必須である。けれども。
わかりやすい筋が通るということは、出てくる人たちは明確な目的を持って意味ある行動をとり、無駄話世間話をしたり、いまから田植えをするのにプラダのスーツに着替えたりしない、ということである。
自由自在の境地に
しかし人間の心は、右(ALL REVIEWS事務局注:上)の私がそうであったように、意味や目的や方向性を持たずに様々に動き、多くの筋の通った小説からはそうしたものが完全に零れ落ちている。バラバラバラ。しかるにこの、山下澄人『ルンタ』(講談社、1728円)は、そうした、人の心の動きや働き、意味のわからない行動、文字に起こして追えば意味がわからないのに確かになにかが通じている会話、筋の通らない言動、突発的な事件、突然訪れる生の中断など、のみによって描かれている。ここでは、この小説独自の、ある仕組みによって時間の流れが過去から未来に一定の速さで流れず、すべての出来事が同時に起こり、すべての過去が同時に存在し、或(ある)いは同所から眺めることが可能で、そのお蔭で何人かの登場人物は、ここで起こるすべての出来事に自在自由に、突っ込み、を入れることができる。そしてその突っ込みなどに留意しながら読み進めるうちに、生きている人間の情念や情趣や感情や肉体や精神によって、こんがらかり、むすぼれてしまったものが、次第にほどけていき、この世の理窟で言えば筋が通らないはずの話が、すっと、筋が通っていく成り行きは読んでいてとても気持ちがよく、いま目に見えるものや耳に聞こえる音に対する感覚が変わってくる。つながるはずのないものがつながり、どこにでも行くことができ、どこからでも戻ることができるような気持ちになった。関西弁の極度に厳密な表記が、人と人との間で交換されるとりとめのない言葉に、人の魂が付着して、漂って相手のなかに入っていく様を現しているようでとても効果的だと思った。
という関西風味で考えると、登場する小さな男のヒントは池乃めだかではないか、なんて想像するのもたのしくて。
ALL REVIEWSをフォローする