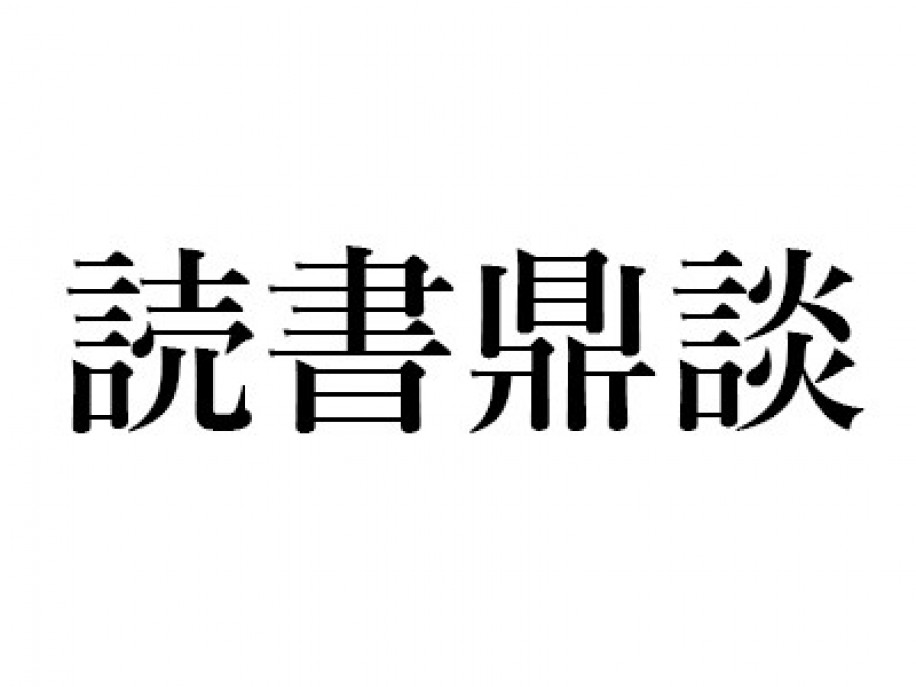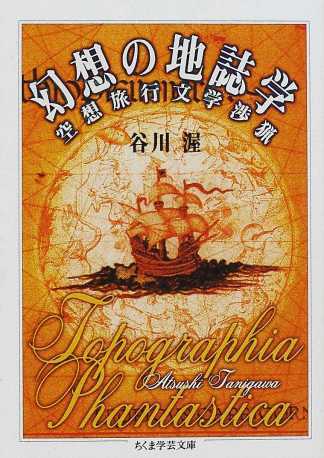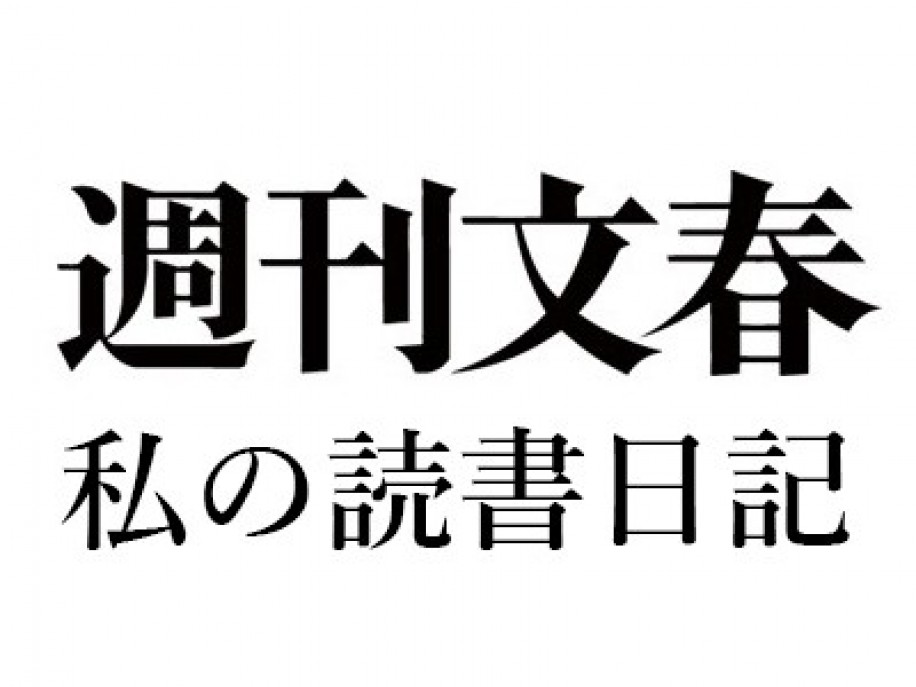書評
『地図を作った人びと―古代から観測衛星最前線にいたる地図製作の歴史』(河出書房新社)
新しい世界の発見と創造のドラマ
さて今度の休みにはどこかに行ってみよう。かたわらにある地図をひろげてみると、地図はまだ見ぬ土地へと誘ってくれる。ジグザグとした微妙な海岸線からは、切り立った崖と打ち寄せる浪のしぶき、海鳥の鳴き声が目の前に浮かんでくる。密なる等高線は、やっと登りあげた岩場から眺める山々の壮大な景観、汗まみれの肌に伝わる心地よい涼風、脚に残る軽い疲労感を想い出させてくれる。
一枚の地図を開いただけでも、いろんな空想にふけることができる。それにはたくさんの情報が書きこまれているからである。地図を利用する人間は、様々な記号から地図の平面を立体化することにつとめるのだ。
ところが、逆のことを行ってきたのが地図をつくった人々である。彼らがどんなに全体像をつかもうと努力してきたか。またできるだけ精確さを求めていかに苦心をはらってきたか、その地図の技術史を詳しく跡づけたのが本書である。
たとえば、紀元前三世紀のアレクサンドリアの図書館長エラトステネスが地球の周囲の長さを測った試み。それは博学で知的好奇心のなせるわざであったが、当時の人々は彼のことをベータとあだ名したという。アルファに対するベータ。専門家に対する二流の人物という嘲りがそこには含まれているが、どうも地図づくりには、常にこのベータ性が必要だったらしい。全体を捉える想像力、未知の部分をこの目で現場に行って確かめる冒険心は、専門家にはとても無理だったからである。
二世紀に出たプトレマイオスは座標をつかって世界図を描いた。後世の地図づくりの基本はここに定まったが、誤りも多く、その誤りから抜け出すのに後の人々はたいへん苦労した。地図づくりはまさに試行錯誤のくりかえしである。とはいえ、ひとたびつくられた地図をひっくり返すのは容易なことではない。地図にはその時代の秩序や思想、世界観がこめられているからである。
中世の神話とドグマにいろどられた地図が解放されたのは大航海時代である。海路を探るヴァスコ・ダ・ガマやコロンブスなどの冒険家たち、その必要と成果によって生まれた新しい地図の数々。メルカトル図法で有名なメルカトルが登場する。
やがてフランスでは国土の地形図づくりが試みられ、それがカッシニ一族によってなしとげられる。イギリスでは、クックやヴァンクーヴァーなどの冒険家にしてかつ測量者により、次々と精確な七つの海の地図がつくられていった。そして新大陸アメリカでの地図づくり、あのワシントンも測量者であったし、西部開拓史は地図づくりの歴史にほかならない。
本書はここまでで約半分。さらに二十世紀のハイテクノロジーによる地図づくりの物語が次々と展開される。これは未知への挑戦をつづけてきた知と情熱の探検者の歴史といえる。地図の裏側にひそむ、領土・戦争・利権といった側面はスパッと切って、地図づくりにかけた男たちの偉大な物語を爽快に描いている。実に読みごたえがあった。
よし、きめたぞ。今度の休みは少しひねってあそこに行くことにしよう。
ALL REVIEWSをフォローする