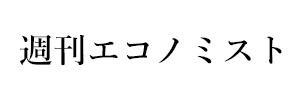書評
『献灯使』(講談社)
言葉の"設定"を離れ自由に暴れ回る快楽
原発事故がなぜ起きたか、ということについてはいろんな理由があるだろうけれども、そのひとつに関係者が、いろんな事態を想定する際、もちろん極端な事態も想定したのだけれども、あまりにも極端な事態は、これを想定しなかった、というのがあるように思う。なぜ、極端な事態を想定しなかったのかというと、まあそれもいろいろあるだろうけれども、一番大きいのは銭の問題であろう。それさえなければ最大級の事態を想定して、どんな自然災害にも人為的な破壊にも耐えられるものを造ることができるはずである。しかし、そんなことをしたら銭、すなわち経費が掛かりすぎてしまって利益が得られない。そこで、極端な事態は想定をしなかった。つまり、あまりにも極端な事態を想定すると都合が悪い、なので想定をしなかった、ということである。
でもそこにひとつの言葉の間違いがあるというのは、想定しなかった、という点で、想定の想、ということは想うということで、けれども、銭が掛かりすぎて都合が悪い、と考えることができるのは、それを想ったからこそで、なので、あまりにも極端な事態は、想定しなかった、ではなく、設定しなかった、と言った方がより正確であるように思う。
というのは、でも関係者の怠慢かと言うと必ずしもそうとも言えず、なぜかというと、私たちの社会は、そうした設定のうえに成り立っているようなところがあるからである。
もちろん会社と社会は違うものだろうけれども、都合が悪いことはなにも銭の面においてのみ生じるわけではなく、身体的に都合の悪いこともあるし、感情面や思想面において都合の悪いこともあって、そういうことを、今度は本当に、想定しない、ことによって社会の安寧秩序が保たれている部分があるのである。
そしてそのために、というのはそうやって都合の悪いことは考えないでよいようにするためにもっとも使い勝手のよい道具はなにかというと、その通り、言葉である。言葉はなにかを考えるために使われることもあるが、なにかを考えないようにするために使われることも実は多いのである。
裏文字で描く文学
なんてことを考えるのは、多和田葉子の『献灯使』(講談社、1728円)を読んだからである。この小説は、先般の事故よりももっと大規模な原子力災害が起きた後の日本国を想定して書かれている。もちろんこれが小説である以上、設定のようなものもあるが、それはあくまでも言葉にとって都合のよいように、逆に言うと、言葉が自由に暴れ回るために都合の悪いものが言葉によって容赦なく成敗された設定である。
この小説のなかで言葉は自在自由に飛び回り、いろいろな兆しや現れを示すが、その一例を挙げると、例えば、私たちは漢字と仮名交じりの文を使い、また、英語などの外国語は片仮名で表記して普通に生き、ハーゲンダッツとか食べて禿げ散らかしているが、それは音と意味をグチャグチャに混ぜておきながら、これは音、これは意味、と得手勝手に使い分けているということで、なぜそんなことをするのかというと、そう例のやつ、そうすると便利だし、ということはそうしないと不便だし、カネもかかるし、面倒くさいし、ひっくるめて言うと都合が悪いし、ということなのだけれども、チョイ待、ウェイウェイウェイ、貴族的な趣味ではなくして、普通に生きていくための文学の言葉というのは、そうした都合によって慣習づけられてきた使い方の裹文字でないとあかぬのではないか、なんてこと思って、日頃、そこいらのことをあまり考えず、自分の甘い設定にとって都合のよい言葉だけを使っていることを反省するのである。
そうした小説の言葉は、都合よく、具合よく設定された、その設定をさっきも言うようにボコボコにするが、その手つきはあぐまでも楽しげで、諧謔(かいぎゃく)に満ちているので、小説に描かれる状況がけっこう悲惨であるのにも読んでいる間中、愉悦・愉楽があり、読み終わると、都合のよい言葉だけを選んで組み合わせて生きるうちに身体に溜まった言葉の毒素が分解されて解脱したような気になれて、よい本であるなあと思いました。想いました。
ALL REVIEWSをフォローする