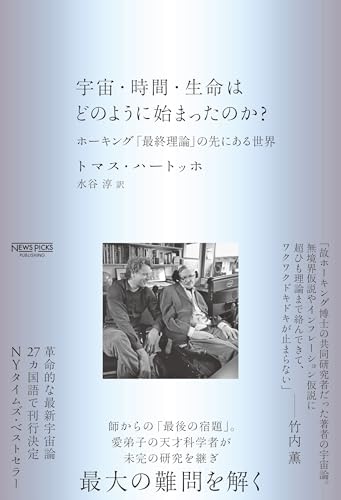書評
『文学は地球を想像する エコクリティシズムの挑戦』(岩波書店)
エコクリティシズムとは「文学と物理的環境の関係についての研究」である。人間活動の地球生命維持システムへの破壊的影響に対する不安を、地球を守る運動にはせず、そこでの地球はどのような見地から捉えられているかと文学研究の立場から斬りこむのだ。そこには、「環境の危機は想像力の危機である」という認識がある。その通りだ。
まず、工業化による自然と人間性の侵蝕を扱ったH・D・ソローの『森の生活』などから近代化が目指す「進歩の文化」に対する「生存の文化」を掘り起こす。それは、自然と都市を対立させず、都市にも自然を見ることにつながる。灰谷健次郎の『兎の眼』に象徴されるこの見方は、想像力の危機は経験の衰退によると教える。これもその通りだ。
次いで、石牟礼道子の『苦海浄土』にある個体を超えてつながるいのちへの信頼、梨木香歩が描く節度ある豊かさに見る幸福など、重要な視点が示される。放射能汚染、人工知能などが問題になる人新世には、カズオ・イシグロの『クララとお日さま』、多和田葉子の「献灯使」がある。全方位への意識と世代をこえる協働が必要な今、文学は役に立つ。
まず、工業化による自然と人間性の侵蝕を扱ったH・D・ソローの『森の生活』などから近代化が目指す「進歩の文化」に対する「生存の文化」を掘り起こす。それは、自然と都市を対立させず、都市にも自然を見ることにつながる。灰谷健次郎の『兎の眼』に象徴されるこの見方は、想像力の危機は経験の衰退によると教える。これもその通りだ。
次いで、石牟礼道子の『苦海浄土』にある個体を超えてつながるいのちへの信頼、梨木香歩が描く節度ある豊かさに見る幸福など、重要な視点が示される。放射能汚染、人工知能などが問題になる人新世には、カズオ・イシグロの『クララとお日さま』、多和田葉子の「献灯使」がある。全方位への意識と世代をこえる協働が必要な今、文学は役に立つ。
ALL REVIEWSをフォローする