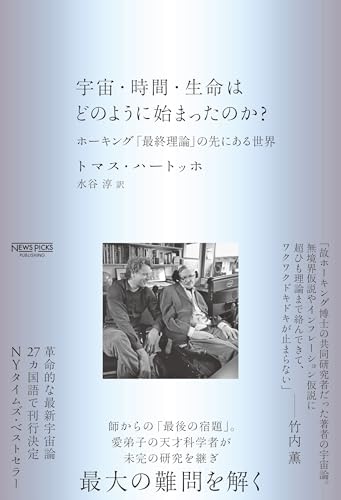書評
『月: 人との豊かなかかわりの歴史』(白水社)
人の願いと不安を反映する「鏡」
七曜というか曜日の七つの名は月、火、水…と、七つの「惑星」の名前からとられているが、そう指摘されないとわからない。なぜそうなのかなど見当もつかない。英語で「マンデー」という語は綴(つづ)りから見当がつくが、ムーン・デー、文字通り「月」曜なのである。最近エコ・エネルギー流行の中で太陽を言うラテン語系の「ソーラー」という言葉が有名だが、対応して月は「ルーナ」であり、形容詞はルナティック。これは月のという意味と同じくらい狂った、狂気のという意味で使われる。並行して「ムーニー」、月のという言葉も口語では狂った、とか「いかれた」という意味に使う。なぜか。そう、日本語でも「月」は「憑(つ)き」に由来するのだとか。
曜日決定や計時法・暦法に関わる知識がないと、あるいは地上の人事と宇宙の運行とが密に関係していると考える魔術的天文観が科学的天文学以前に延々と存在していた事情を知らないと、右のような月をめぐるイロハにだって答えられない。月の発する「憑き」の霊気が人の頭の中に流れこんで人を狂わせる。気が「中に流れこむ」のでこの謎の力を「インフルエンス」と呼んだ。ただ「影響」と訳して足れりとはいかないわけだ。
月をめぐるこういう雑学、民間伝承の宝庫、というか百科事典の娯(たの)しみに満ちている。一方では一九六九年のアポロ月面着陸で月を幻想から科学に拉致する結果になる月の科学史の、ツボを押えた記述がある。啓蒙的な科学ライターとしての著者の冴(さ)えは、現代の科学的と称する宇宙観も、実は古代人が月にウサギの姿を見なければならず、月を女神として捉えざるをえなかったように、実はある時代、ある文化の願いや不安が反映されたものであるという一点において実は何のちがいもないのだという気分にさせてくれるところだ。今「反映」といってしまったが、地上の文化に一対一に向きあう月ほど、人間が自分について考えるための鏡としてふさわしいものはないはずだ。M・ニコルソンの『月世界への旅』、松岡正剛『ルナティックス』とともに、博識と洞察に驚かされる月の博物学の名作。訳文はあくまで読みやすい。
ALL REVIEWSをフォローする
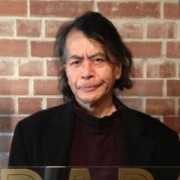





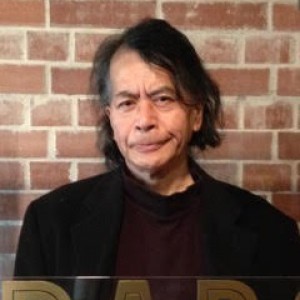
![[図説]100のトピックでたどる月と人の歴史と物語](https://m.media-amazon.com/images/I/517NxrWrasS._SL500_.jpg)