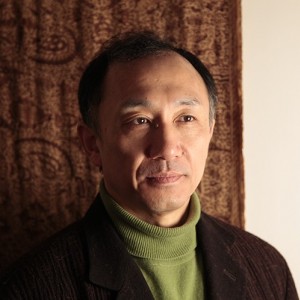書評
『安全神話崩壊のパラドックス―治安の法社会学』(岩波書店)
犯罪増はなく、境界の崩れが不安呼ぶ
リストラが横行し、年金制度も破綻(はたん)が予感されている。牛海綿状脳症(BSE)騒動で食の安心も脅かされた。加えて、「日本には犯罪が少ない」という安全神話も揺らぎつつある。まったく不安だらけだぜ、というのが国民の一般的な心情だろう。ところがこと犯罪に関しては増えても凶悪化してもいない、と著者は言う。それでいて我々は、皮膚感覚としては確かに安全が脅かされていると感じる。なぜだろう? 本書はこの謎を、法社会学の視点から切れ味鋭く解き明かす。
まず、グラフを駆使しつつ事実が示される。一般刑法犯は近年急増しているが、自転車盗が急増部分で、除外すると微増にすぎない。凶悪犯はというと、殺人は50年代から減り続けてこの10年は横ばい。強盗は急増しているものの、ひったくりや集団でのカツアゲを統計に組み込んだせい。検挙率が急降下しているが、ほぼ窃盗犯検挙率の低下に相当している。警察が、軽微な余罪の追及には人員を回さなくなったかららしい。意外さに、あっけにとられた。
後半が、謎解きである。ポイントは、刑法の運用。日本では、累犯者はヤクザの世界など「境界」の向こうに隔離されるか、もしくは刑事や保護官といった「現場の鬼」が彼らにサシで対面しつつ謝罪させ、こちらの社会へ復帰する世話をしてきた(個別主義)。そうした裁量によって犯罪を「ケガレ」として一括する境界線が維持され、安全神話が語られた、という仮説である。犯罪そのものも、繁華街や夜間という一般人が近づかぬ領域で起きていた。境界が崩れ、「現場の鬼」が人手不足になって、「住宅街」で「昼間」に犯罪を見聞きするようになったのが、我々の皮膚感覚を過度に刺激するのだ、と。
経済にせよ、不安対策は法の透明な運用で、というのが昨今の風潮である。本書の仮説が正しければ、犯罪についてはそれだと皮膚感覚上、逆効果になるはず。
安易な改革に警鐘を鳴らす力作である。
朝日新聞 2004年10月24日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする