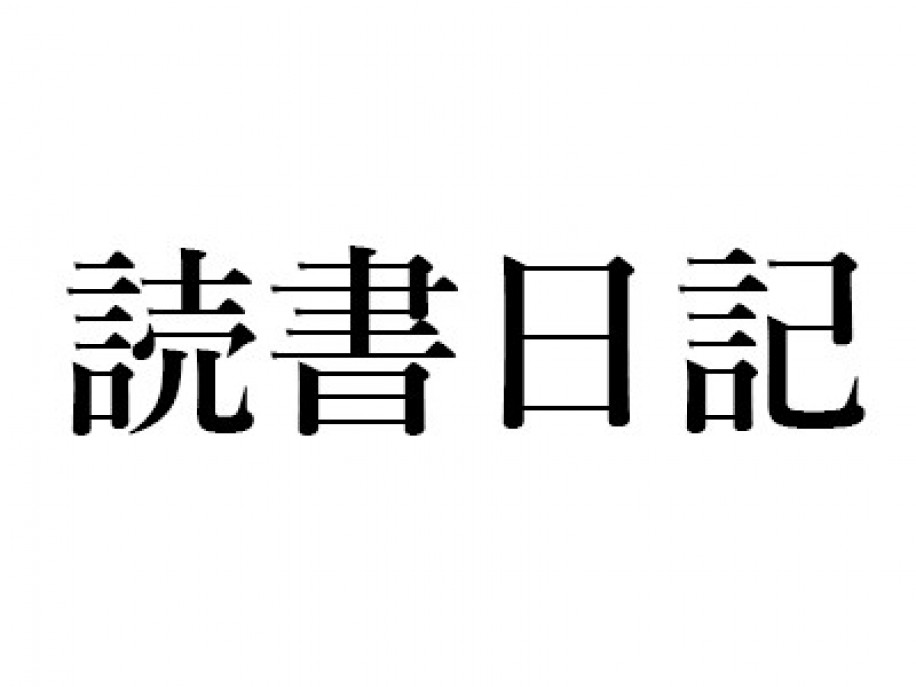書評
『近代日本の社会科学―丸山眞男と宇野弘蔵の射程』(NTT出版)
後発帝国型学問
大正時代のおわりにこんなことがいわれた。最も頭の悪いのが反動学生、つぎに頭の悪いのが文学に走る。最も頭のよい学生は社会科学を研究する、と。それまで知的青年といえば文学青年だったのが、社会科学青年にとってかわられたのである。ここで社会科学というのは、社会科学一般ではなくマルクス主義をいう。本書は、全共闘世代までの知的青年を魔力のごとくひきつけた日本の社会科学の論理の組み立てを山田盛太郎(やまだもりたろう・一八九七~一九八〇)、宇野弘蔵(うのこうぞう・一八九七~一九七七)、丸山眞男などのスター学者たちの学説にさぐり、近代日本の社会科学の特徴を解明している。著者の読解法のかなめになるのが「発展的疎外」という近代日本の立ち位置。環大西洋諸国は、日本にとっての「発展」モデルでありながら、同時に、欠如や相違、脅威を喚起させ、「疎外」をもたらしたという日本の後発帝国性のことである。こうした立ち位置が日本の社会科学に、先進と後進、普遍と特殊、資本主義的と封建的などの二重の思考軸をあたえてきたとする。
マルクス主義陣営において、資本主義という普遍だけでなく、日本型封建制の残滓という特殊をもくみこんだ講座派が労農派(普遍主義)よりもはるかに大きな影響力をもったのも、コミンテルン(共産主義インターナショナル)による示唆と支持だけでなく、著者のいう「発展的疎外」という後発帝国日本の立ち位置によるところが大きかったのではないかとおもえてくる。
本書はこう締めくくられる。
日本はたしかに普遍へと媒介されねばならないが、それによって、普遍自体も実現されるという、そのような特殊だったのでないか。(二八七~二八八頁)
たしかに昭和戦前期の京都学派を中心にした近代の超克論は、特殊(日本)を媒介にあらたな普遍(世界文化)をめざしたものだった。キリストや釈迦の説くところは日本精神に含まれているとする国粋主義は、特殊を一挙に普遍化する荒業である。メタ学問論だからすらすらとは読めないが、読後、うねうねとした道を高みから一望にしたときのような爽快感がある。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする