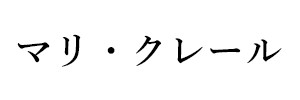書評
『愛と幻想のファシズム』(講談社)
この作品の性格をひとことで言い当てようとすると、ふんだんに毒を含んだハードボイルド風の劇画小説ということになる。まず毒ということからはじめてみる。ひとつは主人公であるハンター上りのトウジのもっている理念が毒だ。トウジは狩猟社会が人間の理想社会で、強い獣と獣を追って仕留める頑強な狩猟人だけが生き残り、人間を含めて弱い動物、愚かな動物、強くてもスポイルされた動物は、すぐに自然のなかで殺されるか、衰弱死する運命になる。だから強くて美しい動物と狩猟人だけが生きられる社会だった。ところが農耕社会にはいって弱者も病人も奴隷になって食料を栽培し、育て、生き延びるようになり、やがて生存を維持するために、弱者や病人は徒党を組み、要求するようになった。だからもう一度狩猟社会の理想を再生させるために、弱者や不適応者を絶滅しなくてはいけない。これが主人公トウジの毒々しい理念だ。この主人公の理念がもつ毒は、単純、明快、幼稚にうまく設定されていて、いかにも劇画風に物語を進行させる。もうひとつ毒がある。主人公トウジと相手役「ゼロ」を中心に組み立てられた「狩猟社」という政治的な結社の性格だ。この結社は、じぶんたちに不都合な人物や集団があると、ハンターが動物をうち殺すようにためらうことなく暗殺したり、薬物を使って廃人にしてしまう。もちろんおなじ結社の仲間でも衰えたり、異和感を示したり、脱落しそうに見えると平気で抹殺してゆく。これも作品を毒ある劇画にしている要素だ。
このふたつの毒は、作品の物語が展開するキイになっていて、このキイを節目のところで行使しないと、物語がさきに進めない仕掛けになっている。作品を劇画風に面白くしているのはこのキイだし、また作品を主人公トウジとまわりをとりまく結社が、この毒をふりまきながら、しだいに雪だるまみたいに膨らんでゆく単純な物語にしているのも、このキイのせいだといえる。
平凡な無名の人たちが、正義や解放の理念を看板にかかげながら、支配者が陰でやっている監視と圧殺と差別と不正に我慢できなくなり、しだいに結束をかためて、強制支配する政府を追いつめて、もうすこしで解体させるところまでいきながら、武力で押しつぶされてしまった、そういう物語を近年ポーランドの連帯の運動とその構想のなかでじっさいに見てきた。
村上龍もそういう物語を紙の上でシミュレーションしてみたかったにちがいない。そういう鬱屈のモチーフを面白い物語にするには、主人公たちやその結社に単純、明快、幼稚で、誰にもわかりやすい毒のある理念と、容易に人間を抹殺できる暗殺やテロの暗闇をつけ加えることがいちばんやり易い。そのためにスターリンがこしらえた幼稚なファシズムの規定を使い、ドイツのナチやイタリアのファッショの成長物語を、借りてきた。作者は通念にのりすぎたきらいがあり、そのため作品の物語のキイを幼稚にしている。もちろん半分はわざとそうやって諷刺を利かせているつもりだ。村上龍がスターリンがこしらえた幼稚な悪玉仕立てのファシズム論などに惑わされないで、ほんとうの実感と意志とやむをえない支配にたいする反抗から、無名のひとたちが手をたずさえて、しだいに連帯をひろげ、ついに知識のつくった迷信からだれもが正義だと思い込んで、どんなひどいことをやっても許容してきた思想管理システムを追いつめて膨らませてゆく物語を、丁寧に、暗殺や薬殺や弱者抹殺などの毒を借りずに構築できたら、劇画的な面白さは減少しただろうが、作品としてはもっと優れたものになったに違いない。それは惜しいことだが、作者は作者に固有な残酷趣味や鬱屈や思い込みがあるだろうから、わたしはただ無いものねだりをしているだけかも知れない。
このあと、よくここまでやったなと感じるところをすこし挙げてみる。
主人公のハンター、トウジの相棒の「ゼロ」を中心につくられた結社「狩猟社」が、最初にぶつかる事件は「世界恐慌」である。発展途上国(後進国)の累積赤字が巨大な額に達し、それがますます進行する一方の徴候しかないため、先進国が債務を帳消しするような贈与を、一挙に行使するほかに、これらの途上国(後進国)が破滅を免れる方法がない。そんな危機感が切迫し、頂点に達したときに近未来の「世界恐慌」は起る。先進国の金融機関は融資の一時停止を主張しはじめ、企業や商社は取引きの打ち切りをいいはじめ、発展途上国(後進国)の経済混乱は、内乱の様相を呈しはじめる。ベネズエラでは軍事クーデタが成功して、債務支払義務の放棄を宣告する。メキシコやブラジルでは、先進国の技術顧問団や産業設備の引き上げがおこる。国家よりも強大な力をもった世界最大の多国籍産業の連合体「ザ・セブン」は猛烈な勢いで、世界の産業を傘下に収まるものと、「ザ・セブン」の圏外に蹴おとしてしまう企業とにふるい分けはじめる。主人公トウジたちの結社「狩猟社」は、最後はどの国家よりも強力になってしまったこの経済のシステム「ザ・セブン」に肉迫して倒したいとかんがえる。そして「ザ・セブン」傘下の「シャノン・フーズ杉の原研究所」の労働争議のとき、研究所の施設を護衛する仕事を「ザ・セブン」から受け負ったのを契機に、右翼の妨害、機動隊の監視のなかで、「狩猟社」の武力組織「クロマニヨン」によってす速い行動力と実力を発揮して、労働組合と左右両翼の政治勢力の派遣員を実力で有無をいわせぬ冷静さで排除し、鎮圧しつくして、最初の実力を世界中に示唆する。それを契機に結社への加入者がふえ、依頼者と国際的な評価と、ファシズムというレッテルが「狩猟社」のまわりに渦巻く。暗殺や薬殺の毒をふりまきながら、弱者抹殺、快楽とぜいたくと財力の讃美の理念を行使して、しだいに独裁勢力への拡大の道を歩みはじめる。
トウジと「ゼロ」のふたりからはじまった「狩猟社」が、しだいに大きな勢力になってゆく過程を、けっして無いとはいえない近未来の世界の経済と政治と軍事の具象的な条件のなかで、できるかぎりの緻密さで描きだしている。それは小説というよりも大説であり、文学作品というよりも言葉で描いた劇画作品といったほうがよい。よくここまで生々しくいかにもありそうな触感を読者に与えながら描ききったものだと感心させる。
もうひとつ作者の現状認知の力を感じさせるのは、「狩猟社」の結社に加入した情報科学にくわしいメンバー、飛駒勇二が担当のエレクトロニクス・テロリズムの可能性について語るところだ。
勇二はトウジに語る。日本を引っ掻きまわすのも簡単だけど、十倍の予算と時間を半年ほどもらえれば米国でさえも破滅させられる。それには小型になり集中的になった空軍機や旅客機の離着陸の誘導装置のコンピュータの連動を切断することだ。すると一日に百件の飛行機事故を起こさせることができるし、この種のエレクトロニクス・テロリズムはいくらでも発生させることが、技術的に可能だと勇二は語る。ほんとうは壊すことが簡単なものは、再生させることも簡単だから、そういうエレクトロニクス・テロリズムは容易にできるし、また容易に防げるという両義性をいつでももっている。だから勇二のいうほどのおおきな意味はない。それでも作者のこの着想には、テロリズムの概念を、すぐに一人一殺や、ビル爆破や、要人暗殺や、ハイジャックにおいてかんがえる現在の世界の左右両翼のテロリストたちの概念に、いわば風穴をあけている印象を与えるに充分だ。ようするに作者は作中の主人公トウジたちの結社が発生してから、膨張をはじめ、ついに国際的な政治勢力にまで発展してゆく過程を、できるかぎり近未来のじっさいに起りうるリアリティをもった場面を背景に構築するために、作家としての描写力を総動員し、経済的な現状認識を緻密にするために、じつによく勉強している。それだけに野心的であることは間違いない。
ところで、この作品は、大説でなく、小説としての部分はどうなっているのだろうか。わたしにはどう好意的にかんがえても、主人公トウジの人格と理念に、カリスマ的な魅力(魔力)があるように描けているとはおもえない。作中で主人公はじぶんの魅力についてこう語りだすところがある。「オレには権力への欲などない、オレはハンターだ、日本国の指導者になりたいなどと一度も思ったことはない、それならば、なぜ、ここにいる洞木を始めとして、二十万の党員がオレを支持するか、わかるか? 岩佐、どうしてだと思う?」そして主人公はじぶんでそれを説明しだす。「俺の言葉や声のさらに奥にある熱い核に触れて」人々が支配されるのだという。その熱い核に触れると、誰でも身にまとった名前や意味や情報や身分をすてて、風が渦を巻く荒野のなかに放たれてしまって、いままであったはずのプライドをたち切られて不快の極限に達するが、そこで逃げ道をもとめて屈服する。そして不快感が逆転して信者に変る。トウジはそう語るのだが、描写そのもので主人公トウジにそんな魅力のあるイメージは浮んでこない。むしろ相棒の「ゼロ」の方は、さすがと思えるほど、よく描かれている。生きる意欲をなくして北極圏の町イヌヴィックでトウジと出会い、トウジにスポイルされた熊だと罵られて、ヘリコプターからつき落されそうになり、遂に自殺しようと思ったところをおし止められて、そのときを契機に心理的な再生に転じる。トウジと「狩猟社」を結成する。結社がおおきくなるにつれて、暗殺、薬殺、陰謀者に平気になっていく雰囲気に、無意識が馴染むことができないで、いわば動物のように衰弱してゆく。トウジとふたりで北海道へ行って、また極限の自然体験を経たあとで、心理的に再生して、「狩猟社」の本格的な宣伝担当者として残酷な宣伝の方法でばく進してゆき、「狩猟社」が本格的な結社として国内でも国際的にも認められるようになったとき、また生の衰弱からとうとう自殺してしまう。この「ゼロ」の生への欲望の衰弱は、じぶんのなかの倫理を無意識の領域に追いこめてそれが極限にきたときに起ることになっている。それは「ゼロ」という人物をありうべき鮮明な心理的な存在にさせていて、小説としてのこの作品をおおきくささえる支柱になっている。
【この書評が収録されている書籍】
このふたつの毒は、作品の物語が展開するキイになっていて、このキイを節目のところで行使しないと、物語がさきに進めない仕掛けになっている。作品を劇画風に面白くしているのはこのキイだし、また作品を主人公トウジとまわりをとりまく結社が、この毒をふりまきながら、しだいに雪だるまみたいに膨らんでゆく単純な物語にしているのも、このキイのせいだといえる。
平凡な無名の人たちが、正義や解放の理念を看板にかかげながら、支配者が陰でやっている監視と圧殺と差別と不正に我慢できなくなり、しだいに結束をかためて、強制支配する政府を追いつめて、もうすこしで解体させるところまでいきながら、武力で押しつぶされてしまった、そういう物語を近年ポーランドの連帯の運動とその構想のなかでじっさいに見てきた。
村上龍もそういう物語を紙の上でシミュレーションしてみたかったにちがいない。そういう鬱屈のモチーフを面白い物語にするには、主人公たちやその結社に単純、明快、幼稚で、誰にもわかりやすい毒のある理念と、容易に人間を抹殺できる暗殺やテロの暗闇をつけ加えることがいちばんやり易い。そのためにスターリンがこしらえた幼稚なファシズムの規定を使い、ドイツのナチやイタリアのファッショの成長物語を、借りてきた。作者は通念にのりすぎたきらいがあり、そのため作品の物語のキイを幼稚にしている。もちろん半分はわざとそうやって諷刺を利かせているつもりだ。村上龍がスターリンがこしらえた幼稚な悪玉仕立てのファシズム論などに惑わされないで、ほんとうの実感と意志とやむをえない支配にたいする反抗から、無名のひとたちが手をたずさえて、しだいに連帯をひろげ、ついに知識のつくった迷信からだれもが正義だと思い込んで、どんなひどいことをやっても許容してきた思想管理システムを追いつめて膨らませてゆく物語を、丁寧に、暗殺や薬殺や弱者抹殺などの毒を借りずに構築できたら、劇画的な面白さは減少しただろうが、作品としてはもっと優れたものになったに違いない。それは惜しいことだが、作者は作者に固有な残酷趣味や鬱屈や思い込みがあるだろうから、わたしはただ無いものねだりをしているだけかも知れない。
このあと、よくここまでやったなと感じるところをすこし挙げてみる。
主人公のハンター、トウジの相棒の「ゼロ」を中心につくられた結社「狩猟社」が、最初にぶつかる事件は「世界恐慌」である。発展途上国(後進国)の累積赤字が巨大な額に達し、それがますます進行する一方の徴候しかないため、先進国が債務を帳消しするような贈与を、一挙に行使するほかに、これらの途上国(後進国)が破滅を免れる方法がない。そんな危機感が切迫し、頂点に達したときに近未来の「世界恐慌」は起る。先進国の金融機関は融資の一時停止を主張しはじめ、企業や商社は取引きの打ち切りをいいはじめ、発展途上国(後進国)の経済混乱は、内乱の様相を呈しはじめる。ベネズエラでは軍事クーデタが成功して、債務支払義務の放棄を宣告する。メキシコやブラジルでは、先進国の技術顧問団や産業設備の引き上げがおこる。国家よりも強大な力をもった世界最大の多国籍産業の連合体「ザ・セブン」は猛烈な勢いで、世界の産業を傘下に収まるものと、「ザ・セブン」の圏外に蹴おとしてしまう企業とにふるい分けはじめる。主人公トウジたちの結社「狩猟社」は、最後はどの国家よりも強力になってしまったこの経済のシステム「ザ・セブン」に肉迫して倒したいとかんがえる。そして「ザ・セブン」傘下の「シャノン・フーズ杉の原研究所」の労働争議のとき、研究所の施設を護衛する仕事を「ザ・セブン」から受け負ったのを契機に、右翼の妨害、機動隊の監視のなかで、「狩猟社」の武力組織「クロマニヨン」によってす速い行動力と実力を発揮して、労働組合と左右両翼の政治勢力の派遣員を実力で有無をいわせぬ冷静さで排除し、鎮圧しつくして、最初の実力を世界中に示唆する。それを契機に結社への加入者がふえ、依頼者と国際的な評価と、ファシズムというレッテルが「狩猟社」のまわりに渦巻く。暗殺や薬殺の毒をふりまきながら、弱者抹殺、快楽とぜいたくと財力の讃美の理念を行使して、しだいに独裁勢力への拡大の道を歩みはじめる。
トウジと「ゼロ」のふたりからはじまった「狩猟社」が、しだいに大きな勢力になってゆく過程を、けっして無いとはいえない近未来の世界の経済と政治と軍事の具象的な条件のなかで、できるかぎりの緻密さで描きだしている。それは小説というよりも大説であり、文学作品というよりも言葉で描いた劇画作品といったほうがよい。よくここまで生々しくいかにもありそうな触感を読者に与えながら描ききったものだと感心させる。
もうひとつ作者の現状認知の力を感じさせるのは、「狩猟社」の結社に加入した情報科学にくわしいメンバー、飛駒勇二が担当のエレクトロニクス・テロリズムの可能性について語るところだ。
勇二はトウジに語る。日本を引っ掻きまわすのも簡単だけど、十倍の予算と時間を半年ほどもらえれば米国でさえも破滅させられる。それには小型になり集中的になった空軍機や旅客機の離着陸の誘導装置のコンピュータの連動を切断することだ。すると一日に百件の飛行機事故を起こさせることができるし、この種のエレクトロニクス・テロリズムはいくらでも発生させることが、技術的に可能だと勇二は語る。ほんとうは壊すことが簡単なものは、再生させることも簡単だから、そういうエレクトロニクス・テロリズムは容易にできるし、また容易に防げるという両義性をいつでももっている。だから勇二のいうほどのおおきな意味はない。それでも作者のこの着想には、テロリズムの概念を、すぐに一人一殺や、ビル爆破や、要人暗殺や、ハイジャックにおいてかんがえる現在の世界の左右両翼のテロリストたちの概念に、いわば風穴をあけている印象を与えるに充分だ。ようするに作者は作中の主人公トウジたちの結社が発生してから、膨張をはじめ、ついに国際的な政治勢力にまで発展してゆく過程を、できるかぎり近未来のじっさいに起りうるリアリティをもった場面を背景に構築するために、作家としての描写力を総動員し、経済的な現状認識を緻密にするために、じつによく勉強している。それだけに野心的であることは間違いない。
ところで、この作品は、大説でなく、小説としての部分はどうなっているのだろうか。わたしにはどう好意的にかんがえても、主人公トウジの人格と理念に、カリスマ的な魅力(魔力)があるように描けているとはおもえない。作中で主人公はじぶんの魅力についてこう語りだすところがある。「オレには権力への欲などない、オレはハンターだ、日本国の指導者になりたいなどと一度も思ったことはない、それならば、なぜ、ここにいる洞木を始めとして、二十万の党員がオレを支持するか、わかるか? 岩佐、どうしてだと思う?」そして主人公はじぶんでそれを説明しだす。「俺の言葉や声のさらに奥にある熱い核に触れて」人々が支配されるのだという。その熱い核に触れると、誰でも身にまとった名前や意味や情報や身分をすてて、風が渦を巻く荒野のなかに放たれてしまって、いままであったはずのプライドをたち切られて不快の極限に達するが、そこで逃げ道をもとめて屈服する。そして不快感が逆転して信者に変る。トウジはそう語るのだが、描写そのもので主人公トウジにそんな魅力のあるイメージは浮んでこない。むしろ相棒の「ゼロ」の方は、さすがと思えるほど、よく描かれている。生きる意欲をなくして北極圏の町イヌヴィックでトウジと出会い、トウジにスポイルされた熊だと罵られて、ヘリコプターからつき落されそうになり、遂に自殺しようと思ったところをおし止められて、そのときを契機に心理的な再生に転じる。トウジと「狩猟社」を結成する。結社がおおきくなるにつれて、暗殺、薬殺、陰謀者に平気になっていく雰囲気に、無意識が馴染むことができないで、いわば動物のように衰弱してゆく。トウジとふたりで北海道へ行って、また極限の自然体験を経たあとで、心理的に再生して、「狩猟社」の本格的な宣伝担当者として残酷な宣伝の方法でばく進してゆき、「狩猟社」が本格的な結社として国内でも国際的にも認められるようになったとき、また生の衰弱からとうとう自殺してしまう。この「ゼロ」の生への欲望の衰弱は、じぶんのなかの倫理を無意識の領域に追いこめてそれが極限にきたときに起ることになっている。それは「ゼロ」という人物をありうべき鮮明な心理的な存在にさせていて、小説としてのこの作品をおおきくささえる支柱になっている。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする