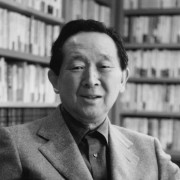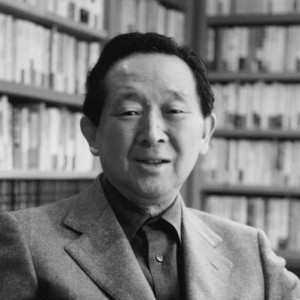書評
『小さな貴婦人』(新潮社)
小説にとって繊細な描写は何のために必要なのだろう。
作家によっては、現実(と彼が思いこんでいるもの)のために、やや偏執的な熱心さで描写が続けられる場合がある。また、読者の心理を特定の空間に誘導するために書いているのではないかと思われる作家もいる。
吉行さんの場合はそのいずれでもない。彼女はただ自分の気分によって書く。彼女は常にどうしようもなく彼女自身なのだ。そのために詩の中のフレーズのように、突然「切符の買い方が分からなくなって」しまったり、「かくしきれない傷口を、小さな両手でおさえたまま」立っていなければならなくなったりする。彼女は狼狽(ろうばい)して現実の入口を見付けなければいけないと思う。指で壁を撫(な)でたり、目を四方八方へ放って、そこに棚(たな)や窓や書き割りのような改札口を発見する。だが、どのような物体も彼女に入口を教えてくれない。
するとその混迷のなかから、煙のように動くものが現れて彼女に近づいてくる。それは「小さな貴婦人」のなかの「雲」、と呼ばれる猫(ねこ)だったり、「赤い花を吐いた猫」のなかの「ダイアナ」だったりする。彼等は、あったかもしれない総(すべ)ての現実の代替物である。
たとえば「雲」は空のない都会の空だ。「雲」の喉(のど)から出る声は、海のない地方の波の音なのだ。
「雲」は去勢された牡(おす)であることによって注意深く現実性を捨象されている。だから「小さな貴婦人」と呼んでもいいのだ。彼女のお相手をする青年は肉体を持っていてはならない。「窓辺の雲」のなかの「ダイアナ」も「少年からどろどろした男」にはならず、女神に変身するのである。
主人公の私は、死んだ「雲」の骨を埋める土地を見付けることができない。そんな都合のいい庭はないから、主人公は記憶のなかに埋めてやらなければならない。
しかし、埋葬が不可能だったのは土地がなかったからではなく、「雲」自身が肉体を持っていなかったためではないか。そう思い出した時、読者はすでに深く吉行さんの世界に入り込んでしまっているのだ。
「小さな貴婦人」のなかには、主人公の私に似ているけれども、何処(どこ)か決定的に異っている老女流詩人Gが登場する。Gは明らかな老化現象を背負っていて、自己愛に固く結びつけられた、記憶と名付けられている風景に浸っている。Gにとって「小さな貴婦人」は自分の幼い頃(ころ)それ自体なのだ。だから店頭から、ぬいぐるみの「小さな貴婦人」が消えてしまった時、彼女は歎(なげ)くけれども、そのことによって事態は少しも変らないのである。
吉行さんの作品に屢(しばしば)々(しばしば)現れる、人間に変身した猫は、いずれも変身譚(たん)につきものの怨念(おんねん)を纏(まと)っていない。彼等は情念の屈折を発条(ばね)にして変身したのではないのだ。だから彼等は境界を意識せずに人の世界と人間の世界を往復することができる。ここにはシャーマニズムの影響はない。つまり吉行さんの猫は肉体を持たないから、動物霊が人に憑依(ひょうい)した結果生れた生物ではないのだ。
変身を描くに際しての、この情念ではなく感性の優位性は、夢と現実の世界の共存を牧歌的に可能にする。その意味で吉行さんの小説は彼女の詩の世界から真直に続いている。
「青い部屋」「幻影」「夢のなかで」等の詩集を構成する諸篇は、いずれも繊細なイメージのなかに作者が息づいている小品群であって、主題が空間を構成し、そこに現実とは対立する世界が形成されるといった詩とは異る。世界は彼女の内側にのみ在る。
詩を書いている人の小説には、二つの型があるように思われる。一つは詩とは全く異質の場で書かれる場合である。勿論(もちろん)、作者固有のポエジーは共通しているのだが、空間形成の手法が切り変えられているのである。もう一つは、まさしく同じ文脈のなかで小説世界が創造される型である。言うまでもなく吉行さんは後者に属する。この特徴は評論においてさえ一貫している。これはかなり珍しいことであって、それは彼女の持っている作品世界の感性が、一見弱々しく見えて実は極めて強靱(きょうじん)な自己完結性に支えられていることを現わしている。そこに彼女の文学的営為の独自の魅力も、果敢(はか)なくあえかな印象の原因も存在するようである。
それならば、彼女が描こうとしたのは、ただ彼女の触手が捕えた、移りゆく影だけなのであろうか。
「猫の殺人」「雲とトンガ」にはじまる五つの短篇を読むと、常に烈(はげ)しい現身忌避の通奏低音が鳴っているのに気付かされる。人間は自然を失った時、喪失を歎いて挽歌(ばんか)を奏(かな)でるかわりに、一層鋭く自然を拒否し、喪失を主体の枠内(わくない)において認めまいとする場合がある。自分はもともと自然なんか好きではなかったと言い張ることによって、自らの主体を傷つけまいと身構えるのだ。吉行さんは長い間このように哀(かな)しい誇りのなかに生きてきたように見える。
誇りは数々の美しいメルヘンを生んだ。しかし受賞作となった最後の短篇の終りに「きっとGさん、小さな貴婦人のメルヘンをお書きになるわ」と主人公に呟(つぶや)かせた時、彼女自身が今まで住んでいた牧歌的世界からの旅立ちを決意したように思われる。新しい世界が実はどろどろした現身の世であっても、彼女はもう決してたじろがない優しさでそこへ歩いていかなければならないのだ。
【この書評が収録されている書籍】
作家によっては、現実(と彼が思いこんでいるもの)のために、やや偏執的な熱心さで描写が続けられる場合がある。また、読者の心理を特定の空間に誘導するために書いているのではないかと思われる作家もいる。
吉行さんの場合はそのいずれでもない。彼女はただ自分の気分によって書く。彼女は常にどうしようもなく彼女自身なのだ。そのために詩の中のフレーズのように、突然「切符の買い方が分からなくなって」しまったり、「かくしきれない傷口を、小さな両手でおさえたまま」立っていなければならなくなったりする。彼女は狼狽(ろうばい)して現実の入口を見付けなければいけないと思う。指で壁を撫(な)でたり、目を四方八方へ放って、そこに棚(たな)や窓や書き割りのような改札口を発見する。だが、どのような物体も彼女に入口を教えてくれない。
するとその混迷のなかから、煙のように動くものが現れて彼女に近づいてくる。それは「小さな貴婦人」のなかの「雲」、と呼ばれる猫(ねこ)だったり、「赤い花を吐いた猫」のなかの「ダイアナ」だったりする。彼等は、あったかもしれない総(すべ)ての現実の代替物である。
たとえば「雲」は空のない都会の空だ。「雲」の喉(のど)から出る声は、海のない地方の波の音なのだ。
「雲」は去勢された牡(おす)であることによって注意深く現実性を捨象されている。だから「小さな貴婦人」と呼んでもいいのだ。彼女のお相手をする青年は肉体を持っていてはならない。「窓辺の雲」のなかの「ダイアナ」も「少年からどろどろした男」にはならず、女神に変身するのである。
主人公の私は、死んだ「雲」の骨を埋める土地を見付けることができない。そんな都合のいい庭はないから、主人公は記憶のなかに埋めてやらなければならない。
しかし、埋葬が不可能だったのは土地がなかったからではなく、「雲」自身が肉体を持っていなかったためではないか。そう思い出した時、読者はすでに深く吉行さんの世界に入り込んでしまっているのだ。
「小さな貴婦人」のなかには、主人公の私に似ているけれども、何処(どこ)か決定的に異っている老女流詩人Gが登場する。Gは明らかな老化現象を背負っていて、自己愛に固く結びつけられた、記憶と名付けられている風景に浸っている。Gにとって「小さな貴婦人」は自分の幼い頃(ころ)それ自体なのだ。だから店頭から、ぬいぐるみの「小さな貴婦人」が消えてしまった時、彼女は歎(なげ)くけれども、そのことによって事態は少しも変らないのである。
吉行さんの作品に屢(しばしば)々(しばしば)現れる、人間に変身した猫は、いずれも変身譚(たん)につきものの怨念(おんねん)を纏(まと)っていない。彼等は情念の屈折を発条(ばね)にして変身したのではないのだ。だから彼等は境界を意識せずに人の世界と人間の世界を往復することができる。ここにはシャーマニズムの影響はない。つまり吉行さんの猫は肉体を持たないから、動物霊が人に憑依(ひょうい)した結果生れた生物ではないのだ。
変身を描くに際しての、この情念ではなく感性の優位性は、夢と現実の世界の共存を牧歌的に可能にする。その意味で吉行さんの小説は彼女の詩の世界から真直に続いている。
「青い部屋」「幻影」「夢のなかで」等の詩集を構成する諸篇は、いずれも繊細なイメージのなかに作者が息づいている小品群であって、主題が空間を構成し、そこに現実とは対立する世界が形成されるといった詩とは異る。世界は彼女の内側にのみ在る。
詩を書いている人の小説には、二つの型があるように思われる。一つは詩とは全く異質の場で書かれる場合である。勿論(もちろん)、作者固有のポエジーは共通しているのだが、空間形成の手法が切り変えられているのである。もう一つは、まさしく同じ文脈のなかで小説世界が創造される型である。言うまでもなく吉行さんは後者に属する。この特徴は評論においてさえ一貫している。これはかなり珍しいことであって、それは彼女の持っている作品世界の感性が、一見弱々しく見えて実は極めて強靱(きょうじん)な自己完結性に支えられていることを現わしている。そこに彼女の文学的営為の独自の魅力も、果敢(はか)なくあえかな印象の原因も存在するようである。
それならば、彼女が描こうとしたのは、ただ彼女の触手が捕えた、移りゆく影だけなのであろうか。
「猫の殺人」「雲とトンガ」にはじまる五つの短篇を読むと、常に烈(はげ)しい現身忌避の通奏低音が鳴っているのに気付かされる。人間は自然を失った時、喪失を歎いて挽歌(ばんか)を奏(かな)でるかわりに、一層鋭く自然を拒否し、喪失を主体の枠内(わくない)において認めまいとする場合がある。自分はもともと自然なんか好きではなかったと言い張ることによって、自らの主体を傷つけまいと身構えるのだ。吉行さんは長い間このように哀(かな)しい誇りのなかに生きてきたように見える。
誇りは数々の美しいメルヘンを生んだ。しかし受賞作となった最後の短篇の終りに「きっとGさん、小さな貴婦人のメルヘンをお書きになるわ」と主人公に呟(つぶや)かせた時、彼女自身が今まで住んでいた牧歌的世界からの旅立ちを決意したように思われる。新しい世界が実はどろどろした現身の世であっても、彼女はもう決してたじろがない優しさでそこへ歩いていかなければならないのだ。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする