書評
『マロニエの花が言った』(新潮社)
パリに生きた青春群像
十九世紀末の文化的雰囲気がまだ残されていた、いわゆるベル・エポックの時代から、第一次世界大戦を経て第二次世界大戦へといたるまでのパリは、国際芸術都市というにふさわしい、きらびやかなイメージに満ちあふれていた。多少のずれはあるものの、この時期、数多くの芸術家たちがヨーロッパの首都を目指し、進むべき道を模索しながら、厳しくも実りある闘いに乗り出していった。上下二巻、数千枚におよぶ清岡卓行の『マロニエの花が言った』は、岡鹿之助、藤田嗣治、金子光晴、ロベール・デスノスという、著者がこれまでにも折に触れて敬愛の念を示してきた画家や詩人たちの青春を、不思議な縁で結ばれた同時代の群像のなかに定着しようとする、雄大な「大河小説」である。
本書の最大の魅力は、若年のころからフランスの詩や絵画や映画に強いあこがれを抱きつつも、さまざまな事情が重なって六十歳を過ぎるまで渡仏の機会を持たなかった著者自身の、パリに対する熱く澄んだ想いが、全篇に塗り込められていることだろう。それが手放しのフランス礼賛に堕さないのは、中途半端な感情移入を避けるべく、記述の対象とのあいだに節度ある距離が保たれているからだ。
とはいえ、情理をかねそなえたその冷静な行文には、しばしば絵巻の水平軸を垂直に引き裂く陽性のエロスが漂う。生涯独身を貫いた岡鹿之助を除いて、先の三人には、それぞれ芸術の質を決するほど重要な、個性的な女性との出会いがあったのだ。
藤田ならユキ、金子なら森三千代、デスノスならイヴォンヌ・ジョルジュ。創作の根底にかかわる彼女らの役割をたどるとき、著者の目はまるでみずからの女神を前にしたかのごとく輝き出し、その瞬間、言葉は詩の強度を、性愛の色を獲得する。
ホテルの窓から花盛りのマロニエを眺める序章は、ため息がでるほどに美しい。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
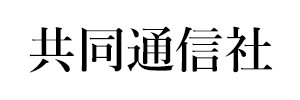
共同通信社 1999年9月
ALL REVIEWSをフォローする


































