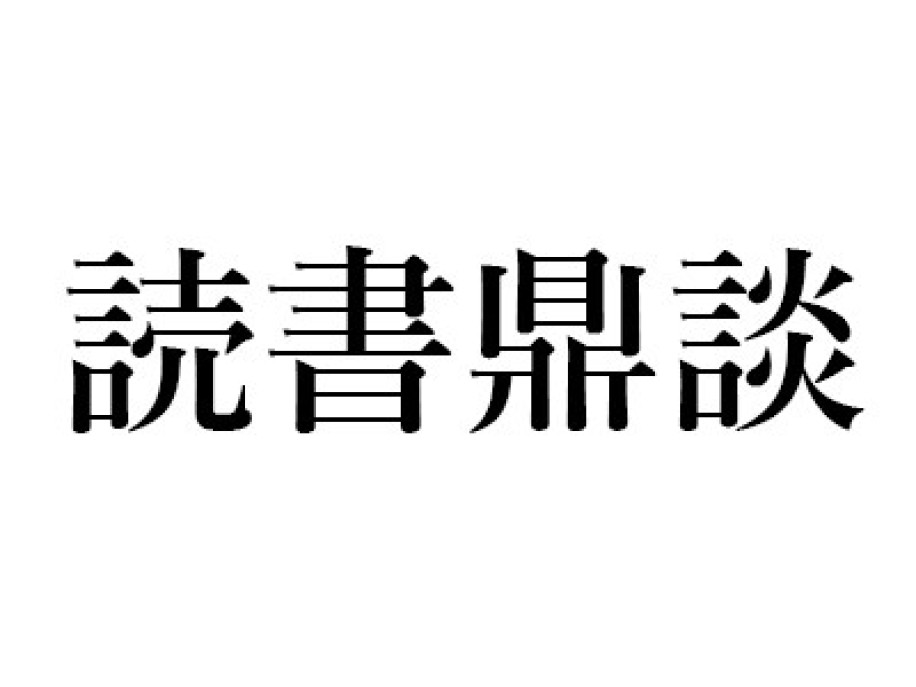書評
『色彩の世界地図』(文藝春秋)
日本の喪服は白だった
私の服装はある時期から黒で統一されてしまったが、別段、何かの喪に服しているためではない。コム・デ・ギャルソンとヨウジヤマモトのスーツが気に入ってそればかりを着るようになったからである。この二つのブランドは、女性モードの世界に禁じ手である黒を持ち込んで衝撃を引き起こしたことで知られる。日本人にとって黒に対する禁忌はそれほどでもなかったが、欧米ではローマ時代から黒は喪色と決まっていたので、モードとして黒が登場したとき、欧米人は完全に意表を衝かれたかたちとなった……と、一応の理解をしていたのだが、本書を読んで、この仮説が間違っていなかったことを知った。というのも、日本では喪色は明治時代までは黒ではなく白だったからである。これは中国の伝統を受け継いだもので、白は喪主が身につける衣装の色。男子は、生成の麻の裃、女性は白無垢というのが一般的だった。変化が起きたのは明治三十年の英照皇太后の葬儀のとき。政府は欧米式の喪服で行くことに決め、以後、黒が国の正式な喪色となったのだ。この傾向に拍車がかかったのは太平洋戦争の末期。地方では白の喪服もまだ多かったが、空襲で焼死者が続出したさい、貸衣装屋は白だと汚れやすいという理由から黒を喪服の定番としたのだ。その結果、戦後、喪服は黒と決まってしまったというわけだ。つまり、黒が喪色というのは日本人にとっては戦後の習慣にすぎず、その分、無意識での禁忌も少なかったのである。コム・デ・ギャルソンやヨウジヤマモトはこの日本人の無意識によってヨーロッパ人の無意識を撃ったことになる。
では、本家の中国ではいまだに白が喪色かというと、近年は欧米化が進み、黒が標準になっている。ただし、女性なら白のヘア・バンドや白の造花をつけて喪を強調する必要がある。やはり、中国では白が喪色なのだ。だから、日本人がお祝いで紅白を用いたり、花嫁が白のウェディングドレスを着るのは異様に思えるらしい。中国では結婚式などの慶事の色は圧倒的に「赤」なのである。結婚式では招待状も赤ければ、祝儀袋も赤。花嫁衣装も赤だった。ところが最近では、中国ですら花嫁は純白のウェディングドレスになってきている。流行の力は民族よりも強しである。
流行といえば、意外だったのはサンタクロースの赤白の衣装。これはなんと一九三一年のコカ・コーラの広告に端を発したもので、以前にはサンタクロースは全身を毛皮で包んでいた。赤白はコカ・コーラのトレード・カラーが転用されたものなのだ。
また、皇帝が着用する高貴な色は何かというと、中国では陰陽五行説で黄色、ローマでは紫色と決まっていたが、近代ヨーロッパでは、ブルー・ブラッドという言葉の通り青となる。サラセン人に支配されたイベリア半島でレコンキスタ(国土回復運動)が起こったとき、白人貴族が、浅黒いイスラム教徒とは違って、青い血管が見える自分たちの白い肌を誇りにしたことから来ているという。
対するに、イスラム教圏では楽園のアドン(エデン)も、神の玉座も、天上界の最上層にあるとされるコーランも緑というところから、緑が聖なる色となる。カダフィ大佐率いるリビアの国旗が緑一色なのはそのためである。
このように、民族・国民の違いによる色彩の心理的イメージは、宗教や民族創世神話によるものも多いが、商業主義的な色彩グローバリズムから来ているものも少なくない。本書は、この両方をバランスよく拾っている。手元に一冊あると便利な本。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする