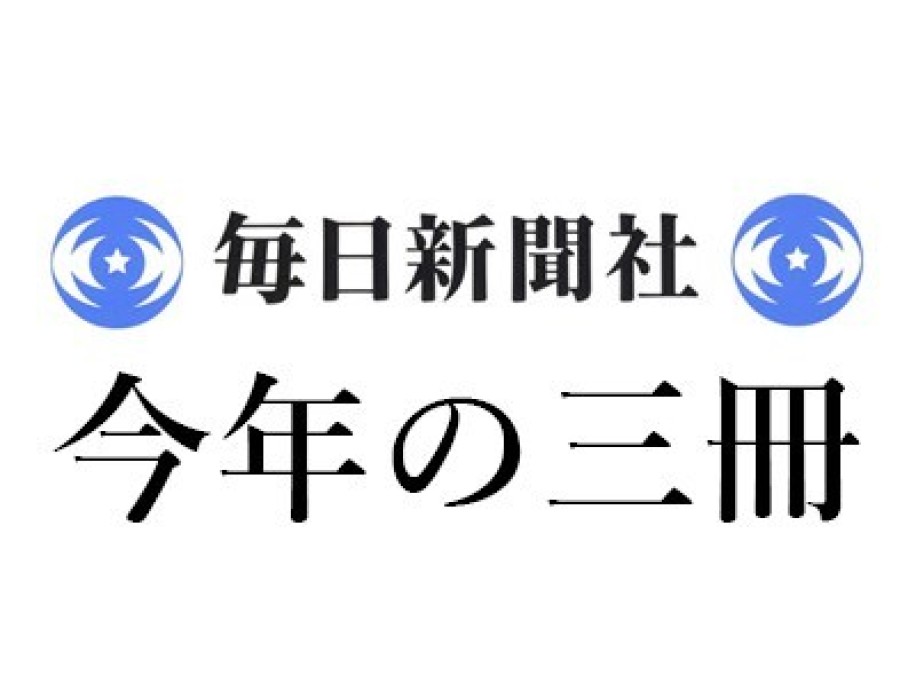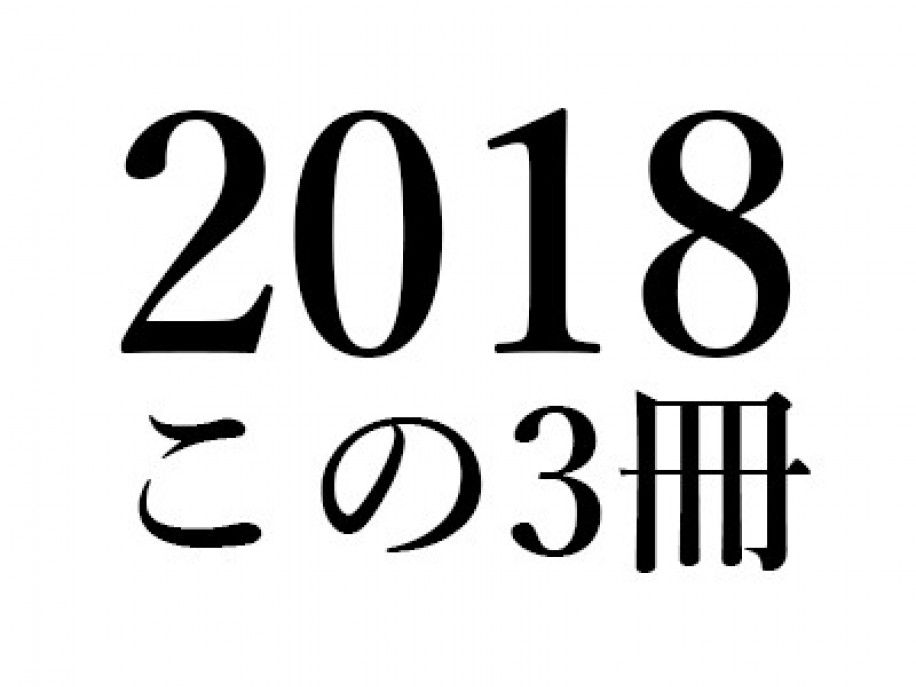書評
『エドゥアール・マネ 西洋絵画史の革命』(KADOKAWA)
複製技術がもたらす過激さ
マネとモネは混同しやすい。マネは音楽の教科書で「笛を吹く少年」が知られる画家で、モネは「睡蓮(すいれん)」で有名な印象派の始祖、と聞けばモネの方が現代的で時代もかけ離れていたように思いがちだが、そうではない。年齢差は8歳でマネはモネの兄貴分だった。改めてマネの「笛を吹く少年」を見てみよう。描写が平坦(へいたん)で影の付け方に矛盾があるなど、画題は古風でも、描き方は統一感を欠き、シュールな印象すらある。
近代絵画史がマネを起点に繙(ひもと)かれていく。画家たちを取り巻く環境が浮き彫りになり、実に新鮮。マネがいたからモネが生まれた。のみならずドガも、セザンヌも、ゴーガンも、ピカソも、ウォーホルすらもマネの画業なくして誕生しなかったのだ。
舞台はオスマンの大改造計画で変貌しつつある19世紀後半のパリだ。複製技術の発達により古典名画が、まずは版画で、のちに写真で複製されて手近に見ることが可能になった。なかでも重要なのは画集『全流派画人伝』(全14巻)の刊行である。これが出た意味はネットで即座に検索できる現代では想像がつかないほど大きい。それまでは大先輩の名画を簡単に目にできないどころか、どこにどんな作品があるかを調べるのも容易ではなかったのだ。
マネはこうしたメディア環境の変化に着目する。古典から構図、モデルのポーズ、筆触、色彩などの要素を抜きだし、時代の文脈に沿って再構成した。それは「起源を問わずあらゆるイメージを同一次元で操作し、絵画を作り上げる試み」であり、「暴力的とでも言うべき過激さ」があった。つまりマネは自分の生きる時代状況に敏感な、当代の「現代美術家」だったのである。
なにが彼をそのような方向に導いたのだろうか。複製芸術、とりわけ写真との出会いは小さくなかった。物事の表面だけをとらえる写真装置は世の物象をフラットに感じさせる。価値のヒエラルキーは崩れ、あらゆるものが等価になって彼の眼前に再登場したはずだ。これがイメージを同次元で扱うという視点につながった。
してみれば、写真が日常化した後世のアーティストが彼の影響から自由なはずがないではないか!
ALL REVIEWSをフォローする