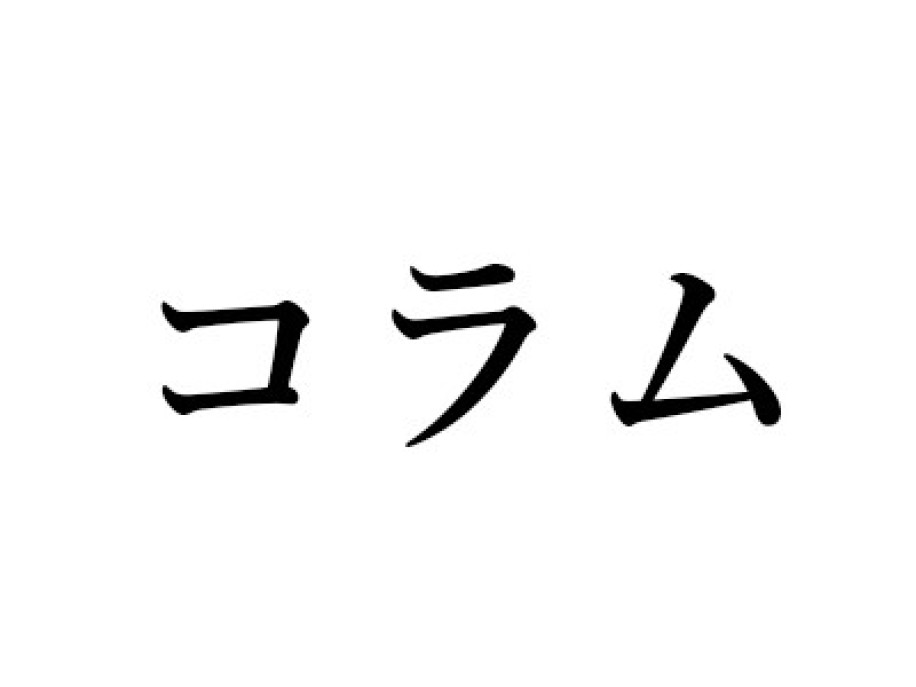書評
『血に飢えた悪鬼』(東京創元社)
ジョン・ディクスン・カーが好き
創元推理文庫で出たディクスン・カーの遺作『血に飢えた悪鬼』(一九七二)を読んだ。“不可能犯罪の巨匠”の最後の作品はいかなるものならん、と大いに期待したのだが、はっきりいって、出来ばえはよくない。一八六九年のロンドンを舞台にしたお得意の歴史伝奇ミステリで、『月長石』の作者ウィルキー・コリンズが探偵役。おそらく、この趣向のみをやりたかったのだろう。あとは、数人の男女がロンドン中を馬車で駆けずりまわって互いの愛情を確かめあう、というだけのお話で、ミステリとしては凡作。彼の作品中でも最もつまらぬ部類に属する。
しかし、そんなことをここで云々しようとは思わない。わたしがある種の感銘をおぼえたのは、作者カーが、この最後の作品に至ってもなお密室と取りくんでいる点である。さらには、“ユドルフォ荘”なるゴシック風の屋敷や蝋人形館まで登場させて、怪奇なムード作りにこだわっている点である。初志貫徹というか、雀百までというか、とにかく執念の人だったのだな、あの人は。
ジョン・ディクスン・カー
という名前は、本格ミステリのファンにとって、忘れがたい独特の響きをもっている。“カー・キチ”と呼ぼれる熱狂的なファンが存在するかと思うと、この名を耳にしただけで顔をしかめる人も多い。これほど、ファンの好悪の度合いが激しいミステリ作家も珍しいのではあるまいか。
カー嫌いの本格ファンが、彼の作品を非難する理由は、だいたい次の四つである。
①吸血鬼だ、黒ミサだ、降霊術だというあの怪奇趣味が大げさでアホらしい。
②「はっはっは、わしはそんなことわかっとったんじゃよ」などというセリフを連発するフェル博士やH・Mの名探偵キャラクターが、芝居がかっていていやだ。
③前記二人が演ずるドタバタが、どうにも耐えられない。あれでユーモアのつもりか。
④内容に関していえば、無理なトリックが多すぎる。なかにはトリックのためのトリックもあり、論理性や必然性を欠いている。
いちいちお説ごもっともであり、あまり反論の余地はない。
しかし、何がどうあれ――と居なおってしまうが、世のカー・キチ連中と同様、わたしはこの作家が大好きである。名前を見ただけで胸がわくわくしてしまうほど、偏愛している。
カーは、れっきとしたアメリカ人であるにもかかわらず、英国――とりわけ十九世紀の英国に憧れ、そこに住み、懸命に英国の作家になろうとした。しかし、本質的にはペンシルバニア生まれの陽性なヤンキー気質の人物であり、ハリウッド映画風の通俗大サービス精神、過剰なほどのショーマンシップの持ち主なのである。その作品の魅力も欠点も、すべてこの点に根ざしているのではないかと思う。
彼はどうしたら読者を一番満足させることができるか、を常に考えていた。謎解きミステリである以上は、最後にあっと言わせなければならない。そのために、意外性の極致ともいうべき趣向を考え出す。どう見てもできそうにないことをやってみせようという”不可能興味”である。観客の目の前で一本の細い綱を渡ろうというだけではなく、その上で、オリンピック体操選手も顔負けのウルトラ演技を演じようとするのだ。それがはかばかしく進行しない時には、チャンバラを入れたり、ローレル&バーディ風のスラップスティックを繰りひろげて見せてくれたりして、少しでも読者を楽しませようとするのである。
わたしなどは、こうしたカーの出血大サービスぶり、その一途なところに惚れこんでしまう。実際、彼のはなれわざが成功したときは、すばらしい。一度味わったら忘れられないほどの快感がある。
ディクスン・カーの代表作として何を選ぶべきかについては、江戸川乱歩を初めとするカー・キチ諸氏によって、以前からいろいろといわれ続けてきた。わたしは、常識的だが、やはり『火刑法廷』(一九三七)をあげる。これは、お得意のアクロバット演技があまりにすごかったために、それがアクロバットであるとすら感じられなくなってしまったという神がかり的な傑作で、カー以外の作家には絶対に書くことのできないミステリである。
二番目には、もう何を持ってきてもよろしい。『三つの棺』(一九三五)でもいいし、『修道院殺人事件』(一九三四)でも『ユダの窓』(一九三八)でもいい。『読者よ欺かるるなかれ』(一九三八)や『緑のカプセルの謎』(一九三九)も完成度が高くて落とせないし、歴史物から『火よ燃えろ!』(一九五七)か『ビロードの悪魔』(一九五一)のどちらかを持ってくる手もある。
それら著名な作品よりも、むしろ、わたしは、まるで話題にのぼらぬものの方に、奇妙な愛着を感じる場合がある。綱の上でアクロバットをやろうとしたはいいが、綱そのものの張り方が悪かったり、張るべき場所でないところに張ったためにものの見事に失敗した、というタイプの作品で、印象に残っているものでは、『五つの箱の死』(一九三八)と『魔女が笑う夜』(一九五〇)。
前者は、カー・ファンでない人が読んだら、なんだ、これは、と怒るだけだろう。しかし、ファンには作者の狙いがよくわかるはずだ。一言で書けるのだが、ネタをばらすことになるのでまあやめておこう。『死人を起す』(一九三八)風の意外性の極致を狙ったのだが、いくらなんでもこればかりは無理だった、という代物。
後者は、知る人ぞ知る怪作。ちょっと信じがたいほど珍妙なトリックが登場する。チェスタトン風の奇想天外とはちがう。珍無類なのである。よくも、これほどバカなことを思いついたものだ。涙ぐましい、という気分すら起こさせる労作。
こんな調子で書いていたら切りがないから、もうやめる。このコラムは、現代の本格物を扱うはずなのに、今回は、なぜかディクスン・カーというお化けみたいな作家の登場となってしまった。 (それもこれも、一九八〇年の今頃になって東京創元社がカーを新刊で出したりするから悪いのだ)
しかし、カーが、意外性の極限に常に挑み続けた稀有の作家であったことは否定しようもない事実だし、彼を失って、多くのミステリ・ファンが淋しい思いをしていることもまた事実である。考えてみれば、偉大な人でした。遅まきながら、御冥福をお祈り申し上げる。
〈付記〉
ディクスン・カーについては、このあとも書いているし、とくに付け加えるべきことはない。『血に飢えた悪鬼』のあとに訳されたカー作品は、『亡霊たちの真昼』(一九六九)一作きりである。やはり、あまりいい出来ではなかった。
文中、『五つの箱の死』について奥歯にもののはさまったような書き方をしており、さっぱり要領を得ないので、ここで書いておきたい。カーはこの作品で、〈登場人物外の犯人〉という趣向を試みようとしたのだ、といいたかったのである。が、さすがにこれは成功しなかった。ただの凡作になったのである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする