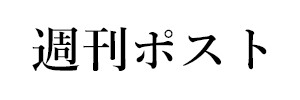書評
『メディア都市パリ』(藤原書店)
目から鱗が落ちるとはよく言うが、この言葉は、まさに本書にこそふさわしい。
ナポレオンがワーテルローの戦いに敗れて成立した王政復古の社会は、逆にナポレオン神話をとてつもなく増幅させ、多量の「成り上がり願望の青年」を生み出す結果になったが、剣がすでに力を持たなくなったこの時代に、こうした成り上がり願望の青年たちの心を最も引き付けたマーケットはといえば、それは最小の資本でもっとも手っ取り早く「名」を獲得することのできる分野、すなわち「文学」であった。著者によれば、十九世紀の代名詞とも言えるロマン主義は、天才や霊感によって彼方の栄光を目指した無償の芸術運動などでは決してなく、なによりもまず、「名」の征服という、いかがわしい欲望がプレテクストとして先行する、世俗的な現象であるという。すなわち、ユゴーもバルザックも、霊感によってペンを取ったのではなく、「ナポレオンのなしたことをペンによってなさん」という上昇願望につきうごかされて、紙を黒くしていったに過ぎないのである。ところが、結果的にこの成り上がり願望の青年たちが本当に天才だったため、それに続く青年たちのみならず、御本人までが、自分たちを「高貴な魂をもった詩人」と錯覚し、ここにいかがわしい成り上がり願望を心の純粋さと取り違える「ロマン的魂」が成立することとなる。
だが、この「ロマン的魂」も、その錯覚を物理的に支えてくれる「言説の市場」、つまりジャーナリズムが成り立っていなければ、はじめから存在し得ない。なぜなら、王侯貴族というパトロンのいなくなった十九世紀においては、自らの文の価値を金に換えてくれるマーケットがなければ、「名声」を「富」に代えることはできなかったからである。ところでモダンのみならずポスト・モダンまでをも支配することになるこのジャーナリズムも、実はロマン主義と同じく成り上がり願望に燃えたエミール・ド・ジラルダンというスキャンダラスな私生児によって、伝達すべき内容をもった言説(思想)から、言うべきことを持たぬ言説(商品)へと、一挙に資本主義の枠内に編入された制度であった。すなわち「一見逆のみぶりによって離反しあうかに見えるこの二つの言説はその実深いところで《いかがわしさ》を共有し合っている。それは《成り上がり》ということにつきる」。
このように、著者の意図は「市場の中の芸術家」が自らの「文の興行師」となってジャーナリズムという「市場の要請」に従い、文学と呼ばれる「インダストリー」を成立させていった過程を「成り上がり」というグリッドによって分析することにあるが、実はなによりも楽しいのは、こうした《いかがわしさ》を著者が限りなく愛しているらしいことである。この意味で本のタイトルには、ジラルダン夫人の流行通信にウエートを置いた現行の題よりも、いっそ三章の副題、『「ロマン的魂」虎の巻』を使ったほうがよかったのではないか。内容を一言にして要約しているこんなスキャンダラスで素晴らしい惹句(じゃっく)はそうはないのだから。
【この書評が収録されている書籍】
ナポレオンがワーテルローの戦いに敗れて成立した王政復古の社会は、逆にナポレオン神話をとてつもなく増幅させ、多量の「成り上がり願望の青年」を生み出す結果になったが、剣がすでに力を持たなくなったこの時代に、こうした成り上がり願望の青年たちの心を最も引き付けたマーケットはといえば、それは最小の資本でもっとも手っ取り早く「名」を獲得することのできる分野、すなわち「文学」であった。著者によれば、十九世紀の代名詞とも言えるロマン主義は、天才や霊感によって彼方の栄光を目指した無償の芸術運動などでは決してなく、なによりもまず、「名」の征服という、いかがわしい欲望がプレテクストとして先行する、世俗的な現象であるという。すなわち、ユゴーもバルザックも、霊感によってペンを取ったのではなく、「ナポレオンのなしたことをペンによってなさん」という上昇願望につきうごかされて、紙を黒くしていったに過ぎないのである。ところが、結果的にこの成り上がり願望の青年たちが本当に天才だったため、それに続く青年たちのみならず、御本人までが、自分たちを「高貴な魂をもった詩人」と錯覚し、ここにいかがわしい成り上がり願望を心の純粋さと取り違える「ロマン的魂」が成立することとなる。
だが、この「ロマン的魂」も、その錯覚を物理的に支えてくれる「言説の市場」、つまりジャーナリズムが成り立っていなければ、はじめから存在し得ない。なぜなら、王侯貴族というパトロンのいなくなった十九世紀においては、自らの文の価値を金に換えてくれるマーケットがなければ、「名声」を「富」に代えることはできなかったからである。ところでモダンのみならずポスト・モダンまでをも支配することになるこのジャーナリズムも、実はロマン主義と同じく成り上がり願望に燃えたエミール・ド・ジラルダンというスキャンダラスな私生児によって、伝達すべき内容をもった言説(思想)から、言うべきことを持たぬ言説(商品)へと、一挙に資本主義の枠内に編入された制度であった。すなわち「一見逆のみぶりによって離反しあうかに見えるこの二つの言説はその実深いところで《いかがわしさ》を共有し合っている。それは《成り上がり》ということにつきる」。
このように、著者の意図は「市場の中の芸術家」が自らの「文の興行師」となってジャーナリズムという「市場の要請」に従い、文学と呼ばれる「インダストリー」を成立させていった過程を「成り上がり」というグリッドによって分析することにあるが、実はなによりも楽しいのは、こうした《いかがわしさ》を著者が限りなく愛しているらしいことである。この意味で本のタイトルには、ジラルダン夫人の流行通信にウエートを置いた現行の題よりも、いっそ三章の副題、『「ロマン的魂」虎の巻』を使ったほうがよかったのではないか。内容を一言にして要約しているこんなスキャンダラスで素晴らしい惹句(じゃっく)はそうはないのだから。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする