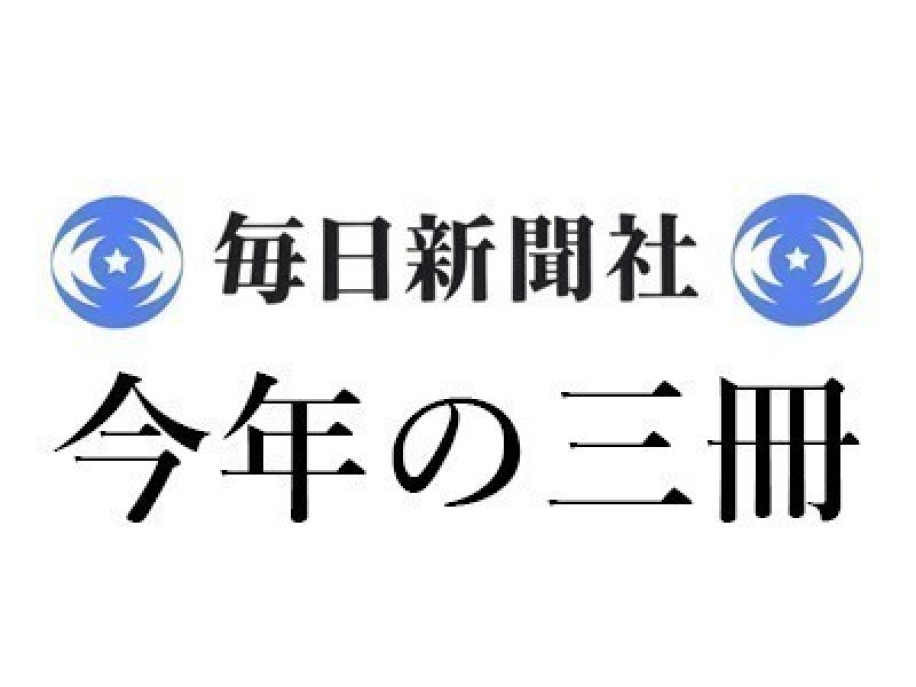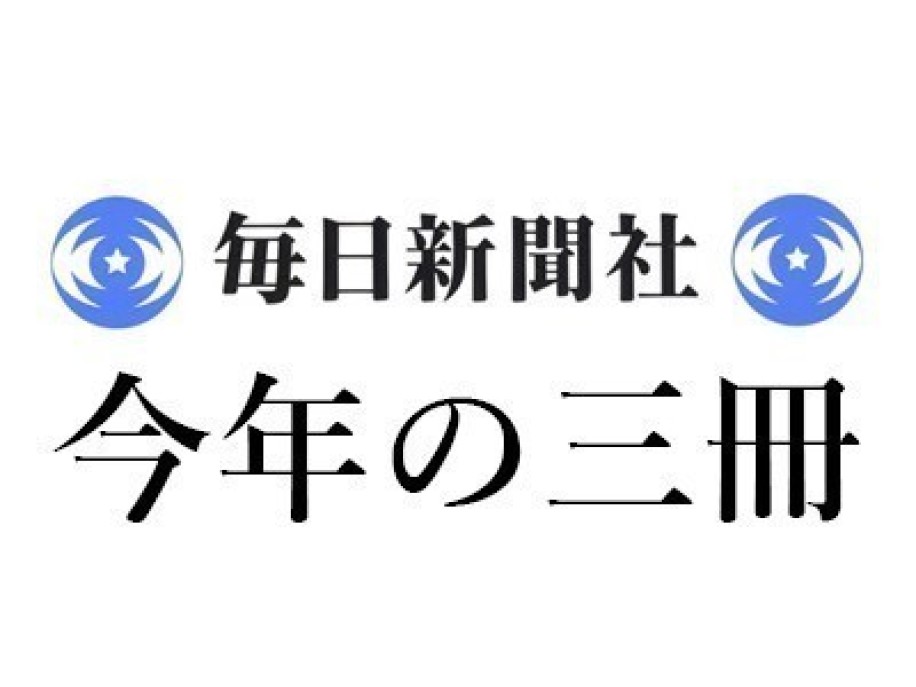書評
『村からのホンネ―きょうからあしたの農を考える』(ダイヤモンド社)
ミカン山の葬式
山下惣一は自分のことを佐賀唐津の〈一介のさえない百姓〉だという。しかし高村光太郎ではないが、内にコスモスを持つ人の言は一地方的存在を越えたものがある。『村からのホンネ――きょうからあしたの農を考える』(ダイヤモンド社)を、農業に素人の私が作者の意図どおり、「寝っころがって」読ませてもらった。そんな読みやすい本なのに、あちこちで教えられ、最後にずしりときた。村には村の不文律がある。「株取り養子」であった父は、異常なほどに「家を潰す」ことをおそれた。だから「総領に分限を超えた教育を受けさせるとつぶれる」と高校進学を許さなかった。人の不幸によって維持される家とは何なのか、と山下惣一は若いころ自問した。それでも農より家、家より人間、より小さなものが大切だと思ってきた。しかしようやく親子、親戚、先祖、田畑山林――一族の拠点である「家」を確固たるものにしたいという父の思いが、父の植えた山を見てようやくわかりかけてくる。
かつて、むらの若者は小遣いかせぎに「どっこいしょ」をやった。コメを一俵、親の目を盗んで売るのだ。「連帯感というのは共犯意識の共有のことだから、どっこいしょ仲間はいくつになっても仲が良い」。そうにちがいない。が、いまコメの値段は鴻毛のごとく軽く、若者はだれも「どっこいしょ」などしなくなった。
九州で佐賀県だけがヤマイモに関心が低いのはナゼか。それは旧鍋島藩に百姓がきびしく搾取され、遊び心も育たなかったからではないか、という。なぜならば田んぼのレンゲの花を眺めて「ああ、きれいだ」ではなく、「こりゃおおごと、はよう鋤(す)かにゃトラクターに巻きつく」とあわてる。そんなではヤマイモを掘りにいく心の余裕がない、というのだ。
どの話もおもしろい。くらしの歴史が土地の人気(じんき)をつくることが納得される。私は「ふーん」「ふーん」と鼻を鳴らして読みつづけた。
後半は、農作物の自由化、異常な商品化、減反政策への怒りがつよい。つよいを通りこして剣呑(けんのん)ですらある。「冷房がんがんきかして地球環境を語る都会人」などと痛罵(つうば)されるとドキンとしながら、「惣一つぁん、どこに住もうとベストをつくすしかないんじゃない? 」と語りかけたくもなる。が、悟って鎮まりきらないのが彼の身上だろう。
まさか、と思っていた山下家でも、国のミカン園廃転換事業で「ミカン山の葬式」を出さざるを得なかった。妻と二人、木を焼きに通う。三十年前から植え、手塩にかけたミカンである。
「今年からは夏の盛りに草刈り機背負うて草刈りこんでもよかたい。お前もラクになる」「ほんなこて、苦労したね」「ああ」……夫婦は山に深々と頭を下げた。
米の輸入に絶対反対の著者は、「なぜだ? 」と問われて、まず「イヤだから」と答える。政府や大企業の論理にこの暮らしの論理、いってみれば生活様式・生活文化を対置する点で、白保の海を守る人びとも、地上げ屋にたった一人抗する人も、逗子の女たちもつながりあえるのだ。物わかりよくなる必要はないではないか。まぎれもなく山下惣一は佐賀の農民であり、大所高所から見ず、あくまで小所低所にこだわるところにリアリティがある。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする