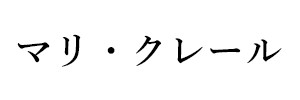書評
『アメリカン・マインドの終焉――文化と教育の危機 【新装版】』(みすず書房)
この本をいったいなんと呼んだらいいか、日本の分類でいえば教育関係論とか教育思想の本ということになるとおもう。旧い正統的な教養をもち、またそんな教養主義の良さと伝統を確信し、保守的な思想と考え方をもっているアメリカの大学教授が、現代のアメリカ学生気質と若者の生活や行動や文化の受けいれ方の現状をつぶさに観察し、学生と身近に接し、感じたことを、その根底までふくめたうえで、思うざまぶちまけて批判している。そしてわたしたちの言葉でいえば〈この世もすえだ、末法だ〉というのが表題の「アメリカン・マインドの終焉」の意味になっている。もちろん、「アメリカン・マインド」の拡散といっても、展開といっても、もっと調子よく発展といっても、いいはずだとおもう。
古典的な教養人というにふさわしく、この文体と批判の密度、調子、魂の大きさと粗っぽさの度合は、プラトンの対話篇にいちばんよく似ていて、影響をうけているとおもう。じじつプラトンが『国家』篇のなかで理想とする共同体の構想から、文芸と音楽を敬遠したのとおなじように、この本でもことに言葉はげしく学生、若者文化の主流であるロック・ミュージックにたいして、否定論議をやっていて、この本のなかでも圧巻だといえる。根拠はやはりプラトンの『国家』篇の第三巻十~十二とおなじだ。リズムと音階とメロディは、どんなものよりも魂の内奥にふかく入って、ひとの魂を力づよくつかむものだから、気品のある優美さをもつ音楽ならば、気品ある人間をつくり、その逆なら逆の人間ができあがるということだ。
いまアメリカのロック・ミュージックのように十歳から二十歳にかけて、大多数の「生きがい」になっている音楽の時代は、一世紀まえのドイツのワーグナー音楽の与えた陶酔と熱狂に匹敵すると、この本の著者は書いている。家にはステレオや、音楽ヴィデオがあり、放送はひっきりなしに音楽番組を流し、おまけにウォークマンが登場した。アメリカの若者たちの心のなかでクラシック音楽は死に、そのかわりに趣味などというものではなく、魂のなかに喰い入るようにロック・ミュージックは氾濫した。この本の著者のいうとおりにいえば、以前の学生はクラシック音楽について著者よりも豊富な知識をもっていた。そのかわりに音楽はあくまでも趣味の域をでなかった。いまではクラシックなどなんの知識ももっていないけど、音楽そのものは人生に重大な意味をもっていることを知っているようになった。そしてその音楽というのは、学生や若者たちが自分の手で、まるで空気のように必要なものとして探しだしたロック・ミュージックなのだ。著者はこのことにとまどい、ほんとうは学生や若者がじぶんで探しあてたという意味で評価しながら、またそれがロックであったことに露骨に不満と否定をもらしている。
ところでこの本の著者によればロック・ミュージックは、性欲に訴えかけるひとつの野蛮な手段で、愛でもなければ〈エロス〉でもなく、未熟な性欲相手のしろもので、娯楽産業にけしかけられて性交愛のビートを売っているだけなのだ。十三歳の少年がウォークマンを耳にあててロックを聴きながら数学の宿題をやっているとすれば、この少年の感情はオナニズムの快感や親殺しの歌詞に象徴される。この少年の野心は演奏しているホモのミュージシャンのまねをして、名声と財産を手にいれようと当てこんでいるだけだ、としかいえない。
この本の著者はさらに悪態をつく。ロック・ミュージックが盛んになるのを野放しにしてきたのは、アメリカの家族の精神の空隙で、親たちは子供にロックを聴くのを禁じると、子供たちから背かれてしまうとおもって、禁止を言いわたすのをためらっている。だが親はロックなど拒絶する力を発揮すべきなのだ。
また著者によれば、左翼は、末期資本主義に容赦ない批判をあびせるのに、ロック・ミュージックにたいしては、民衆芸術だということで肯定的だが、ほんとうはロックの繁栄をもたらしているのは音楽産業の利益とこみになっているからだ。そう書いている。そしてこのあとでちょっとした否定そのもののミック・ジャガー論がロック悪の象徴の王としてつけ加えてある。著者はひどい判らず屋だが、その源泉はヨーロッパの正統な教養主義からする端正な知識と教養についてのイメージから流れくだっている。
アメリカ、アメリカのこころとはいったいなんなのか。この本の著者からすれば、アメリカのこころには魂の「地下室」がない。すべては「表層」の問題だけで形がつく。深さがない。現実とすぐに折り合いがつけられる。これが歯がゆいばかり薄っぺらなアメリカのこころなのだ。ちょうど日本の古典的な知識人が、日本にあるのは猿のような目まぐるしい模倣だけで、皮を一枚一枚むいていくとらっきょうみたいに何も固有性などのこらないと、よく苛立っていうのとおなじことになる。じぶんの文化現象にたいするじぶんの苛立ちはさまざまな憎悪にみちた否定を増殖させる。著者にかかると現代のアメリカの社会の集合意識と文化はすべて駄目なのだ。
(1)ラジオ、つぎにテレビは、アメリカのこころが育まれる家庭のプライバシーにおそいかかってこれを破壊してしまった。テレビは家庭の居間に侵入し、老若男女それぞれの趣向に滲みこみ、画一化して親たちから家庭の雰囲気をとりしきる意欲と能力をうばってしまった。
(2)アメリカ人には明日からでもなれるが、たとえばフランス人には少くともその時期には永久になれないと思わせる根底がある。それは伝統、正統性の深さに自信があるからだ。
ではアメリカの特徴はどこにあるのかと著者に質問したとすれば、著者は近代的な民主主義を実現し、年寄と大多数の福祉ということを政治体制の眼目として実現したことだと答えることになる。
アメリカでもブルジョワジイといっていい階級はいる。だがそれの対立語である王家、貴族、聖職層などはじめからない。また現在では、労働者階級(プロレタリアート)すらない。すべてが「中産階級」になっているし、アメリカ人は自分でそういうことを好んでいる。
アメリカ人は著者の言葉をつかえばロック主義者であり、ビジネスとしての仕事を必要とし、福祉としての互助を好み、自分の権利を主張するかわり他者の権利も認め、バランスよく破滅の思想ももたないかわりに、神や英雄になることも望んでいない。もちろん著者がこういうとき、嫌味、欠陥、否定の記号として語られている。ほんとうはドゴールやソルジェニーツィンみたいに「合衆国はたんなる個々人の集まり、他所から運んだ廃物のごみ捨て場であって、消費に没頭している国だ」と言いたいにちがいない。だがそう言いたい衝動をこの著者が抑えているのは、その古典主義的な素養によるだろう。わたしがこの本を読んで感じるのは、著者がアメリカ知識人のなかの西欧派ともいうべき存在で、欧州大陸の伝統的な知の系譜と流れのなかにアメリカの文化を位置づけたいと願望しているということだ。どうして六〇年代以後のアメリカの文化のアパシイ化、カルチャーの崩壊と拡散化、クラシックの衰退と非理性的な騒音や雑音の登場をくさすために、ホッブスやジョン・ロックやルソーが引きあいに出されなくてはならないのか。とても大げさで奇異に感じられる。アメリカ文化の特徴を論ずるのに、アメリカ文化だけで充分だし、たぶんアメリカという原理は、西欧という原理とまるで違っている。アメリカはジーンズが世界あまねく普遍化したのとおなじような意味で、六〇年代以後に世界史を造成してきた。それはたぶん西欧という原理とまったく異質な原理、著者のいう平等主義と民主主義の露骨な先導によってなのだ。悪平等、大多数主義、がさつと素直、単純さと行動主義、ヴェールをかぶった教養主義のかわりに直接むきだしのリビドーのリズム、こういったものが現在のアメリカの果してきた特色だというほかに、何もいうべきことはない。だが著者によれば、このアメリカの現在の特色はすべて否定の表象で、アメリカのこころが終焉にむかう徴候なのだ。そしてこの徴候はこの本の著者がわざわざ一項目をもうけて説いているように、六〇年代からはじまった。
(1)六〇年代は大学にとって災厄で、その時代に生れたもので肯定できるものは何もない。
その六〇年代に、黒人を、女性を、南ヴェトナムを解放したというのはまったく嘘だ。六〇年代は、教条主義とどうでもいいパンフレットの時代で、ただ一冊も長期にわたり重要だとみなされる本など生れなかった。
(2)六〇年代にジェーン・フォンダが本物の自堕落な女として登場し、ローリング・ストーンズが活動したということには何の重要性もない。
(3)行動科学は事実と価値を区別し、事実の研究に専念して、ウェーバー的な価値の科学をバカにする社会科学だ。
(4)アメリカの大学の倉庫には、アメリカとは何か、善とは何で悪とは何かを教える真剣な思想と信念が蔵されていたのに、学生たちは大学を破産させただけで、アメリカの学問がもつ偉大な自由主義的伝統を放棄した。
まだたくさん著者の六〇年代評とそれ以後にたいする否定的な批判と繰り言はいっぱいある。たとえば数学のルネ・トムや行動主義のベイトソンみたいな、アメリカならではの偉大な思想と実績が、著者のおおざっぱな批判と否定のかげで流されてしまうような不愉快な感じもあるし、フロイト主義やマルクス主義や構造主義や脱構築主義などを、「作家を近代の学者が造園した庭に植えられた植物にしてしまった」というような愉快な批判も含まれている。
また、いたるところばらまかれている卓見もある。たとえば「カリスマ」「ライフスタイル」「コミットメント」「アイデンティティ」といった、アメリカの俗語になって、チューインガムのように街頭にとびかっている言葉は、もとをたどればニーチェとフロイトとウェーバーの価値と価値転換にむすびついた語彙だったという指摘などは、西欧派的な古典主義者であるこの本の著者でなければ、なかなか見つけだせなかったとおもえる。ニーチェやフロイトやウェーバーの社会哲学的な用語が、アメリカという実利主義的で、世界の最強で最大の国で日常用語に変ってしまった。その奇跡のような世界(史)の変貌を、二〇年代の誰もが思いつくことさえできなかったと、著者は言っている。この変貌はニーチェやフロイトやウェーバーの価値概念がアメリカ的な価値の大衆化と拡散と解体にさらされたことを意味していると、この本は大なたをふりあげて主張し、それをわたしたちに向ってふりおろしている。わたしは、ほんのすこしなら、この大なたを防げるような気がしながら読みおえた。
【この書評が収録されている書籍】
古典的な教養人というにふさわしく、この文体と批判の密度、調子、魂の大きさと粗っぽさの度合は、プラトンの対話篇にいちばんよく似ていて、影響をうけているとおもう。じじつプラトンが『国家』篇のなかで理想とする共同体の構想から、文芸と音楽を敬遠したのとおなじように、この本でもことに言葉はげしく学生、若者文化の主流であるロック・ミュージックにたいして、否定論議をやっていて、この本のなかでも圧巻だといえる。根拠はやはりプラトンの『国家』篇の第三巻十~十二とおなじだ。リズムと音階とメロディは、どんなものよりも魂の内奥にふかく入って、ひとの魂を力づよくつかむものだから、気品のある優美さをもつ音楽ならば、気品ある人間をつくり、その逆なら逆の人間ができあがるということだ。
いまアメリカのロック・ミュージックのように十歳から二十歳にかけて、大多数の「生きがい」になっている音楽の時代は、一世紀まえのドイツのワーグナー音楽の与えた陶酔と熱狂に匹敵すると、この本の著者は書いている。家にはステレオや、音楽ヴィデオがあり、放送はひっきりなしに音楽番組を流し、おまけにウォークマンが登場した。アメリカの若者たちの心のなかでクラシック音楽は死に、そのかわりに趣味などというものではなく、魂のなかに喰い入るようにロック・ミュージックは氾濫した。この本の著者のいうとおりにいえば、以前の学生はクラシック音楽について著者よりも豊富な知識をもっていた。そのかわりに音楽はあくまでも趣味の域をでなかった。いまではクラシックなどなんの知識ももっていないけど、音楽そのものは人生に重大な意味をもっていることを知っているようになった。そしてその音楽というのは、学生や若者たちが自分の手で、まるで空気のように必要なものとして探しだしたロック・ミュージックなのだ。著者はこのことにとまどい、ほんとうは学生や若者がじぶんで探しあてたという意味で評価しながら、またそれがロックであったことに露骨に不満と否定をもらしている。
ところでこの本の著者によればロック・ミュージックは、性欲に訴えかけるひとつの野蛮な手段で、愛でもなければ〈エロス〉でもなく、未熟な性欲相手のしろもので、娯楽産業にけしかけられて性交愛のビートを売っているだけなのだ。十三歳の少年がウォークマンを耳にあててロックを聴きながら数学の宿題をやっているとすれば、この少年の感情はオナニズムの快感や親殺しの歌詞に象徴される。この少年の野心は演奏しているホモのミュージシャンのまねをして、名声と財産を手にいれようと当てこんでいるだけだ、としかいえない。
この本の著者はさらに悪態をつく。ロック・ミュージックが盛んになるのを野放しにしてきたのは、アメリカの家族の精神の空隙で、親たちは子供にロックを聴くのを禁じると、子供たちから背かれてしまうとおもって、禁止を言いわたすのをためらっている。だが親はロックなど拒絶する力を発揮すべきなのだ。
また著者によれば、左翼は、末期資本主義に容赦ない批判をあびせるのに、ロック・ミュージックにたいしては、民衆芸術だということで肯定的だが、ほんとうはロックの繁栄をもたらしているのは音楽産業の利益とこみになっているからだ。そう書いている。そしてこのあとでちょっとした否定そのもののミック・ジャガー論がロック悪の象徴の王としてつけ加えてある。著者はひどい判らず屋だが、その源泉はヨーロッパの正統な教養主義からする端正な知識と教養についてのイメージから流れくだっている。
アメリカ、アメリカのこころとはいったいなんなのか。この本の著者からすれば、アメリカのこころには魂の「地下室」がない。すべては「表層」の問題だけで形がつく。深さがない。現実とすぐに折り合いがつけられる。これが歯がゆいばかり薄っぺらなアメリカのこころなのだ。ちょうど日本の古典的な知識人が、日本にあるのは猿のような目まぐるしい模倣だけで、皮を一枚一枚むいていくとらっきょうみたいに何も固有性などのこらないと、よく苛立っていうのとおなじことになる。じぶんの文化現象にたいするじぶんの苛立ちはさまざまな憎悪にみちた否定を増殖させる。著者にかかると現代のアメリカの社会の集合意識と文化はすべて駄目なのだ。
(1)ラジオ、つぎにテレビは、アメリカのこころが育まれる家庭のプライバシーにおそいかかってこれを破壊してしまった。テレビは家庭の居間に侵入し、老若男女それぞれの趣向に滲みこみ、画一化して親たちから家庭の雰囲気をとりしきる意欲と能力をうばってしまった。
(2)アメリカ人には明日からでもなれるが、たとえばフランス人には少くともその時期には永久になれないと思わせる根底がある。それは伝統、正統性の深さに自信があるからだ。
ではアメリカの特徴はどこにあるのかと著者に質問したとすれば、著者は近代的な民主主義を実現し、年寄と大多数の福祉ということを政治体制の眼目として実現したことだと答えることになる。
アメリカでもブルジョワジイといっていい階級はいる。だがそれの対立語である王家、貴族、聖職層などはじめからない。また現在では、労働者階級(プロレタリアート)すらない。すべてが「中産階級」になっているし、アメリカ人は自分でそういうことを好んでいる。
アメリカ人は著者の言葉をつかえばロック主義者であり、ビジネスとしての仕事を必要とし、福祉としての互助を好み、自分の権利を主張するかわり他者の権利も認め、バランスよく破滅の思想ももたないかわりに、神や英雄になることも望んでいない。もちろん著者がこういうとき、嫌味、欠陥、否定の記号として語られている。ほんとうはドゴールやソルジェニーツィンみたいに「合衆国はたんなる個々人の集まり、他所から運んだ廃物のごみ捨て場であって、消費に没頭している国だ」と言いたいにちがいない。だがそう言いたい衝動をこの著者が抑えているのは、その古典主義的な素養によるだろう。わたしがこの本を読んで感じるのは、著者がアメリカ知識人のなかの西欧派ともいうべき存在で、欧州大陸の伝統的な知の系譜と流れのなかにアメリカの文化を位置づけたいと願望しているということだ。どうして六〇年代以後のアメリカの文化のアパシイ化、カルチャーの崩壊と拡散化、クラシックの衰退と非理性的な騒音や雑音の登場をくさすために、ホッブスやジョン・ロックやルソーが引きあいに出されなくてはならないのか。とても大げさで奇異に感じられる。アメリカ文化の特徴を論ずるのに、アメリカ文化だけで充分だし、たぶんアメリカという原理は、西欧という原理とまるで違っている。アメリカはジーンズが世界あまねく普遍化したのとおなじような意味で、六〇年代以後に世界史を造成してきた。それはたぶん西欧という原理とまったく異質な原理、著者のいう平等主義と民主主義の露骨な先導によってなのだ。悪平等、大多数主義、がさつと素直、単純さと行動主義、ヴェールをかぶった教養主義のかわりに直接むきだしのリビドーのリズム、こういったものが現在のアメリカの果してきた特色だというほかに、何もいうべきことはない。だが著者によれば、このアメリカの現在の特色はすべて否定の表象で、アメリカのこころが終焉にむかう徴候なのだ。そしてこの徴候はこの本の著者がわざわざ一項目をもうけて説いているように、六〇年代からはじまった。
(1)六〇年代は大学にとって災厄で、その時代に生れたもので肯定できるものは何もない。
その六〇年代に、黒人を、女性を、南ヴェトナムを解放したというのはまったく嘘だ。六〇年代は、教条主義とどうでもいいパンフレットの時代で、ただ一冊も長期にわたり重要だとみなされる本など生れなかった。
(2)六〇年代にジェーン・フォンダが本物の自堕落な女として登場し、ローリング・ストーンズが活動したということには何の重要性もない。
(3)行動科学は事実と価値を区別し、事実の研究に専念して、ウェーバー的な価値の科学をバカにする社会科学だ。
(4)アメリカの大学の倉庫には、アメリカとは何か、善とは何で悪とは何かを教える真剣な思想と信念が蔵されていたのに、学生たちは大学を破産させただけで、アメリカの学問がもつ偉大な自由主義的伝統を放棄した。
まだたくさん著者の六〇年代評とそれ以後にたいする否定的な批判と繰り言はいっぱいある。たとえば数学のルネ・トムや行動主義のベイトソンみたいな、アメリカならではの偉大な思想と実績が、著者のおおざっぱな批判と否定のかげで流されてしまうような不愉快な感じもあるし、フロイト主義やマルクス主義や構造主義や脱構築主義などを、「作家を近代の学者が造園した庭に植えられた植物にしてしまった」というような愉快な批判も含まれている。
また、いたるところばらまかれている卓見もある。たとえば「カリスマ」「ライフスタイル」「コミットメント」「アイデンティティ」といった、アメリカの俗語になって、チューインガムのように街頭にとびかっている言葉は、もとをたどればニーチェとフロイトとウェーバーの価値と価値転換にむすびついた語彙だったという指摘などは、西欧派的な古典主義者であるこの本の著者でなければ、なかなか見つけだせなかったとおもえる。ニーチェやフロイトやウェーバーの社会哲学的な用語が、アメリカという実利主義的で、世界の最強で最大の国で日常用語に変ってしまった。その奇跡のような世界(史)の変貌を、二〇年代の誰もが思いつくことさえできなかったと、著者は言っている。この変貌はニーチェやフロイトやウェーバーの価値概念がアメリカ的な価値の大衆化と拡散と解体にさらされたことを意味していると、この本は大なたをふりあげて主張し、それをわたしたちに向ってふりおろしている。わたしは、ほんのすこしなら、この大なたを防げるような気がしながら読みおえた。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする