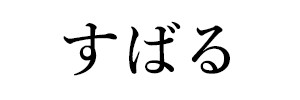書評
『ビル・エヴァンス―ジャズ・ピアニストの肖像』(水声社)
規律あるロマンティシズム
一九八〇年秋のある週末、中途半端な時間帯にスイッチを入れたFMチューナーから、スタン・ゲッツとビル・エヴァンスのデュオで「グランド・ファーザーズ・ワルツ」が流れてきた。愛らしいこの小品が終わると、今度はビル・エヴァンス・トリオで「グロリアズ・ステップ」「サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム」がつづいていく。おかしいな、ビル・エヴァンスの特集なんて番組表には記されていなかったはずだ。嫌な予感がして、同日の夜、あるヴァイオリニストの海外演奏会を録音するつもりで用意してあったソニーのDUADという高価なカセットテープをまわしはじめたとたん曲がフェードアウトし、声に聞き覚えのあるジャズ評論家が番組をしめくくった。本日は予定を変更し、五十一歳で急逝したビル・エヴァンスの追悼特集をお送りしました……。ほぼ編年体で丁寧にたどられたピーター・ペッティンガーのエヴァンス伝を繙(ひもと)いているうち、私はその晩のことを思い出した。本来録音されるべき演奏ではなく、ひとりの稀有なピアニストの死の報を記録しただけで何年も放置されることになったカセットは、数年後、友人に借りたリヒテルのライブ放送で埋められてしまったのだが、エヴァンスが母親を通じてロシア人の血を引いていること、さらにオリジナル曲のいくつかにスクリャービンの前奏曲の影響があることなどをこの本で教えられ、ラフマニノフとスクリャービンをかぶせたのならエヴァンスに対しても失礼ではなかったのだと胸を撫で下ろした。
しかしそんなことはどうでもいい。マイルス・デイビスの『ジャズ・トラック』に名を連ねている無名のピアニストの「時を超越した完成度」と「一音一音に秘められた、もう少しで聴く側にも手が届きそうな感じがする、音楽家の静かな情熱や音に対する熱望」をわずか十三歳で感受して以来、ペッティンガーはエヴァンスのすべてを追い、節度ある愛をもって端正な評伝を書きあげたのだ。過度な思い入れや破調は見られず、対象への敬意はあっても妙な神格化はない。自身も音楽家なだけに奏法や楽曲構成の分析は的確で、かつ素人にも理解しやすい言葉が選ばれ、エヴァンスが理想とする「規律に基づいたロマンティシズム」を控え目に伝えて過不足がない。
著者略歴によれば、氏は本書の刊行年に没しているから、いわばどうしても書き残しておきたかった白鳥の歌でもあったのだろう。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする