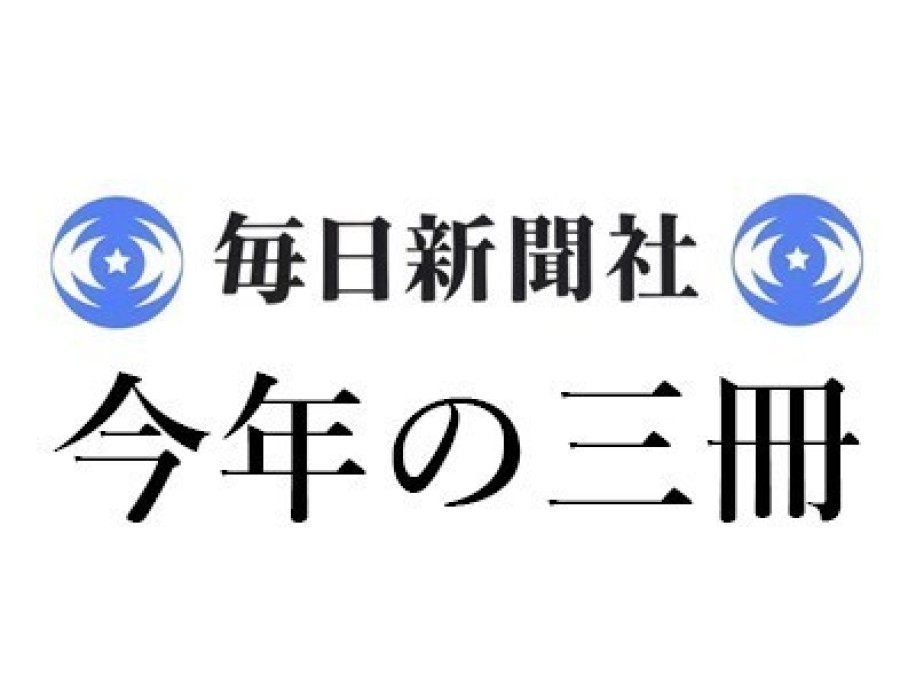書評
『重税都市―もうひとつの郊外住宅史』(住まいの図書館出版局)
都市を動かしてきた力は税金だろうか
書名を見てギョッとさせられた。花見の最中に冷たい水を首筋から流し込まれたような気分になった。ここ数年、東京論ブームというのがあって、風俗、社会、建築、文学といったさまざまな分野から東京ひいては日本の都市を取り上げて論じてきた(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1991年)。
日本の都市は一見混乱しているが実は見えざる秩序を持っているとか、転変定めなき都会が生んだ文学的感性とか、高度消費社会を世界で最初に到達したシブヤの面白さとか、街にころがる奇妙な物件を発見する楽しさとか、いずれも現代の日本の都市を肯定的に明るくとらえる点に特徴があった。
マア言ってみれば、明治このかたの暗い日本の都市論を脱して近代史上初めてお花見気分に酔っているところに、
“ジュウゼイ都市”
である。
重税と都市の二語をつなげたセンスだけでも見事なもので、今後、日本の都市を考えるうえで欠かせないキーワードが顔を出したと言えよう。
それにしても顔を出すのはもうすこし酔いが回ってからにしてほしかった。重税都市の四文字を目にしただけで、この本の言わんとするところはある程度予想がつく。腰巻に「見えざる負の力」とあるが、「負の力」という言い方もこの本の姿勢をうまくとらえたコピーにちがいない。
明治以後今日まで日本の都市を作り動かしてきた力は何であったのかと、この本はわれわれに問いかける。政治の力か市民の夢かはたまた生産力か、いやそれらはすべて表向きの話であって、ホントは税金だったんじゃないか、とこの若い著者は言うのである。
それではミもフタもないではないか、と反発しながらも反論できないのがツライ。
実に、わが日本の都市は税によって動かされてきた。都市の物理的基盤となるのは土地だが、その土地の動きを身近なところで振り返ったらいい。昔風の家や商店が壊され、細長いビルになったり、小分けされてミニ開発されたりするのはたいてい相続の時の税の力にほかならない。税という見えざる負の力によって一つのまとまった土地は三代で解体し、再編され、こうした部分の変化の総和として日本の都市は変わってきたのではないか、と著者は言い、その証拠として郊外住宅地を取り上げる。
「明治末から大正期にかけて東京、大阪、京都の三大都市を中心に実施された『家屋税』をめぐる狂想曲。そこでは税と負担の格差が人々をして新たな行動に駆り立てた。都市は人々を引きつけると同時に郊外に追い出したのだ」
郊外住宅地といえばこれはもう明治末年以後、“田園生活”“健康”“家族”“赤いフランス瓦の屋根と青い芝生”といったキャッチフレーズによって、サラリーマン階層を引きつけてきた夢の地にほかならないが、この本を読むと、どうもそんな単純な話ではなかったことがよく分かる。
この本は、花見客への冷水ともいえるし、中学生がおしゃべりに興じている時、急に宿題の話を出すヤな奴、ともいえるのだが、しかし、日本の都市が土地問題という大きな宿題をやり残したままになっており、そのポイントが土地税制にあることを考えると、避けて通れない一冊であることはまちがいない。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする