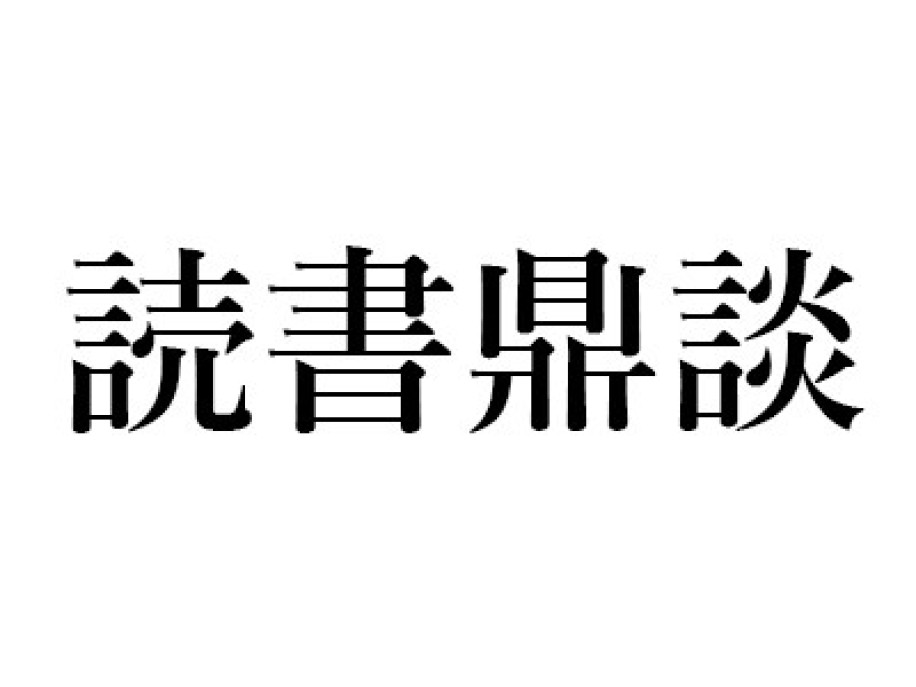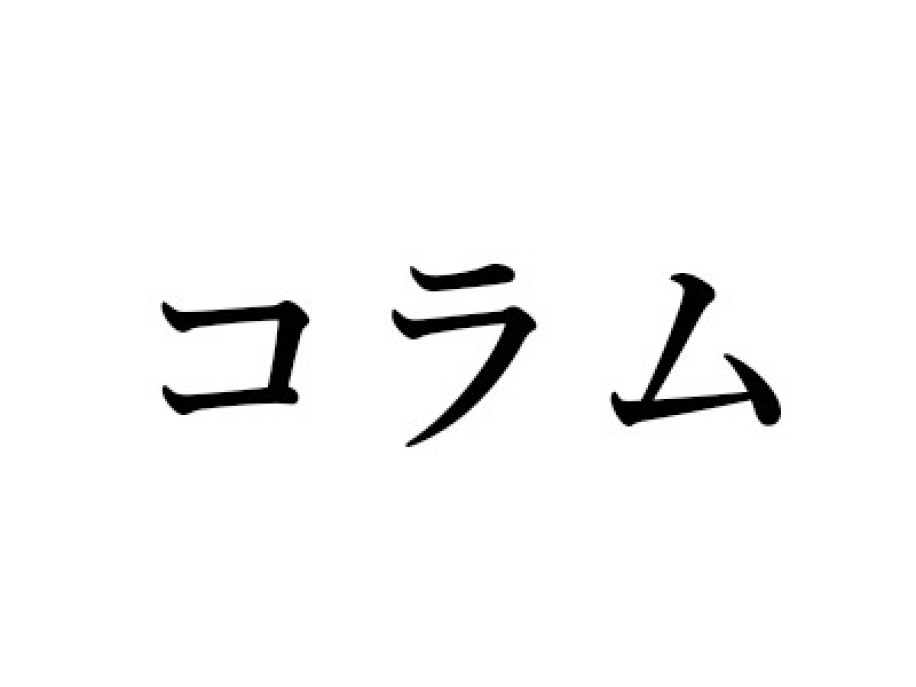書評
『同潤会アパート原景―日本建築史における役割』(住まいの図書館出版局)
外国人が研究した日本初の近代的集合住宅
やっと、そしてついに、かの同潤会アパートについてのまとまった本が刊行された(住まいの図書館出版局)。それも、日本の都市学者や建築史家じゃなくて、フランスの国立・現代日本研究センターの若い研究者の手によって。僕としてはちょっぴりくやしい。
考えてもいただきたい、同潤会アパートが日本の近代都市の歩みの上に放つ栄光と実績を。アパートといっても、木造二階建ての例の立体長屋のことではなくて、同潤会のは日本最初の近代的な集合住宅であった。外国人用をのぞいて、人が集まって住むといえば木造の長屋ばかりだった東京と横浜に、震災復興計画の中で、今日でいうならマンションに相当する鉄筋コンクリートの同潤会アパートが次々に出現し、高密度に集まって住むことが大きな利便と健康をもたらしうることをはじめて教えてくれた。以後、集合住宅の形式は日本に定着し、また同潤会も、住宅営団、住宅公団と続き、今日の住宅・都市整備公団(その後、都市公団)にいたる。
同潤会アパートこそ、現在の日本の都市住宅の基本といっていいのだが、どうしたことかこれまでまとまった研究が世に出されなかった。日本の研究者で手を着けていた人は何人かいるが、一部分の深い追求に日を過ごし、全体の流れと意味を大きく把まえてまとめることをおこたっている間にフランスから青い目の若い学者がやってきて、
一九八四年の早春のある午後、表参道の大通りをぶらぶらと散歩していたとき、私はふとある空間に引き込まれた。ここには建物のスケール、光、色が溶け合って調和した集合住宅が連なっていた……実際、一目惚れ以外の何ものでもなかった
という具合で、以後、惚れた勢いで資料の山とまだいくつも残る現場に突進し、八年かかってこの一冊がまとまった次第。
基本的なことはしっかり書かれている。時の内務省地方局が中下層の住宅改良のために外郭団体として同潤会を創設したこと。不燃と耐震と高密度化のために鉄筋コンクリート造りとし、加えて集会所や娯楽室や児童遊園を付加して、コミュニティー活動の充実を図ったこと、などなど。こうした大筋の話のほか、細部も捨てがたい。たとえば、床の仕上げをどうしたか。土足で上がることはないにしても、畳かジュータンかそれとも別の何かか。
鉄筋コンクリートの建物の内部に、木造建築と密接に結び付いている伝統的空間を持ちこむことができるかと彼ら(同潤会)は不安を抱いていた。東京や横浜のような夏は蒸し暑いところでは、衛生上、保存上の理由から、コンクリート構造の床面の上に直接畳を敷くことはできない。そこで、まず最初に畳の代わりに茣蓙(ゴザ)をかぶせた二層のコルクを敷くことが考案された
日本人がはじめて体験したアパートは、コルクの上にゴザを敷いたものだったのである。
大きな本ではないが、貴重な写真と図面もたくさんおさめられており、全体としてこれを越えるものはもう出ないであろう。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする