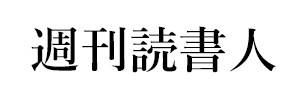書評
『十八世紀パリ生活誌―タブロー・ド・パリ〈上〉』(岩波書店)
待望久しい、古典的名著の翻訳である。アナール派史学の登場以来、ルイ=セバスチャン・メルシエのこの著作は、フランス革命と近代社会史研究の必読文献として、しばしば引用されてきたが、部分訳であるとはいえ今回こうして日本語で全貌(ぜんぼう)に近い姿に接してみると、あらためてその重要さを実感せざるをえない。社会学的統計をいくら列挙されてもアンシャン・レジーム末期の危機的状況を想像裏に描くことのできない歴史音痴でも、富の極端な偏りを葡萄酒(ぶどうしゅ)価格や家賃の中に見抜くメルシエの卓抜な描写を読めば、一七八九年のバスチーユ襲撃は歴史的必然であったのかという思いにかられるはずである。結局のところ、十八・十九世紀の社会史研究は、すべてこの『タブロー・ド・パリ』の要約だと言ってもさほど言い過ぎではあるまい。
ところで今日の我々からすると、メルシエが取り上げている当時のパリのタブローはいかにも異様な突出した現象ばかりを記録したもののように思えるかもしれないが、メルシエが描き出す驚くべき現実は、どれも同時代の人間にとってはごく当たり前のことと映っていた事象にすぎない。メルシエの偉大な点は、同時代の感受性が当然のことと受け取っていた社会の歪(ひず)みを、自己のボン・サンスのみに依拠して、「これは当然なことではない」と看破した点にある。ひとことで言えば、メルシエはジャーナリストという言葉が生まれる以前に最も良質なジャーナリストとしての仕事を残したわけであるが、フランス革命から二百年たった今日、はたして我々はメルシエに匹敵するようなジャーナリストをひとりでも持っているだろうか。
なお訳文はメルシエのたたみかけるような小気味よい文体をよく生かしきった明快なものだが、書評子はそれ以上には膨大な原著から過不足なく目配りのきいた抜粋をおこなった訳者の労を多しとしたい。この作業は、しんどい割りに評価されることのまことに少ないものだから。
【この書評が収録されている書籍】
ところで今日の我々からすると、メルシエが取り上げている当時のパリのタブローはいかにも異様な突出した現象ばかりを記録したもののように思えるかもしれないが、メルシエが描き出す驚くべき現実は、どれも同時代の人間にとってはごく当たり前のことと映っていた事象にすぎない。メルシエの偉大な点は、同時代の感受性が当然のことと受け取っていた社会の歪(ひず)みを、自己のボン・サンスのみに依拠して、「これは当然なことではない」と看破した点にある。ひとことで言えば、メルシエはジャーナリストという言葉が生まれる以前に最も良質なジャーナリストとしての仕事を残したわけであるが、フランス革命から二百年たった今日、はたして我々はメルシエに匹敵するようなジャーナリストをひとりでも持っているだろうか。
なお訳文はメルシエのたたみかけるような小気味よい文体をよく生かしきった明快なものだが、書評子はそれ以上には膨大な原著から過不足なく目配りのきいた抜粋をおこなった訳者の労を多しとしたい。この作業は、しんどい割りに評価されることのまことに少ないものだから。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする