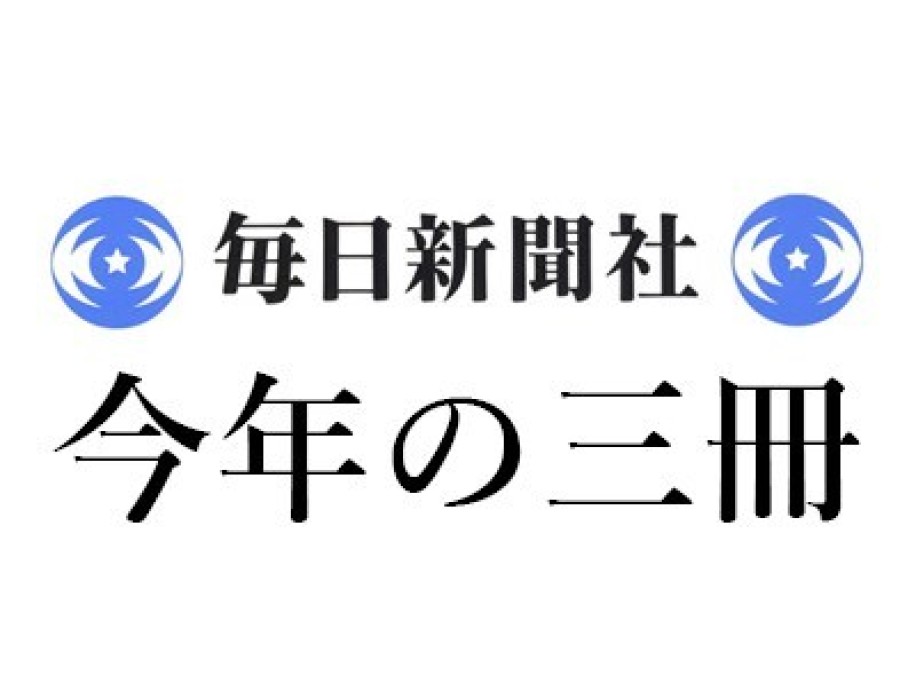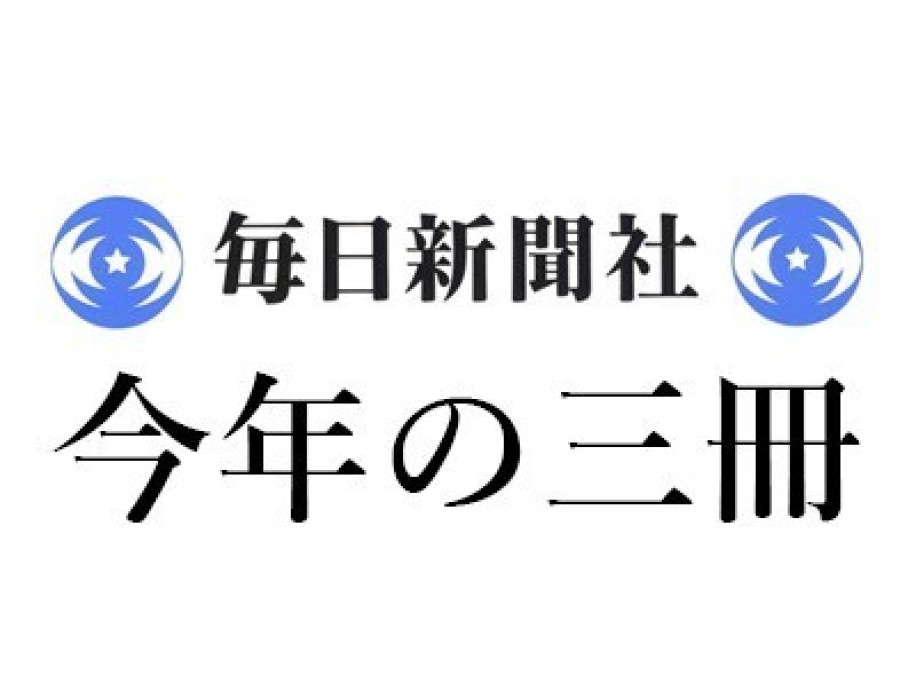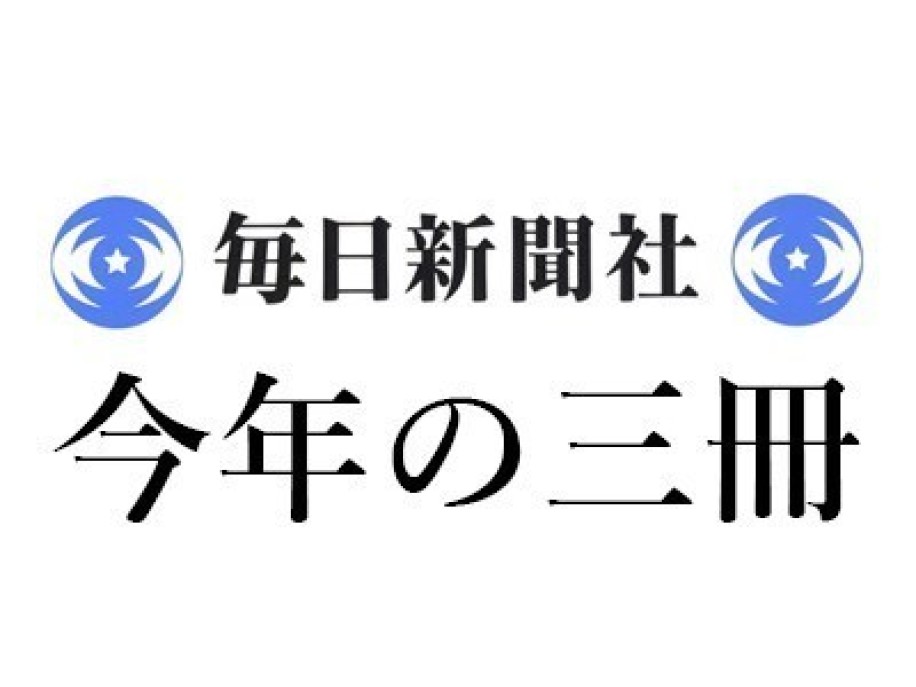書評
『超孤独死社会 特殊清掃の現場をたどる』(毎日新聞出版)
孤独をなくすだけでなく孤独を受け入れる社会を
「緩やかな自殺」とまで言われる孤独死は年間3万人。1000万人もの人々が孤立状態で暮らしている日本だが、週刊誌を開けば、軒並み「死に方」が議論されている。穏やかに死ぬ、というより、どうすれば迷惑をかけずに死ねるかが優先される。あまりに残酷な孤独死の現場の後始末を行う「特殊清掃業者」を追うと、無慈悲な社会が浮き上がってくる。「特殊清掃業者にとって、孤独死の最も多く発生する夏場はかき入れ時だ」という一文が多くを物語る。密室で命を落とした誰かの存在が、おびただしい数の蠅や蛆、時には玄関の入り口付近に放射線状に広がるゼリー状のドロドロした液体によって知らされる。ただ命をつなぐために飲み、食べる。排泄(はいせつ)やゴミまでケアする余裕など残されていなかったのだ。
本書で多くの事例を知るにつれ、だからこそ家族の助けが必要だとか、施設や病院に入ってもらわなきゃといった、正しいとされる道筋を確保するだけではいけないと教え込まれる。孤独死した老人の実子が遺骨の引き取りを拒否する事例も多い。孤独死と一言で片付けられがちだが、実像が無数にあるのだ。
「必ず俺が臭い消したる」、体液が壁や柱などの建材にまで染み込んだ臭いを何とかして除去しようとする特殊清掃業者は、死んでいった人々の尊厳を少しでも取り戻そうとする行為だ。
AIやITを使い、変化の兆しを感知する仕組みが増え始めている。家族間の意思疎通や地域のつながりについて、うん、それって大事だよね、とは思う。でも、それだけではなく、どうしたって増えていく孤独をいかに受け止めるべきか、社会に招き入れるか、その理解が急がれている。逆説的かもしれないが、一人で死ぬことを受け止めようとする本とも思えた。
ALL REVIEWSをフォローする