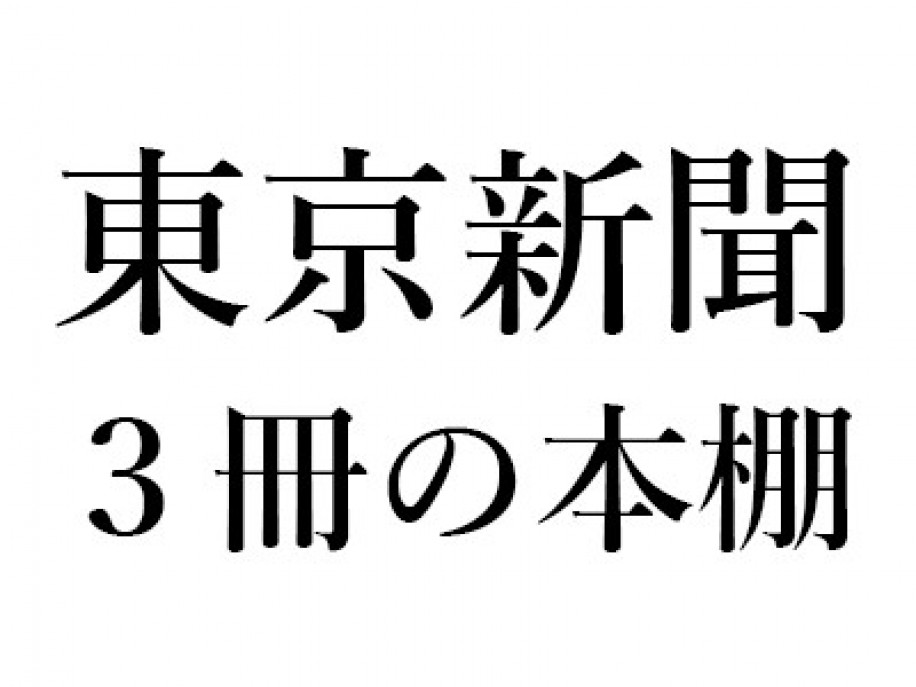書評
『真剣師小池重明』(幻冬舎)
江戸と敗北
読売巨人軍はどんどん負け続けて、テレビ画面から見える長嶋監督の表情からはすっかり笑みが失せ、ヴェルディ川崎の加藤監督は辞任を匂わせる。ついこの間このコラムでとり上げたばかりの羽生名人も谷川竜王に負けて「名人」位を奪われ「これも実力ですから」と震える声でいわねばならない(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1997年)。人間は人間に負けてもイヤになっちゃうが、IBMのスーパーコンピューターに負けたカスパロフさんだって試合終了後はガックリしてチェス盤に突っ伏してしまった。だから、負けることはまったくよろしくないのである。
――というようなことを、旅行中、考えていた。今回、トランクの中に入れていったのは『真剣師小池重明』(団鬼六著、幻冬舎アウトロー文庫)と『「敗者」の精神史』(山口昌男著、岩波書店)。なんだかこういう組み合わせになっちゃったのである。『真剣師』の方は単行本が出た時に買ったまま読まずに終わり、『敗者』の方は拾い読みしかしなかったので、今度はちゃんと全部読もうと思ったのだった。『真剣師』の主人公小池重明は「新宿の殺し屋」と呼ばれた伝説の将棋ギャンブラーである。名古屋出身で高校中退、各地を転々としながら賭け将棋で腕を磨いてアマチュア日本一にもなり、プロの高段者にも勝って「プロ殺し」の異名をとったが、ギャンブルや酒や女に溺れ(人妻との駆け落ち三回)寸借詐欺同然の借金を重ねて将棋界から追放、最後は過度の飲酒から肝不全で四十四歳で死亡――というから筋金入りの破滅型ギャンブラーだ。
小池重明は棋士である。棋士である以上勝たねばならない。負けちゃなんにもならない。だから、小池重明は勝つ。勝ち続ける。この伝記の圧巻は棋士小池の勝ちっぷりである。もちろん、ぼくは将棋がわからない。だが、著者の丁寧な説明で、小池の不思議な勝ちっぷりが伝わってくる。一言でいうと、小池の戦法は異様で感覚的でかつ「古い」。序盤はもたもたして、とても勝てそうにないと思わせ、後半ものすごい勢いで追い込んでくる。
小池の序盤のまずさは技術開発がなされていなかった江戸期の将棋感覚だが、彼の終盤における的確さも江戸期の将棋の特徴に似ている、というのである。
将棋で連戦連勝だった小池重明も、他の分野では負けっぱなしだった。酒に負け、競馬に負け、女に負ける。欲望を制御できないのである。徹夜で酒を飲んで試合場に現れる。で、将棋に勝つ。プロのチャンピオン、大山名人との試合の前夜、泥酔して喧嘩し留置場へぶち込まれ、釈放されたその足で将棋会館に駆けつけ、名人に圧勝する。
将棋に勝つだけ、他で負ける。いや、なにもかも負けてしまう分を補うように将棋で勝ち続ける。小池が破滅していったのは、プロ入りを拒否されたからだと著者は示唆している。プロ将棋は幼い頃から奨励会という養成所で学びそこから選抜されてきた特殊なエリートたちで成立している社会であり、アウトローの小池には入る余地がなかった。だが、特例で入ったとして「江戸将棋」の小池が「近代将棋」のエリートたちに勝てただろうか。
ところで、『「敗者」の精神史』は日本近代を流れる「知的」敗者の精神を源流にまで遡ろうとした労作である。山口昌男は、明治維新で新政府に敗れた「江戸」にその淵源を求めた。そして、敗者の徹底した「脱世間」の精神の中に二十一世紀への希望を見つけようとするのだが、この二冊を同時に読んでいたぼくには『真剣師』がまるで山口昌男の本の一章のような気がしたのだった。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする