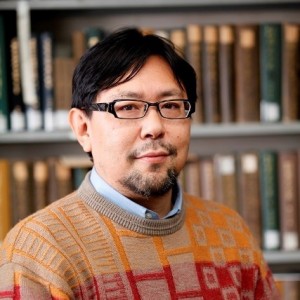書評
『粋を食す 江戸の蕎麦文化』(天夢人)
江戸っ子は蕎麦を粋な食べ物に育て上げた
新年早々、妙なニュースにモヤモヤした。一代で財を成した。敬服のほかない。美女のハートを射止めた。女性が才能と財力に惚(ほ)れるのは道理だ。けれど、大金をお年玉代わりにばらまくというのは……。間違っちゃいない。人助けにもなるのだが……何か違う。こういう時、何といえばいいのか。……粋じゃあねえ。そうか、粋かヤボかだ。私たち日本人は善悪とも利害とも異なる尺度、粋というやせがまんを大事にしてきたじゃあないか。室町時代後期、貴族趣味はすたれ、生活に根ざした文化が生まれた。江戸時代、武士に代わって庶民が文化の担い手になり、粋の概念が生まれた。粋な食べ物といえば、鮨(すし)・天麩羅(てんぷら)・鰻(うなぎ)。今や日本料理の代表となったこれらに先がけたのが、蕎麦(そば)であった。米が取れぬ荒廃した土地でやむなく生産される蕎麦。貧相な作物を江戸っ子は粋な食べ物に育て上げた。
蕎麦っ食いの美学に一番大切なのは「形」。味は二の次。本書はそう喝破する。よく、ツユはちょっと付けるだけで口の中で噛(か)んじゃあいけない、のみ込んでつるつるっとのどごしを味わう、三口か四口で手早く食べ終わらなきゃあ旨(うま)くない、という。あれは要するに作法であり、江戸っ子のこだわりなのである。うまいかどうかじゃない。うまそうに食べるところがポイントであって、蕎麦をたぐるというのはグルメなんぞというヤボじゃあねえんだ、べらぼうめ。
徳川四天王の豪勇、本多平八郎は「わが本多家のサムライは形から入る。あるべき形を 徹底的にまねていけば、サムライの魂も精神もあとから自然についてくる」と説いた。こうしてみると、蕎麦を食うのは武士道にも通じるのか。ああ、小腹がすいた、蕎麦が食べたい。思わずそう呟(つぶや)かせる痛快な一書。
ALL REVIEWSをフォローする