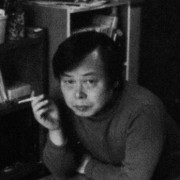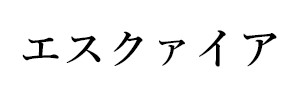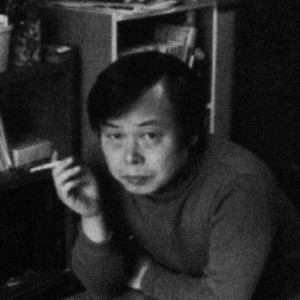書評
『ファシストを演じた人びと』(青土社)
1936年のベルリン・オリンピック大会。イタリア選手団は黒シャツに白ズボン、トルコ帽風の帽子に肩からななめにかけたたすき。ナチス・ドイツは白の上着にネクタイ、カスケットのような帽子。一方、日本代表団は戦闘帽に濃い色の上着、やや薄めの同色のズボン。日独伊枢軸といっても、これだけコスチューム・プレイヤーのセンスに差があった。わが国が段ちがいにダサイ。
戦中からの固定観念で、私たちはともすれば、ファシズム・イタリアもカーキ色の戦闘帽の同類と考えがちである。しかし実情はそうではなかった。'30年代イタリアはファシズム体制にもかかわらず、というよりファシズム体制下なればこそ、芸術的アヴァンギャルドの最前線にあった。ヒトラーとはちがい、ムッソリーニはアヴァンギャルド・ファンだったのだ。もしかするとムッソリーニこそは当時最前衛のアヴァンギャルディストだったかもしれない。
あるときは農民、あるときは労働者、ときには中産階級、またあるときは飛行士、兵士。雪之丞や多羅尾伴内もかくやとばかりに七色十色に変した。不動のカリスマとして君臨するよりも、「ポリフォルムの指導者として国民を操作し」、「国民は自分の鏡像をムッソリーニの上に見た」一筋縄ではいかない芸人だったのである。動きのないクローチェ美学に依存していた左翼文化人は、その芸にだしぬかれて手も足も出なかった。
ムッソリーニがアヴァンギャルド美学に密着して政治操作をしたのにひきかえ、ファシズム体制下の芸術家たちは政治に密着しながらアヴァンギャルド芸術を持続させ、それを戦後にまで持ち込んだ。食うか食われるかの現場の駆け引きである。文学者の戦争責任とか、体制芸術のコンフォルミズムとかいう、喧嘩すぎての棒ちぎれめいた話ではない。イデオロギーには金城鉄壁の境界がある。それでも境界であることに変わりはない。いつかは文化がそれを越える。これはその、政治が文化を越境し、文化が政治を越境する、抜きつ抜かれつの大接戦の実況報告である。
戦中からの固定観念で、私たちはともすれば、ファシズム・イタリアもカーキ色の戦闘帽の同類と考えがちである。しかし実情はそうではなかった。'30年代イタリアはファシズム体制にもかかわらず、というよりファシズム体制下なればこそ、芸術的アヴァンギャルドの最前線にあった。ヒトラーとはちがい、ムッソリーニはアヴァンギャルド・ファンだったのだ。もしかするとムッソリーニこそは当時最前衛のアヴァンギャルディストだったかもしれない。
ヒトラーが単一の、固定したイメージを与えているのに対して、ドゥーチェ(総帥ムッソリーニ)は、変幻自在に、多様な人物を演じている。彼は大衆の中にある類型をできるかぎり多く写しとろうとした。(略)階級の境を自由に越えてみせた。その衣裳に対する考慮が尋常ではなかったことは多くの写真からすぐに推測できる。
あるときは農民、あるときは労働者、ときには中産階級、またあるときは飛行士、兵士。雪之丞や多羅尾伴内もかくやとばかりに七色十色に変した。不動のカリスマとして君臨するよりも、「ポリフォルムの指導者として国民を操作し」、「国民は自分の鏡像をムッソリーニの上に見た」一筋縄ではいかない芸人だったのである。動きのないクローチェ美学に依存していた左翼文化人は、その芸にだしぬかれて手も足も出なかった。
ムッソリーニがアヴァンギャルド美学に密着して政治操作をしたのにひきかえ、ファシズム体制下の芸術家たちは政治に密着しながらアヴァンギャルド芸術を持続させ、それを戦後にまで持ち込んだ。食うか食われるかの現場の駆け引きである。文学者の戦争責任とか、体制芸術のコンフォルミズムとかいう、喧嘩すぎての棒ちぎれめいた話ではない。イデオロギーには金城鉄壁の境界がある。それでも境界であることに変わりはない。いつかは文化がそれを越える。これはその、政治が文化を越境し、文化が政治を越境する、抜きつ抜かれつの大接戦の実況報告である。
ALL REVIEWSをフォローする