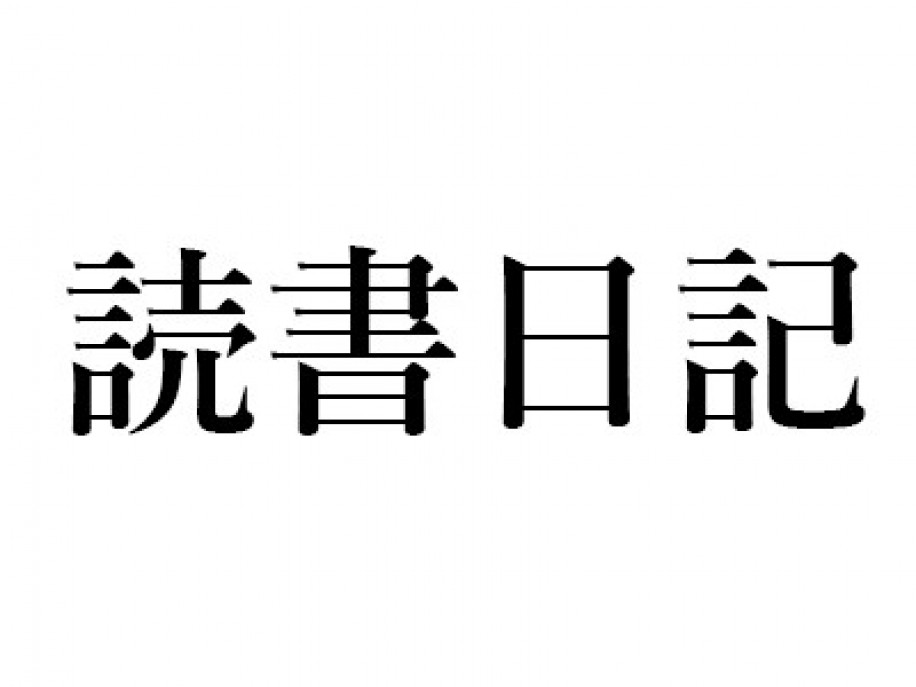書評
『警視庁草紙〈上〉―山田風太郎明治小説全集〈1〉』(筑摩書房)
山田風太郎と「明治小説」の楽しみ
楽しみにしていた山田風太郎の「明治小説全集」(筑摩書房)の刊行がはじまった。全集のスタートは『警視庁草紙』。時は明治六年から十年にかけて、征韓論にやぶれた西郷隆盛が東京を出立するところから物語ははじまる。ご一新によって出来上がった新政府と新都東京を舞台に、警視庁の面々とかつての警視庁、江戸南町奉行所の元奉行、元同心、元岡っ引きたちが対決する事件の数々は滔々たる流れとなり、遠ざかってゆく江戸への挽歌となるのだが、この作品のいちばんの楽しみは細部にあるようだ。
格子の向うで、蒼白い顔にかすかにあばたのあとのある子供は、利口そうな眼にいっぱいに恐怖のひかりをたたえていった。
『鬼ごっこみたいにめかくしされたひとが……雨のなかを。そのまえに、ボロボロのこじきが、たくさんあるいていったよ。……』
そうであったか、盲人の大名小路はここであったか、と千羽兵四郎は茫然として、銀灰色の蒸気の中にけむるがらんどうの遊女町を見わたした。
『こら、女の子、ここはどこだか知ってるか』
『おうもん』
『なんだい、それ……おまえなにしにここへきたんだ』
『おいやん』
『おまえ、おいらんになりにきたのか。ばか、なんて名だい』
『あたい、ひぐち、なちゅ』(「幻談大名小路」)
このあどけない会話を続けているのは数え年八歳の夏目漱石と同じく三歳の樋口一葉である。そして、「春愁 雁のゆくえ」のこんな一節。
――萩から密使の秘命をおびて上京して来た玉木真人は、わざと訪問しなかったが、陸軍省に伝令使として勤務する二十八歳の乃木希典は、彼の兄であった。真人は、よそに養子にいったので姓がちがったのである。……。
(乃木の乗った)馬車にはもう一人、少年が乗っていた。陸軍省のある書類を折返し至急届けてもらいたいと西周がいい、ちょうどその日、西家を訪れていた――以前西家に書生をしていたこともあるという――その少年が受取りの用を命じられて、同乗させてもらっていたのだ。
『僕は、あの巡査を知っています』
と、その少年――森林太郎がいい出した。
幼い漱石と一葉が会話し、明治天皇に殉死し、漱石の『こころ』の背景にもなった若き日の乃木将軍の馬車にまだ学生の鷗外が偶然乗っている。いや、その他にも、歴史上の有名人物から架空の人物まで、さまざまなキャラクターが自在に闊歩する。明治という時代は他のどの時代より、そういう自由な想像を作者に許してくれるような気がするのである。その理由はたぶん、
① 明治という時代はすでに十分遠くなり、実在の人物もまたひとりの魅力的な虚構の存在のように感じられるから、であり、
② 明治人たちの個性が現代人より遥かに明確でかつ強烈だから、であり、
③ にもかかわらず明治には現代と同じ問題がすべて出そろっていたから、
だろうか。
実をいうとぼくもまた、現代人の誰より、実在・架空を問わず明治の人物たちと小説の上で会話を交わすことの方が楽しいのである。いやはや。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする