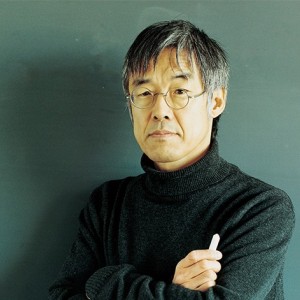書評
『ほんとうの私』(集英社)
ミラン・クンデラと恋愛小説の「中身」
ミラン・クンデラの最新作『ほんとうの私』(西永良成訳、集英社)の帯には大きく「熱く切なく燃える熟年の危うい愛」と書かれているので、そういう小説だなとわかる。そして、実際読んでみると、確かにそうなのである、お終い――これでは僅か三行ですんでしまうので、もう少し書いてみよう。『ほんとうの私』は恋愛小説である。ここまでクンデラの小説はたいてい恋愛小説であったともいえる。いや、そもそもほとんどすべての小説はなんらかの形で恋愛に関わっている。
ここで質問。恋愛小説というものには何が書かれているでしょう。
馬鹿なことをいうなとおっしゃるであろうか。恋愛小説なんだから、恋愛についてに決まってるじゃんか。
じゃあ、もう少し具体的にいうと?
恋愛というものへの仄かな憧れ。
あるよなあ、それ。
最初の、不意打ちのような出会い。ときめき。恋愛に陥る瞬間。
あるある。
燃え上がる恋、激しい欲望、目眩(めくるめ)く日々、喧嘩、三角関係、結婚、倦怠、不倫、禁じられた愛、倒錯した愛、老いらくの恋に若すぎる恋。どれもある。きっとある。たぶんある。
それでは再度質問。ここに挙げたテーマが一つもなくて恋愛小説が書けるでしょうか。つまり、憧れも欲望も倦怠も、その他、いわゆる「恋愛」を成り立たせているパーツが何にもなくて小説になるのかってことですが。
クンデラの答えはもちろん「書ける」。それが『ほんとうの私』なのである。
もちろん、厳密にいうならこの作品にも、恋愛小説のさまざまなパーツは存在している。同棲する中年カップルの不思議な心理の綾は、恋愛小説の中でしか読むことのできない性質のものだ。だが、どうもこの作品の中心はそこにはないようなのである。
このカップルは恋愛の全過程をすでに通り過ぎている。ふつうの「恋愛小説」なら、この後には倦怠と別れしか残らない。しかし、クンデラはその先に興味がある。恋愛の全過程が終わった後でも、なおかつ別れないでいるとしたら。それもただ別れないでいる(夫婦というものはそのようなあり方で存在している)のではなく、恋愛時のような緊張を維持しつつなお共にいるとしたら、どうすればいいのか。
その答えは「会話をする」である。
――ぼくがきみを知ったときに、すべてが変わったんだ。つまらない仕事が面白くなったからじゃない。そうではなく、まわりで起こっていることをすべて、ぼくらの会話の材料に変えるからなんだ。
――別のことだって話せるでしょうに!
――世の中から孤立し、ふたりだけで愛し合っているふたりの人間、それはとても美しいよ。でも彼らは、なんによってそのふたりだけの状態に滋養をあたえるんだろうか? たとえこの世の中がどんなに軽蔑すべきものだとしても、彼らが話し合えるためには、その世の中を必要とするんだよ。
――黙っていることもできるわ。
――隣のテーブルの、あのおふたりさんみたいに? とジャン=マルクは笑った。ああ、いや。どんな愛も沈黙に抵抗して生き延びられはしないさ。
「恋愛」を持続させるためには「軽蔑すべき」世の中を材料にした「会話」を必要とする。そして、読者は「軽蔑すべき」世の中を材料にした「会話」を必要とするものがもう一つあることに気づく。それは何? 「小説」に決まってるじゃありませんか!
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする