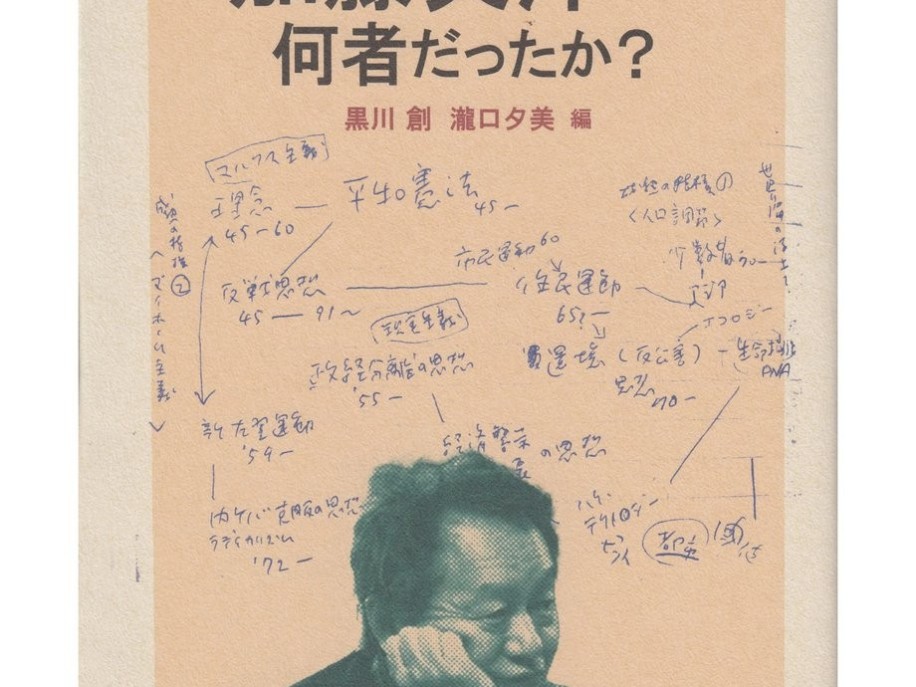書評
『回帰する月々の記―続・縄文杉の木蔭にて』(新宿書房)
十五夜に浜で……
まず鈴木一誌の装幀に見とれた。表には老樹の木肌、裏には冬の月。しんとした群青色。目次にはムカシウサギ、島いとこ、びろう葉帽子、離れ猿と見なれない文字が並び、頁をはやくめくりたいが、この人の本はあせってはならないのだ。ゆっくりいこう。『回帰する月々の記――続・縄文杉の木陰にて』(山尾三省、新宿書房)。
山尾三省が屋久島へ入って十三年になる。詩人であり百姓であり、ときに漁師である著者の日常の記は、六十ワットの裸電球の下、家族七人がマツオ(カツオ)のすしをたいらげるところから始まる。焼酎を飲みながら満月の光を浴び、十五夜に浜で網引きする彼に月のイメージは強い。月は満ち欠け、季節はめぐる生活のなかで「直進する文明の時間と回帰する地球の時は、共に地球から生み出された二筋の水脈である。地球に還るほかはない」と彼は悟る。
時はすすみ、しかもめぐるのならば、私たちは原発や核兵器のない数十年前へもとりあえず帰っていけるではないか、という。これは大変な自覚であり自信であると思った。
とはいえ、その人生の時とは固有で一回限りのものである。薪が愛という火ではげしく燃え、やがてとろとろ燃える燠(おき)になる。そのようになじんだ妻が突如逝く。青く晴れわたった空の下にひとりで生きていかねばならない自分をみいだしたとき、彼はまず葬式の出入りで許容量を超えた便所の肥汲みから始めなくてはならなかった。長柄のひしゃくで茶の木の根方へ肥を施す。
来年の春、もう妻と共に茶摘みをすることもないのだと思いながら、その思いに身を流してはならぬと必死に思いながら黙々と肥を運び施した。
そして海が見える裏山に墓を立てる。
墓石を抱きかかえ、ある限りの力を出した。そして遂にそれが本来の位置に座った時、自分が力の限りを尽くして抱きかかえていたものが、妻そのものであったことを突然に感じて涙があふれた。
うらやましくなるようないのちの濃さである。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする