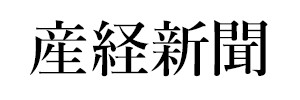書評
『天皇制の文化人類学』(岩波書店)
昭和から平成へ、掴みどころなく流れる習俗の筋書き。その正体を見とどけたい読者へ、タイムリーなプレゼントだ。この一冊で、山口昌男氏が過去三十年間、天皇制と王権をどう追ってきたかわかる。
折にふれ、多彩な角度からこのテーマを論じた文章の集成だが、基調は驚くほど一貫している。改めて読みかえすと、トリックスターさながらに登場した山口氏の発想と用語が、いまはふつうに口にされるようになったと、時代の流れを感じさせられる。
氏の説は中心ー周縁図式、または象徴の宇宙論(コスモロジー)の名で知られる。簡単におさらいしてみよう。
天皇制など過去の遺物にすぎないという戦後民主主義の楽観に、氏は与しなかった。日本史を専攻のあと人類学、それもアフリカ王権研究に転じたのは、天皇制を念頭においてのことという。そして、フレイザー『金枝』の王殺し説を、象徴人類学の先駆と再評価。それをふくらませ、どんな共同体や国家も、権力を集中する中心化の作用、それに抗する非中心化の作用、の二つを内蔵する。そして、両者が劇的に交錯する周期的な場が祝祭だ、と考える。
中心ー周縁図式は、よほど便利とみえ、七〇年代にかなり卑俗なかたちで流布した。むろん山口氏の責任でない。肝心なのは、氏がこの図式を踏まえ、どこまで天皇制に切りこんだかである。
なぜこの図式が、どんな社会の象徴世界にもあてはまるのか? ふつうの王権と天皇制は、どこが違うのか? 問題をもっと詰めるなら、それをはっきりさせることだ。この点がややもの足りない。
山口氏は、精神分析など個人心理のはたらきに関心をよせ、その総和として中心ー周縁の力学を語る。天皇制も、その普遍的な力学に従う、と強調する。確かにそうだが、象徴の宇宙論では、その先が見えにくい。天皇制の独自な姿を追うには、個人心理でなく、人びとの行動についてなにか仮定をおいたうえで、全体社会のもっと具体的なモデルを考えてみることも必要ではないか。
【この書評が収録されている書籍】
折にふれ、多彩な角度からこのテーマを論じた文章の集成だが、基調は驚くほど一貫している。改めて読みかえすと、トリックスターさながらに登場した山口氏の発想と用語が、いまはふつうに口にされるようになったと、時代の流れを感じさせられる。
氏の説は中心ー周縁図式、または象徴の宇宙論(コスモロジー)の名で知られる。簡単におさらいしてみよう。
天皇制など過去の遺物にすぎないという戦後民主主義の楽観に、氏は与しなかった。日本史を専攻のあと人類学、それもアフリカ王権研究に転じたのは、天皇制を念頭においてのことという。そして、フレイザー『金枝』の王殺し説を、象徴人類学の先駆と再評価。それをふくらませ、どんな共同体や国家も、権力を集中する中心化の作用、それに抗する非中心化の作用、の二つを内蔵する。そして、両者が劇的に交錯する周期的な場が祝祭だ、と考える。
中心ー周縁図式は、よほど便利とみえ、七〇年代にかなり卑俗なかたちで流布した。むろん山口氏の責任でない。肝心なのは、氏がこの図式を踏まえ、どこまで天皇制に切りこんだかである。
なぜこの図式が、どんな社会の象徴世界にもあてはまるのか? ふつうの王権と天皇制は、どこが違うのか? 問題をもっと詰めるなら、それをはっきりさせることだ。この点がややもの足りない。
山口氏は、精神分析など個人心理のはたらきに関心をよせ、その総和として中心ー周縁の力学を語る。天皇制も、その普遍的な力学に従う、と強調する。確かにそうだが、象徴の宇宙論では、その先が見えにくい。天皇制の独自な姿を追うには、個人心理でなく、人びとの行動についてなにか仮定をおいたうえで、全体社会のもっと具体的なモデルを考えてみることも必要ではないか。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする