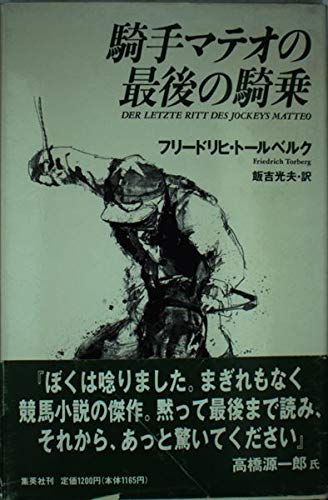書評
『カフカの恋人 ミレナ』(平凡社)
生き生きした燃える火
前略、ゆかりちゃん。こないだの晩は楽しかった。あのときちょっと話した『カフカの恋人 ミレナ』ね、絶版になってたのだけれど、平凡社ライブラリーで復刊されたようです。ぜひお読みください(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1993年)。
著者はマルガレーテ・ブーバー=ノイマンという女性。大変な時代に大変な情況に生き合わせた人といっていいでしょう。ドイツ共産党とコミンテルンの幹部であった夫ハインツ・ノイマンはモスクワで粛清され、彼女はソヴェトの強制収容所に送られ、一九四〇年にナチスの手に引き渡される、という想像を絶する体験をしたんですもの。二つの全体主義の収容所の経験は『スターリンとヒトラーの囚人として』という本になっていますが、ベルリンの北方約八十キロのところにあったナチスのラーヴェンスブリュック女性強制収容所で、彼女は忘れられぬ友ミレナ・イェセンスカーに出逢うのです。
「プラハの、ミレナです」と自己紹介した彼女は背が高く、目と顎(あご)は強い決断力を現わし、優雅で生きいきした身のこなしをしていた。自由で無頓着でゆうゆうと、くじけずにいた。列になって行進することを拒否し、口笛をふき、大胆に友情を示す彼女は、屈従を強いられる収容所にあって、唯一人「魂の囚人」ではなかった。
マルガレーテとミレナはすぐさまお互いを見分け、絶望の中でお互いを生きる支えにし、「ふたたび自由になったら一緒に本を書きましょう」と耐えがたい経験を記憶に刻むのです。この本は収容所で死んだミレナの肖像を、生きのびたマルガレーテが描いたもので、女性同士の友情について深く考えさせられます。
ミレナは一八九五年、プラハ生まれ。歯医者の娘であること、通ったミネルヴァ女学校の自由な雰囲気など、私たちと共通点を見つけてそれもうれしかったの。少女のときから自由に主体的に生きるって屈従しない精神を作るよね。
でも、あの年頃ってエキセントリックじゃない? 感受性が強く、字義通り大道からはずれて奇をてらってたミレナが、社会にまともに向きあうほどに、人間的誠実さや正義感をとぎすまし、まさにナチスのあの時代に、「人間の大道」を進んだところが私には興味深いのです。
その名前は、フランツ・カフカの「ミレナへの手紙」で一番知られているでしょう。カフカは「彼女は、いままで見たこともない、生き生きした燃える火だ」と書いてるわ。一方、ミレナも「完全性、純粋さ、真実をかれほど徹底的に議論の余地なくもとめる人間はいないと思います」とカフカを評し、「誠実な男らしい顔、まっすぐに見つめる静かな眼」に夢中になったのでした。
しかし情熱的な人妻ミレナはカフカにすべてを、当然、肉体的な愛をも求め、すでに肺を病んでいたカフカは、それに応えられず、後ずさりした。短い期間で恋愛は挫折したけれど、ミレナはカフカの作品をチェコ語に最初に訳し、その早い死に当たり、心を打つ追悼文を書いています。
たしかに恋多きひとでした。生命力が強いのね。一日五十時間分生きたんじゃないかな。愛する夫ポラックの不実に苦しみ、ジャーナリストとして働き、精神的におかしくなって麻薬に溺れたこともあった。子どもを育てながら、仲間のために食事をつくり、困っている人は助けずにはいられなかった。「あなたの真剣さとあなたの力は、なんという深淵までおりていくのでしょう」。これもカフカのミレナ評です。
ユダヤ人ではないのに、わざとダビデの星をつけて町を歩くような彼女の向こうみずが私は好きだわ。そしてユダヤ人の救援活動に身を挺して捕らわれ、収容所で生を終えた。
一見、平和で豊かに見える〈いま〉だけど本当はそうじゃない。ただ鈍らされ、馴らされ、忘れさせられていることが多いと思うの。だから私は過酷な時代にミレナの示した、イデオロギーではない市民的勇気、人間らしさ、精神の誇りと張りをじっと考えてみたいと思うのです。ゆかりちゃん、また会いたいね。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
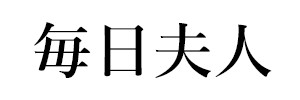
毎日夫人(終刊) 1993年頃
ALL REVIEWSをフォローする