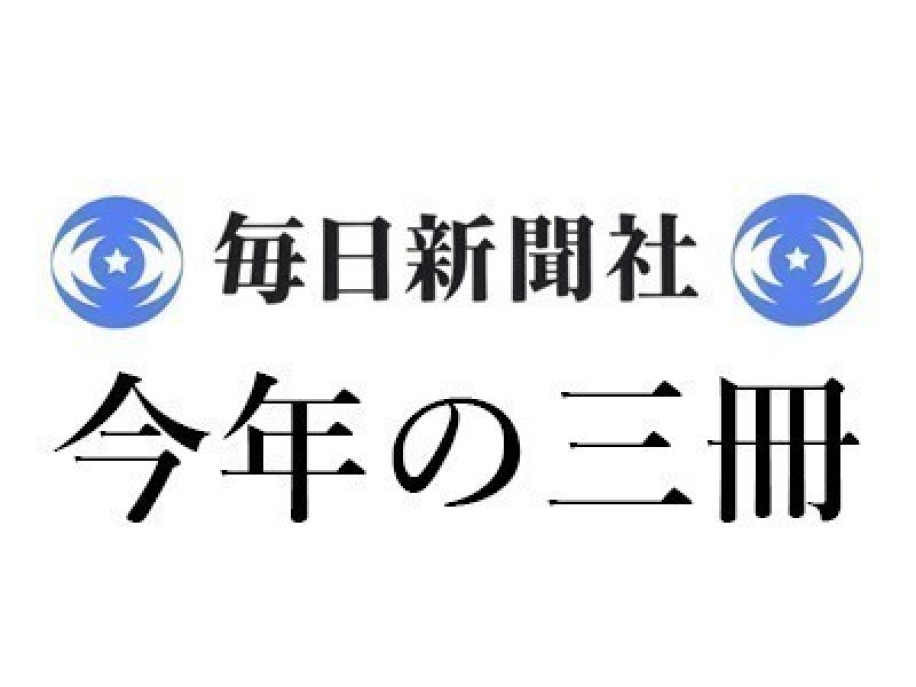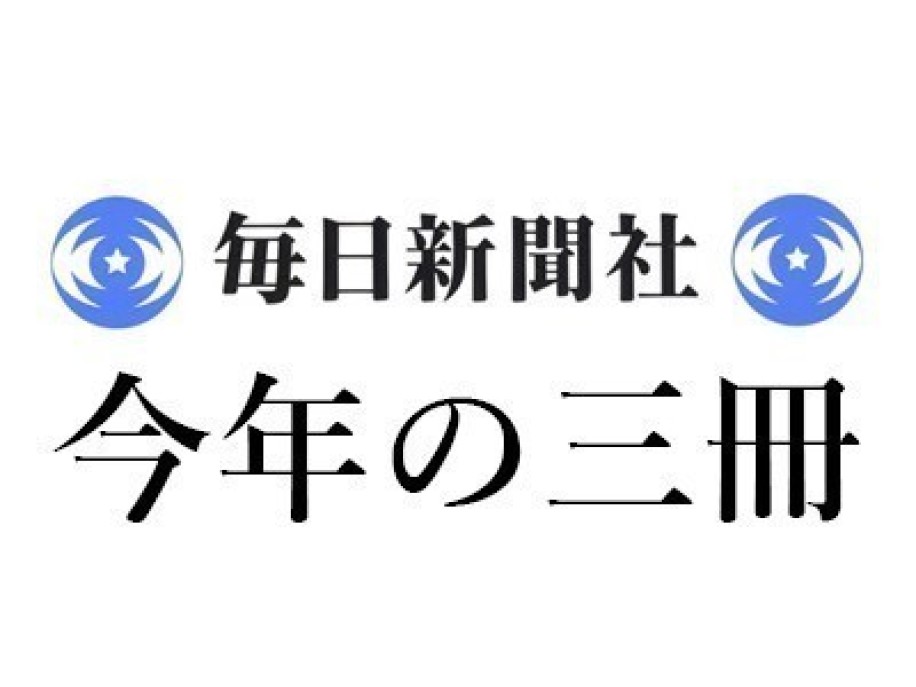書評
『奴隷の哲学者エピクテトス 人生の授業 ――この生きづらい世の中で「よく生きる」ために』(ダイヤモンド社)
心の自由に目を向け、心豊かに生きる
二世紀の五賢帝最後の皇帝マルクス・アウレリウスは奴隷あがりの哲学者エピクテトスから最も深い影響を受けたという。ストア派の哲人皇帝の名高い『自省録』をひもとけば、皇帝が奴隷出身の哲学者のまぎれもない忠実な弟子であったことが分かる。といっても、直々に師弟であったわけではなく、師と仰ぐ貴族ルスティクスに導かれて、エピクテトスの「覚書」に親しんだのである。奴隷身分から解放されたエピクテトスは、ローマを去ってギリシア本土のニコポリスに移住し私塾で教師をしていたが、ソクラテスと同様に、とくに著作を残さなかった。彼の弟子の一人が言行録のごとき『語録』を作成し、やがて門下生以外にも流布して広く読まれるようになったらしい。さらに、これを抜粋した文庫本のごとき『提要』が編纂(へんさん)され、それが広範に出まわって、後代にも圧倒的な影響をおよぼしたという。
そもそも、ストア哲学は前四世紀末ごろギリシアではじまり、ローマ帝国で受容されるころには、とくに人間の生き方に心を向ける実践倫理になった。ヘレニズム期からローマ帝政期にかけて、三千年前からの地中海文明は頂上に昇り、人類が初めてグローバル世界を目にした時代である。物資の交易も人々の交流も情報の流通も盛んになればなるほど、その荒波に流されず生きるにはどうすればいいのか、その心構えが模索されたのである。その意味で、ストア哲学は二十一世紀の現代にも通じる指針をふくんでいる。
本書は、それぞれの話題について、まず漫画で分かりやすい事例を描き、『提要』の語録で指針を示し、最後に専門家の著者が現代に即して解説する。具体的な話題が数多く取り上げられているので、実に身にしみて理解できるのはありがたい。
エピクテトスは『語録』のなかで、しばしば「心像(ファンタジア)に拉致されるな」という表現を好んで使う。地位、名声、財産などの上っ面の評判ばかりに気をとられて、羨望(せんぼう)や嫉妬が生まれる。そのような外観に幸せがあるわけではないのだ。
大切なことは「我々次第であるもの」と「我々次第でないもの」をはっきりと識別することだ、とエピクテトスはくりかえし指摘する。家柄、遺産、外貌など、あるいは友人、知人、家族にあっても他者の思惑や性格などはどうしようもないものである。それらが嫌であったなら、他者に対する自分の心構えを変えたり制御したりすることだと忠告する。心の自由にいたる唯一の道は「我々次第でないもの」を軽く見ることであるという。
エピクテトスによれば、人々の不安をかきたてるのは、事柄(プラグマタ)それ自体ではなく、それに関する考え方(ドグマタ)である。たとえば、死であってすらそれ自体は恐ろしいものではなく、「死は恐ろしい」という思い込みが正体なのだ。
さらに、何ごとにあっても「私はそれを失ってしまった」とは言うな、と忠告する。たとえ最愛の子供や配偶者でも「私はお返しした」と言うべきだという。自分の外側にあるものはいつか失う可能性があることを肝に銘じておかなければならないのだ。
ストア哲学はしばしば禁欲主義として理解されている。だが、それは心身の欲望を抑えつけるのではなく、人間の心の自由に目を向け、心豊かに生きる術なのである。たしかに、個人の心構えとしてはグローバル世界の現代にも通じる道が示唆されている。だが、政治、社会、外交のような集団の行動規範としてなら、どうだろうか。日中、日韓などの隣人問題をかかえるわが国には悩ましい論点が浮かびあがってくる。
ALL REVIEWSをフォローする