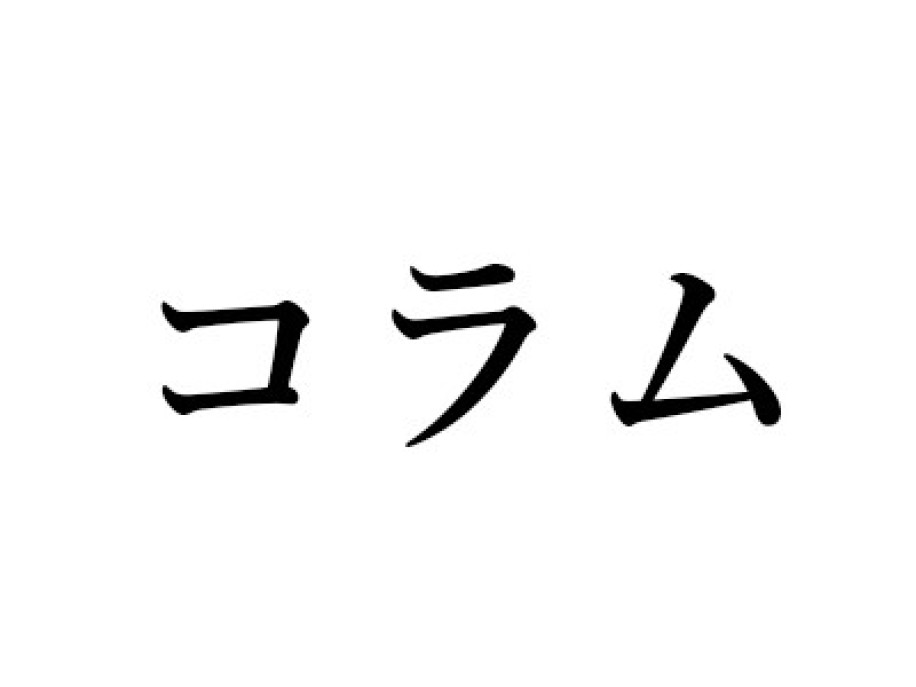書評
『日本人の老後 60歳から100歳まで100人が語る』(晶文社)
老人たちの生活と意見
今朝からラジオ体操を始めた。座って原稿ばかり書いているので、膝が痛くなる。腰も重い。少しは体を動かさなければ。神社の境内に六時半に集まる老若男女。おなかの出たおばあちゃんも、野球帽のおじいさんも、見ていると私よりずっと体が柔らかい。十一年間、町の老人(私はお年寄りだのシルバーだのいうより、この方が威厳があって好き)の聞き書きをしてきたのに、『日本人の老後』(晶文社)の百人へのインタビューを読んで知らないことが多かった。
たとえば私の近所、根津に住む柏木せきのさんは百歳。トイレにいくたび、「百歳になっても、お漏らしせずにこうして自分一人で行けるんだからいいほうなのかなあ」と思うという。家の周りを掃除し、上野の松坂屋にもバスで行き、月に三回は外食もする。四年前に家をマンションに建て替えた。融資に当り「九十過ぎのおばあさんに貸したのは、銀行始まって以来だ」といわれたそうだ。
こういう驚異的な老人の後ろには必ず親切な隣人、やさしくてしっかりした親戚のネットワークがある。
老人になって生活のしかたが変わる人もいる。東京・荻窪で眼鏡屋さんだった大圖正さん(八十一歳)は店をちょうど五十年でやめ、神奈川・相模原のマンションに夫婦二人暮らし。男が年上で寿命も短いからって、先に行くとは限らない。「そろそろあなたも考えなさいよ」と奥さんにいわれ、朝ごはんを作りはじめた。八時半に準備ができると「ハイ奥さん、朝ごはんができましたよ」と起こしにいく。「五十年以上もお風呂掃除してイヤんなっちゃった」と奥さんがいうと、これも全面的にバトンタッチ。何でも新しいことに気楽に挑戦してみる。それが結構楽しい。
有料老人ホームに住んでみた。サウナ、プール、美容室があり、食事はおいしい。最初は快適だったのに、仲良しグループができてくると、やれ旅行だ、買物だ、お誕生会だ、古稀のお祝いだとつきあいが強制される。渡部照子さん(七十七歳)は「なんだか窮屈だな」と思って、老人ホームを出て高齢者向けマンションに引っ越した。敷地内に地域の人も使える施設があって風通しがいい。
余暇を上手にゼイタクに使っている老人も多い。俳句、植木、小説、自転車旅行、人力車のボランティア、ロシア語通訳。
バレーボールのコーチをしている大島芳子さん(七十八歳)は、明日は練習という日はうれしくてしょうがない。森田真穂さん(八十一歳)は六十六歳で走り幅跳のマスターズ世界大会に出た。耳が悪いけどバイオリンを弾き、オーケストラに入った武田英男さん(八十二歳)、七十八歳で大学入学資格検定に合格した畳屋の小林一さんもいる。「何で勉強するんだっていうとね、目的じゃなくて理想なんですよ」
妻を介護しながら能の舞台に立つ人もいるし、痴呆症の妻を映画に撮った人もいる。高齢化社会は男たちの人生や価値観をも大きく変えているのだ。
老後にはたしかにつらい、大変なことも多いにちがいない。しかし老いとの心構えやつきあい方で、楽しくも苦しくもなる。目の黒いうちにと時価八億円の土地を市に寄付してしまった金井きみさんは、もう税金のことを考えずに、あした何を食べようかと考えられてうれしいという。妻との関係を大事にしながら、一生一度のプラトニックラブに心燃やす男性もいる。いいなあ。エピローグの北林谷栄さんの言葉がすてきだ。「年老いても、想像力というのは自由ですから」
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
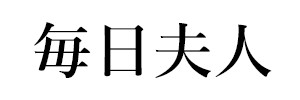
毎日夫人(終刊) 1993~1996年
ALL REVIEWSをフォローする