書評
『随筆集 明治の東京』(岩波書店)
鏑木清方画伯の回顧展を見に行くと、いつも狂おしい気持に襲われる。
買いたい、手に入れたい、所有したい、ここにある絵のすべてが欲しい! と思ってしまうのだ。私はがいして絵を見るのは好きだが、買いたいとはめったに思わない(私のこの狭苦しい部屋に置いたら絵がかわいそうだし、第一高くて手が出ないし……)。それなのに清方の絵だけはやみくもに欲しい! と思う。私が凄い富豪だったら、邸なんかどうでもいい、清方作品のコレクションに血道をあげるだろう。
なぜなのか自分でもほんとうのところはよくわからないが、鏑木清方の絵が好きだ。心が震える。有名な「築地明石町」や「衿おしろい」や「一葉」(樋口一葉の肖像画)や「小説家と挿絵画家」(清方の画室に泉鏡花が訪れたところの絵)、それから一葉の「たけくらべ」や「にごりえ」の挿絵などは知っている人も多いと思う。私はそういった作品の、何と言うか、すっぱりとした美しさに心が震える。私がいつもぼんやりと「こういうのが綺麗」「こういうのが気持いい」「こういうのがかっこいい」と感じているものを、清方が精選し、濾過し、凝縮して、絵画という一つのカタチにしてくれたようで、「ありがたさに涙こぼれる」という気持になってしまうのだ。
鏑木清方は明治十一年に生まれ、昭和四十七年に九十三歳で亡くなった。昭和初期に川端龍子(りゅうし)がとなえた「会場芸術」に反論し、「卓上芸術」を提唱した。大作ではなく、また床の間の掛け物でもない、卓上で手にとって心ゆくまで鑑賞したくなるような芸術(たとえば色紙や短冊)があってもいいではないかという論である。仰ぎ見る芸術ではなく、うつむいて見る芸術——。
実際、清方のよさとか独自性は、絵日記や挿絵や表紙絵といった、ちょっとした小さなもののほうにより強く発揮されているような気がする。こういう作品を見るたび、私は、自慢ぽい気持にもなる。どうだ、日本人は凄いだろう。こんな繊細軽快な美の伝統を持っているのだもの。アブラをコテコテ塗りあげるなんて野暮なことはしないんだい——というような。
中でも一番好きなのは、「築地川」という連作の中の一つで、白い服を着た金髪の女の子が輪っか遊びをしている絵である。その色どりの程のよさったらない。水色と緑色が淡く煙ったようなところに少女のリボンと立ち葵の赤が効いている。私は、まさに「舌なめずり」するような気持で、隅々まで眺める。
さて、ようやく本題に入る。五年ほど前に岩波文庫から清方の随筆集『明治の東京』が出た(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1994年)。その表紙カバーにこの「築地川」の金髪少女の絵が使われている(印刷では色の調子がよく出ていない感じがするが)。
清方は晩年にも「わたしは、小説を書きたかった」と語っていたという人である。小説はともかく十冊にのぼる随筆集を書いていて、この『明治の東京』なぞを読むと、その絵と同様のすがすがしさを感じさせる名文だと思う。
名文というと人は、あんまり日常ではなじみのない凝った言い回しや、装飾語を駆使した文章を思い浮かべるようだが、私なぞはそういうのは何とも言えず照れくさく恥ずかしく感じられ、ついつい「くさい文章!」と蹴散らかしたくなってしまう(久生十蘭は珍しい例外だ)。清方の文章は、(ほんとうは苦心したのかもしれないが)そういう凝ったところの見えない、楽な、いい文章だと思う。この随筆集にも書かれているが、白足袋は晴れがましい感じがするので自分はめったにはかない。紺足袋のほうがいい——という人の文章である。
「築地川」をはじめ、自分が育った築地・銀座近辺のことを書いた一連のエッセーも非常に興味深いが(八年ほど前から私は築地の隣町に住んでいて、そこは私の父の生地でもあるので)、今回私が清方の「卓上芸術」を見るのと同じような「舌なめずり」する気持で読んだのは、「前垂」というエッセーである。
前垂というのは今で言う前掛け(エプロン)のことで、子どもの頃からの前垂にまつわる思い出を中心につづったものだが、
といったくだりには、清方の絵を眺めるのと同じ喜びがある。
清方は江戸直系の下町育ちである。父親はジャーナリストだったが、下町独得の気風や美意識に強い愛着を持っていた。この「前垂」の中に、
という一節がある。サラリと書いているが、他のエッセーでも、下町のお酒落心が山の手や「御国から出て来た方たち」に駆逐されて行ったことを繰り返し書いており、その奥にはそうとうの憤懣があったらしく思われる。
「広重と安治」というエッセーでは、
と愚痴を言い、「明治以来東京の名物」というエッセーでは、
と珍しく怒っているのが……うーん、痛ましいような、またほほえましいような。
近頃は下町という言葉に関しておそるべき拡大解釈がまかり通っているが、「山の手と下町」というエッセーを読むと、昔にさかのぼってもう少し厳密に規定しないと、江戸文化たとえば歌舞伎のエスプリなぞというのもわからなくなってしまうと思う。清方に言わせれば「この対立関係(山の手と下町)は一朝一夕のことではなく、それこそ、白柄組(しらつかぐみ)と町奴(まちやっこ)、武家と町人の初めからで、根ざしは深く三百年の昔にある」というのだもの。
私は清方と違って根っからの東京下町人ではないが「チョク」を尊ぶ美意識(チョクというのは「直」=気軽さとか、さりげなさとか、カジュアルな美とかいうことだろう)が「手重く見える」のを尊ぶ美意識に負けて行く、その無念さはよくわかるような気がする。
【この書評が収録されている書籍】
買いたい、手に入れたい、所有したい、ここにある絵のすべてが欲しい! と思ってしまうのだ。私はがいして絵を見るのは好きだが、買いたいとはめったに思わない(私のこの狭苦しい部屋に置いたら絵がかわいそうだし、第一高くて手が出ないし……)。それなのに清方の絵だけはやみくもに欲しい! と思う。私が凄い富豪だったら、邸なんかどうでもいい、清方作品のコレクションに血道をあげるだろう。
なぜなのか自分でもほんとうのところはよくわからないが、鏑木清方の絵が好きだ。心が震える。有名な「築地明石町」や「衿おしろい」や「一葉」(樋口一葉の肖像画)や「小説家と挿絵画家」(清方の画室に泉鏡花が訪れたところの絵)、それから一葉の「たけくらべ」や「にごりえ」の挿絵などは知っている人も多いと思う。私はそういった作品の、何と言うか、すっぱりとした美しさに心が震える。私がいつもぼんやりと「こういうのが綺麗」「こういうのが気持いい」「こういうのがかっこいい」と感じているものを、清方が精選し、濾過し、凝縮して、絵画という一つのカタチにしてくれたようで、「ありがたさに涙こぼれる」という気持になってしまうのだ。
鏑木清方は明治十一年に生まれ、昭和四十七年に九十三歳で亡くなった。昭和初期に川端龍子(りゅうし)がとなえた「会場芸術」に反論し、「卓上芸術」を提唱した。大作ではなく、また床の間の掛け物でもない、卓上で手にとって心ゆくまで鑑賞したくなるような芸術(たとえば色紙や短冊)があってもいいではないかという論である。仰ぎ見る芸術ではなく、うつむいて見る芸術——。
実際、清方のよさとか独自性は、絵日記や挿絵や表紙絵といった、ちょっとした小さなもののほうにより強く発揮されているような気がする。こういう作品を見るたび、私は、自慢ぽい気持にもなる。どうだ、日本人は凄いだろう。こんな繊細軽快な美の伝統を持っているのだもの。アブラをコテコテ塗りあげるなんて野暮なことはしないんだい——というような。
中でも一番好きなのは、「築地川」という連作の中の一つで、白い服を着た金髪の女の子が輪っか遊びをしている絵である。その色どりの程のよさったらない。水色と緑色が淡く煙ったようなところに少女のリボンと立ち葵の赤が効いている。私は、まさに「舌なめずり」するような気持で、隅々まで眺める。
さて、ようやく本題に入る。五年ほど前に岩波文庫から清方の随筆集『明治の東京』が出た(ALL REVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1994年)。その表紙カバーにこの「築地川」の金髪少女の絵が使われている(印刷では色の調子がよく出ていない感じがするが)。
清方は晩年にも「わたしは、小説を書きたかった」と語っていたという人である。小説はともかく十冊にのぼる随筆集を書いていて、この『明治の東京』なぞを読むと、その絵と同様のすがすがしさを感じさせる名文だと思う。
名文というと人は、あんまり日常ではなじみのない凝った言い回しや、装飾語を駆使した文章を思い浮かべるようだが、私なぞはそういうのは何とも言えず照れくさく恥ずかしく感じられ、ついつい「くさい文章!」と蹴散らかしたくなってしまう(久生十蘭は珍しい例外だ)。清方の文章は、(ほんとうは苦心したのかもしれないが)そういう凝ったところの見えない、楽な、いい文章だと思う。この随筆集にも書かれているが、白足袋は晴れがましい感じがするので自分はめったにはかない。紺足袋のほうがいい——という人の文章である。
「築地川」をはじめ、自分が育った築地・銀座近辺のことを書いた一連のエッセーも非常に興味深いが(八年ほど前から私は築地の隣町に住んでいて、そこは私の父の生地でもあるので)、今回私が清方の「卓上芸術」を見るのと同じような「舌なめずり」する気持で読んだのは、「前垂」というエッセーである。
前垂というのは今で言う前掛け(エプロン)のことで、子どもの頃からの前垂にまつわる思い出を中心につづったものだが、
眉(まゆ)を剃(そ)った痕(あと)の青々とした、年増(としま)の女房が、小紋縮緬(ちりめん)の三枚襲(がさね)の裾を引いて、山繭(やままゆ)ちりめんの前垂、紫絞(しぼり)の絎紐(くけひも)ゆるく引き結び、塗膳(ぬりぜん)にふきんをかけているさまなど、前垂姿の風情(ふぜい)よきものの一つにかぞえよう。
紫矢絣(やがすり)に黒い襟をかけ、緋鹿(ひが)の子(こ)の帯、それに眼覚(めざ)めるばかりの友禅の前垂を締めたのはあの時代の町娘特有の美しさであった。
といったくだりには、清方の絵を眺めるのと同じ喜びがある。
清方は江戸直系の下町育ちである。父親はジャーナリストだったが、下町独得の気風や美意識に強い愛着を持っていた。この「前垂」の中に、
明治から大正へかわる頃(ころ)から、おかみさんと呼んだ人妻の呼び名が、見さかいなしに奥様と呼ばれるようになった、ちょうどそれと軌をひとつにして、黒い襟も、前垂も、御国(おくに)から出て来た方たちに、さも卑しきものとして嫌われ出した。
その頃から以来、チョクに見えるということは、下品と同じことに思われ、手重く見えるというのは、ものが善(よ)く考えられ、女のきものに金の糸、漆(うるし)の糸など、前の代にはあまり行われなかったのが、ザラに行きわたるようになって、また世は簡素な中の美しさを見直させるところへ廻(まわ)って来た。
という一節がある。サラリと書いているが、他のエッセーでも、下町のお酒落心が山の手や「御国から出て来た方たち」に駆逐されて行ったことを繰り返し書いており、その奥にはそうとうの憤懣があったらしく思われる。
「広重と安治」というエッセーでは、
名前の呼び方一つを取り上げて見ても、よけいな見栄(みえ)に気の張ることがなく、めいめいが分を守ればものみな心やすく、長屋住(ずま)いにも鉢植(はちうえ)の手入して、暮らしを楽しむ根からの江戸人東京人の、嫌いなのは、押しの強い、図々(ずうずう)しい、出しゃばり、我利々々(がりがり)、思いやりのない、およそこういう種類の人種はなかま外(はず)れとされた気風はそのまま広重の『江戸土産』となり、安治の東京風景となって、今更のようにその頃(注・明治の中頃まで)の生活が偲(しの)ばれる。
と愚痴を言い、「明治以来東京の名物」というエッセーでは、
この浅漬のことを関西の方ではべったら漬と呼んでいたのだが、最近東京でもいつしか関西流にべったら漬というようになった。……(略)浅漬と呼んでこそ、あっさりして、歯切れのいいあの香のものの魅力がある。べったら漬ではいかにも場違いで、第一ひどくまずそうだ、ところが日本橋の角店(かどみせ)の軒先に高々とべったら漬、とかいてあるのを見た。昔の日本橋は江戸の真んなかで、江戸っ子のお守(もり)はここから出ますといったような気稟(きっぷ)の土地だった、その日本橋にべったら漬の刻印を、私はいまだに会得しかねている。
と珍しく怒っているのが……うーん、痛ましいような、またほほえましいような。
近頃は下町という言葉に関しておそるべき拡大解釈がまかり通っているが、「山の手と下町」というエッセーを読むと、昔にさかのぼってもう少し厳密に規定しないと、江戸文化たとえば歌舞伎のエスプリなぞというのもわからなくなってしまうと思う。清方に言わせれば「この対立関係(山の手と下町)は一朝一夕のことではなく、それこそ、白柄組(しらつかぐみ)と町奴(まちやっこ)、武家と町人の初めからで、根ざしは深く三百年の昔にある」というのだもの。
私は清方と違って根っからの東京下町人ではないが「チョク」を尊ぶ美意識(チョクというのは「直」=気軽さとか、さりげなさとか、カジュアルな美とかいうことだろう)が「手重く見える」のを尊ぶ美意識に負けて行く、その無念さはよくわかるような気がする。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
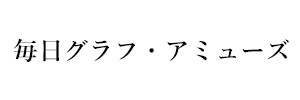
毎日グラフ・アミューズ(終刊) 1994年10月12日号
ALL REVIEWSをフォローする








































