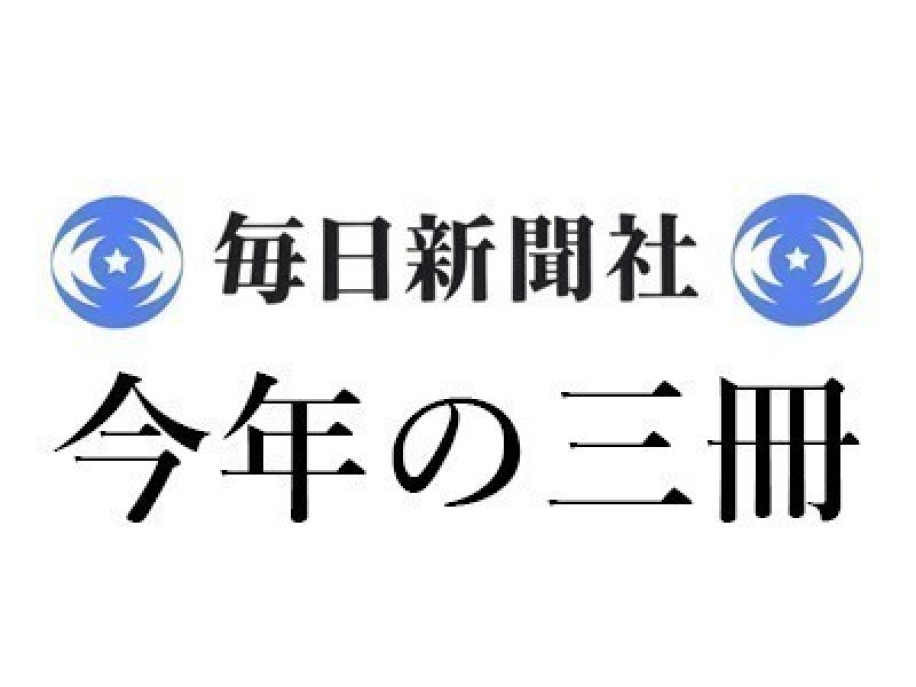書評
『言わなければよかったのに日記』(中央公論新社)
住専をめぐる日本の経済エリートたちの無能と無責任ぶりに対しては私も大いに怒っているが、しかし、批判派の、「庶民」という言葉を連発して恥じない無神経さにもいいかげんうんざりしている(ALLREVIEWS事務局注:本書評執筆時期は1995年頃)。
ついこのあいだまで財テクだの株だの不動産だのと浮かれ騒いでいたくせに、どうしてああ平然と自分を「庶民」と言いきれるのだろう。不思議でたまらない。住専問題に対しては、私たちは「一納税者として」あるいは「一国民として」という立場で考えるべきじゃないだろうか。「庶民」という言葉にはあまりにもよけいな情緒がまとわりつきすぎる。
いんちき庶民にうんざりしていたので、自然と深沢七郎の本に手が伸びた。私にとっては深沢七郎の小説の中に出てくる人たち――自分の頑丈な歯を恥じ入り、自らつぶして、嬉々として死地におもむく『楢山節考』のおりん婆さんや、孫の友人たちに自分の姿を見せたくなくて物置小屋にかくれている『庶民烈伝 おくま嘘歌』のおくま婆さんたち――この人たちこそが「庶民」という言葉をとうとく美しく輝かす存在なのであって、私はとてもおそれ多くて「庶民」なんぞとは言えません。
深沢七郎の書いたものは、三年に一度くらいのペースで恋しくなる。私は基本的に方言で書かれた小説が苦手なのだが、深沢七郎は別格だ。あの甲州弁が恋しくなる。
さて。今回感想を書いてみたいのは、深沢七郎が『楢山節考』で突如デビューした二年後の『言わなければよかったのに日記』だ。あの傑作長編『笛吹川』を書きあげ、『東京のプリンスたち』に取りかかる直前の、おかしな身辺雑記である。『風流夢譚』事件の二年ほど前の話である。当時、深沢七郎四十四歳。
日劇ミュージックホールでギターを弾いていた男が、宝クジを買うようなつもりで原稿を送ったら、当選してしまい(中央公論新人賞)、いきなり純文学界の中央に押し出されたのである。「いつか賞を……」と刻苦勉励してきたという人間ではまるでない。絵を描く気持で文章を書き、一人楽しんで、あきたらザーッと破り捨てる。まったく自分一人の快楽だけで書いてきた人間なのである。
出版社の窓口に行って賞金を受け取って帰ってくるだけでいいと思っていたのに、実際にはそうはいかなかった。授賞式を「腹ワタが煮え返るような嫌な席」と思い、「苦しい授賞式の席で(こんな思いまでして賞金をもらうなら、来なければよかった)とも思ったりしていた」というのは、深沢七郎にとってはまったく嘘いつわりのない本音だったろう。
名誉ある賞を受けて、それが身の置きどころなく厭だった――というのは世間では珍しいリアクションだが、深沢七郎個人のなかではちゃんと理屈の筋道は通っていて(こんな立派な扱いをされるような作品とは自分では思っていなかった。自分ではただもう“おりん”のようなばあさんが好きで、楽しんで書いただけなのに。おそろしいことになってしまった……という気持)、私にはストレートにわかるような気がするのだった。世間とは逆の向きかもしれないが、この臆病で、しかも徹底的に自分本位な心の動き方はすんなりとわかり、こういう心の動き方をする人がいるということが、何かとてもうれしく楽しい気持になるのだった。
この『言わなければよかったのに日記』は、そうやっておそるおそるのぞき見た文学界のリポートというおもむきもあり、何人かの小説家に対する深沢七郎の寸評というか印象記が、まことに鋭く、おかしい。
文壇への奇妙な闖入者、深沢七郎と当時の大作家たちとの会見記は、まるで落語の「こんにゃく問答」のようだが、中でも凄かったのは石坂洋次郎の家を訪ねたときの話だ。
深沢七郎は『笛吹川』の出版記念に、以前対談で会った石坂洋次郎の家の庭に笛吹川の月見草を植えさせてもらいたいと思い立つ。それで、月見草を持って石坂家まで行くが、その前に庭の様子が気になって、道路のはじの松の木によじ登り、庭をのぞき込む。
あやしい男が松の木から庭内をうかがっているというので、石坂家の犬は騒ぐわ、女中さんは駆け出して来るわ、石坂洋次郎まで出て来て「そこにいる方は、何をしているのですか?」と声をかけるわ……。
深沢七郎は(今さら、こんな恰好で、こんなところでご挨拶をするのはイヤだ)と思い、顔を見られないようそむけ、五月晴れの空に目をそらし「あの……、鯉のぼりが……」とだけ答える。答えにならない答えだが、石坂洋次郎も女中さんも「他意はなさそうだ」と思ったのか、奥へ引っ込む。
――なんと、のどかでおかしな光景だろう。マンガかメルヘンのようだ。
数分後、そしらぬ顔で玄関から訪れると、石坂洋次郎がこれまたそしらぬ顔で「やあ」と言って迎え入れた――というのが念入りにおかしい。
深沢七郎の取った行動は、ちょっと風変わりで、「奇行」というふうに見えるけれど、すべて彼個人の中では理屈の筋道は通り過ぎるほど通っているのだ。どこまでも正気。まっとう。ただちょっと世間一般とズレていたり、向きが違うだけなのだ。
この『言わなければよかったのに日記』の中で、深沢七郎は『楢山節考』についてこんなふうに書いている。
『東京のプリンスたち』にも語られているが、深沢七郎の、自意識にたいする嫌悪は思いのほか深そうだ。私が三年に一度、深沢七郎が恋しくなるのは、私の自意識がそのくらいのペースで疲れきり、チャージを求めるようになるということなのかもしれない。
【この書評が収録されている書籍】
ついこのあいだまで財テクだの株だの不動産だのと浮かれ騒いでいたくせに、どうしてああ平然と自分を「庶民」と言いきれるのだろう。不思議でたまらない。住専問題に対しては、私たちは「一納税者として」あるいは「一国民として」という立場で考えるべきじゃないだろうか。「庶民」という言葉にはあまりにもよけいな情緒がまとわりつきすぎる。
いんちき庶民にうんざりしていたので、自然と深沢七郎の本に手が伸びた。私にとっては深沢七郎の小説の中に出てくる人たち――自分の頑丈な歯を恥じ入り、自らつぶして、嬉々として死地におもむく『楢山節考』のおりん婆さんや、孫の友人たちに自分の姿を見せたくなくて物置小屋にかくれている『庶民烈伝 おくま嘘歌』のおくま婆さんたち――この人たちこそが「庶民」という言葉をとうとく美しく輝かす存在なのであって、私はとてもおそれ多くて「庶民」なんぞとは言えません。
深沢七郎の書いたものは、三年に一度くらいのペースで恋しくなる。私は基本的に方言で書かれた小説が苦手なのだが、深沢七郎は別格だ。あの甲州弁が恋しくなる。
さて。今回感想を書いてみたいのは、深沢七郎が『楢山節考』で突如デビューした二年後の『言わなければよかったのに日記』だ。あの傑作長編『笛吹川』を書きあげ、『東京のプリンスたち』に取りかかる直前の、おかしな身辺雑記である。『風流夢譚』事件の二年ほど前の話である。当時、深沢七郎四十四歳。
日劇ミュージックホールでギターを弾いていた男が、宝クジを買うようなつもりで原稿を送ったら、当選してしまい(中央公論新人賞)、いきなり純文学界の中央に押し出されたのである。「いつか賞を……」と刻苦勉励してきたという人間ではまるでない。絵を描く気持で文章を書き、一人楽しんで、あきたらザーッと破り捨てる。まったく自分一人の快楽だけで書いてきた人間なのである。
出版社の窓口に行って賞金を受け取って帰ってくるだけでいいと思っていたのに、実際にはそうはいかなかった。授賞式を「腹ワタが煮え返るような嫌な席」と思い、「苦しい授賞式の席で(こんな思いまでして賞金をもらうなら、来なければよかった)とも思ったりしていた」というのは、深沢七郎にとってはまったく嘘いつわりのない本音だったろう。
名誉ある賞を受けて、それが身の置きどころなく厭だった――というのは世間では珍しいリアクションだが、深沢七郎個人のなかではちゃんと理屈の筋道は通っていて(こんな立派な扱いをされるような作品とは自分では思っていなかった。自分ではただもう“おりん”のようなばあさんが好きで、楽しんで書いただけなのに。おそろしいことになってしまった……という気持)、私にはストレートにわかるような気がするのだった。世間とは逆の向きかもしれないが、この臆病で、しかも徹底的に自分本位な心の動き方はすんなりとわかり、こういう心の動き方をする人がいるということが、何かとてもうれしく楽しい気持になるのだった。
この『言わなければよかったのに日記』は、そうやっておそるおそるのぞき見た文学界のリポートというおもむきもあり、何人かの小説家に対する深沢七郎の寸評というか印象記が、まことに鋭く、おかしい。
伊藤先生(㊟伊藤整)はスマートで、ちょっと、大学教授のような人だと思った。あとで知ったのだが、本当に大学の教授をしているというのでまた驚いた。ボクのカンは当らないはずだが、伊藤先生だけはうまく当ったので、これは一世一代の名演奏のような気がした。ボクのカンは全然だめで、石坂先生(㊟石坂洋次郎)は産婦人科のお医者さんのような気がした。副業で小説を書いてるのだと思った。井伏先生(㊟井伏鱒二)は質屋のご隠居さんで、副業に小説を書いているらしいと思った。武田先生(㊟武田泰淳)は通産省の役人をやっていた人ではないかと思った。正宗先生(㊟正宗白鳥)は外国の大使を長いことやっていた人だと思った。
文壇への奇妙な闖入者、深沢七郎と当時の大作家たちとの会見記は、まるで落語の「こんにゃく問答」のようだが、中でも凄かったのは石坂洋次郎の家を訪ねたときの話だ。
深沢七郎は『笛吹川』の出版記念に、以前対談で会った石坂洋次郎の家の庭に笛吹川の月見草を植えさせてもらいたいと思い立つ。それで、月見草を持って石坂家まで行くが、その前に庭の様子が気になって、道路のはじの松の木によじ登り、庭をのぞき込む。
あやしい男が松の木から庭内をうかがっているというので、石坂家の犬は騒ぐわ、女中さんは駆け出して来るわ、石坂洋次郎まで出て来て「そこにいる方は、何をしているのですか?」と声をかけるわ……。
深沢七郎は(今さら、こんな恰好で、こんなところでご挨拶をするのはイヤだ)と思い、顔を見られないようそむけ、五月晴れの空に目をそらし「あの……、鯉のぼりが……」とだけ答える。答えにならない答えだが、石坂洋次郎も女中さんも「他意はなさそうだ」と思ったのか、奥へ引っ込む。
――なんと、のどかでおかしな光景だろう。マンガかメルヘンのようだ。
数分後、そしらぬ顔で玄関から訪れると、石坂洋次郎がこれまたそしらぬ顔で「やあ」と言って迎え入れた――というのが念入りにおかしい。
深沢七郎の取った行動は、ちょっと風変わりで、「奇行」というふうに見えるけれど、すべて彼個人の中では理屈の筋道は通り過ぎるほど通っているのだ。どこまでも正気。まっとう。ただちょっと世間一般とズレていたり、向きが違うだけなのだ。
この『言わなければよかったのに日記』の中で、深沢七郎は『楢山節考』についてこんなふうに書いている。
私は若い日に、人生などということを真剣に考えたことがあった。そんなことを考えることはバカバカしいことだと思っていた。もう考えないことにしていたはずだった。
あの小説には、ボクが忘れてしまった人生観などという悲しい、面倒クサイものが、書こうともしなかったのに、形を変えて書いてしまったのではないかと思った。
『東京のプリンスたち』にも語られているが、深沢七郎の、自意識にたいする嫌悪は思いのほか深そうだ。私が三年に一度、深沢七郎が恋しくなるのは、私の自意識がそのくらいのペースで疲れきり、チャージを求めるようになるということなのかもしれない。
【この書評が収録されている書籍】
初出メディア
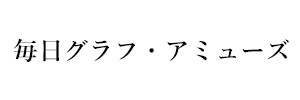
毎日グラフ・アミューズ(終刊) 1995年3月8日号~1997年1月8日号
ALL REVIEWSをフォローする