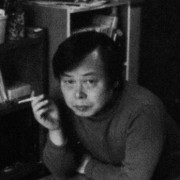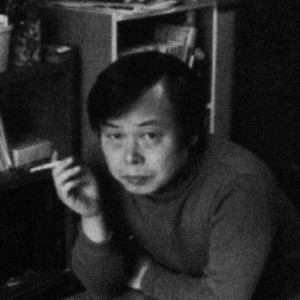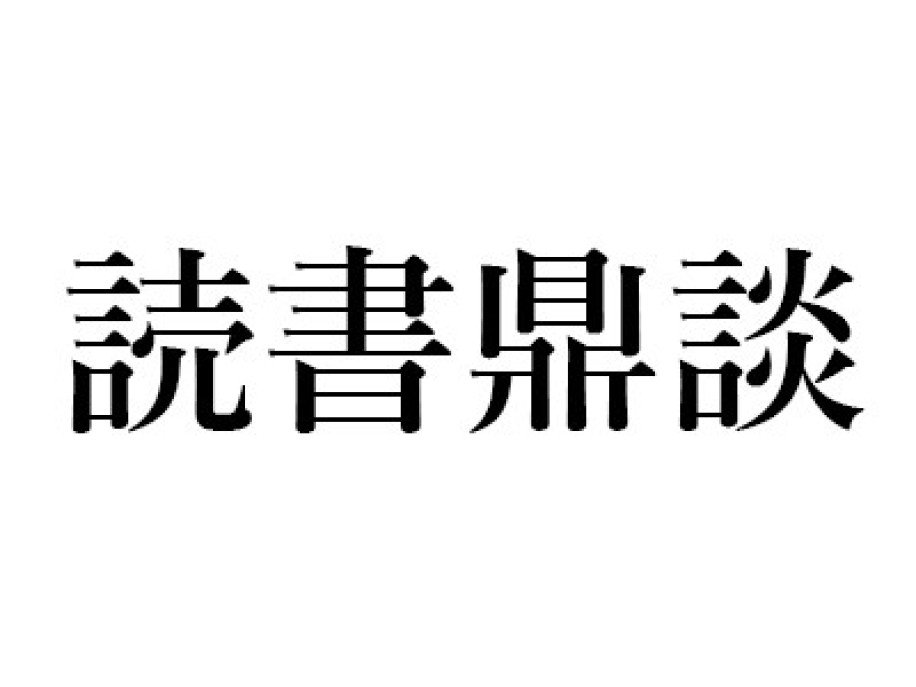内容紹介
『句集 雪女』(沖積舎)
大いなる眼に見られをり——眞鍋呉夫句集『雪女』のために
眞鍋呉夫さんは、私などはこれまで『黄金伝説』などの小説家として愛読してまいりました。ところが、この度は発句集『雪女』の作者として歴程賞を受賞されたそうです(ALL REVIEWS事務局注:本原稿執筆時期は1993年)。歴程は詩人集団でありますから、句集が受賞対象になるのは異例のことと思われます。そこでその理由を私なりに二、三憶測してみました。
『雪女』というフォークロリックな題名の句集を眞鍋さんが出されたこと自体は、『黄金伝説』のような小説作品がすでにフォークロアのモティーフをはらんでいるのでふしぎとは思いませんでした。一方、詩作品を対象にした歴程賞が発句集に与えられたことについては、この句集がたとえば萩原朔太郎や伊東静雄、李賀のいくつかの詩のフレーズを組み込んだ、鉱物質の色彩感をきらめかせているところからして納得されます。
月光に開きしままの大鋏
密會の髪の根青く發光す
青柿の蔕より青き月夜かな
ところで、この「傀儡」、「桃の皮」、「桶の箍」、「現身」の四部からなる句集の各部見出しは、ご覧のように、いずれも中身のがらんどうのものばかりです。形骸だけがあってそれを満たす内容がない。リヒテンベルクのいう「刃のない柄のないナイフ」のような、ナンセンスすれすれの表象です。
喪失の後にきた形骸。しかしこの形骸はかならずしも過去を懐かしむための装置ではありません。あるいは、過ぎ去った時間をともに過ごした故人たちを悼む儀礼的文辞ではありません。むろんここには、亡き壇一雄、亡き島尾敏雄を悼む句があります。しかし壇一雄への追憶に捧げられた「眩さのはてにありけり繼子投」のように、他界への旅立ちさえ地中海的な光と風に送られて出発する豪快な英雄神話風のエピソードへと換骨奪胎されています。
そうかといって、中身を捨て去った現実放棄の無責任な身軽さを、もっぱら楽隠居風に骨董いじりしているというのでもありません。かつては一つの全体のなかに緊密に組み込まれていたものが形骸化し断片化している現在を、唐突なオブジェとしてポンと投げ出して見せる捨て身のいさぎよさが、かえって過去の記憶をとりこぼしなく呼び寄せる、はりつめた召霊儀式の体をなしているように思われます。うしなわれた時間と断片化した今、二つの時間の交錯がふしぎなアウラを発光させて、ときにシュルレアリスム風の秀句を生み出します。
朧夜の鬚根がはえたドラム罐
月の道ちぎれた縄がおちていて
穴まどひ大いなる眼にみられをり
最後の句にきて、はっきりした転調がひびくように思います。ここでは他者性の眼、とでもいったようなものがこちらを見ています。断片化した現在が充実した過去を見ているのではありません。自我の視線が追えばそれだけ逃げ去る、名付けられないなにものか、その「大いなる眼」が見ているので、自我が見ているのではない。「大いなる眼」の視界に、記憶の細部さえも拭いおとした、純粋な存在の相が忽然として浮上してくるのです。そうしてあらためて来し方を振り返ってみると、こまやかにもなつかしい記憶の細部と思われたものも、自我の側の過去への視線からではなく、他者性の視線から見られていたのだと思い当ります。
他者性の大いなる眼に浮き身になって身をゆだねること。ヴィトゲンシュタインはかつて哲学者の仕事についていいました。現代の哲学者は牢獄の窓を一生懸命こじあけようとしているが、ふと振り返るとその牢獄の扉は開いているのではあるまいか。現代詩人の仕事もこの開かずの窓をこじあけて、追えばそれだけ遠ざかる名付けられないなにものかをつかまえる不可能性の探究にある、と申せましょう。しかしひょっとしてそれは、なにげなく振り返ってみると、閉まっていると頭から決め込んでいた扉のほうがとっくに開いていたという、思いも掛けなかった事態に先を越されるかもしれない。
いうまでもなくこれは危険な賭です。扉のほうもまた依然として開かずの扉かもしれないのですから。けれども窓派も扉派もおたがいに背をそむけあいながら、ことばにおける他者性の発見というプログラム自体については、たえてないほど両者が接近しているのかもしれません。そこにジャンルを越えて眞鍋さんの句集が受賞された契機もあるのではありますまいか。
句集の「後記」において眞鍋さんは、発明的装置としての季語や歌枕の根源的意味を説いておられます。「これを要するに、『雪女』や『鎌鼬』や『竈猫』などによって代表される季語は、字義通り、われわれの蜉蝣《ふゆう》の生命を長大な時空に向かって解き放つための卓抜な発明であり、昇華装置にほかならない」。
ことばを「蜉蝣の生命」たる自我の閉空間に固定し限定する、近代の詩法をより大きな関連へと取り戻すこと。眞鍋さんはこの「長大な時空」を超自然をも含むような「自然」といっておられますが、ここでは私流に、かりに「それ」と名づけて話を続けたいと思います。
それがわれわれを在らしめているので、われわれが存在するためにそれが消えてしまうという関係を取り結ぶべきではなかったそれ、ドイツ語でならさしずめ非人称の es と呼ばれているようなそれは、宇宙論的ひろがりにおいてはすでにわれわれにじかに捉えられなくなっているとしても、たとえば子供がそこらに転がっている柿の蔕や落ちている縄を指して「それ」というとき、それが見えない領域から忽然として現れてくるかもしれない。すでに大きな関連をうしない、大きな関連から見捨てられもしたわれわれは、ときとしてそんな開け胡麻の呪文を夢見ます。
しかもそういう大きなそれは、季語のような一見したところの無意味、ささやかな日常的事物やその組み合わせたる民俗的超自然として、なにげなくそこらに転がっていないともかぎらない。これが、突き出した釘やドラム缶のような一見ささやかにも小さい断片のそれから、包括的なそれを喚びだし在らしめる措置として、眞鍋さんの場合にたまたま俳句が選ばれた消息ではなかろうかと愚考いたします。
それ以上に俳句としてどう、というようなことを申し上げる器量は私にはございません。そういう私にも理解できるかぎりでの短詩型文学を楽しませて頂いた、というかぎりでのお話をいたしました。これをもちましてお祝いのことばに替えたいと思います。
付記・以上は一九九二年十一月十二日、眞鍋呉夫句集『雪女』の歴程賞授賞式の席上読み上げた祝辞に若干の加筆を施したものである。
【全句集】
ALL REVIEWSをフォローする