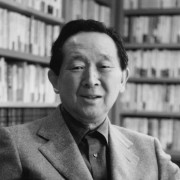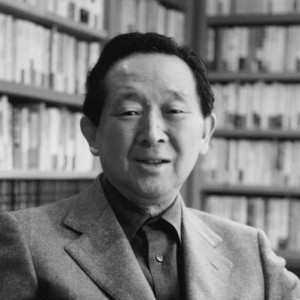書評
『黄色いリボン』(幻冬舎)
主人公風子はボストン大学で勉強している。街には湾岸戦争に出征したアメリカ軍将兵の無事を祈る黄色いリボンがここかしこに結びつけられ、揺れている。テレビのスイッチを入れると、イラクのフセイン大統領とアメリカのブッシュ大統領の、正義と国益を主張し合う声明合戦、「砂漠の嵐作戦」と呼ばれる多国籍軍の展開が、迫力のある〝実況中継〟よろしく映し出される。
恋人の邦夫も風子も試験勉強中だが、アメリカ社会の戦争への熱狂のなかでシラケてゆくばかりだ。黄色いリボンは次第に風子たちにとって一種の強迫観念の象徴になってゆく。そうなればなるほど、風子は人間はニュースなんか知らなくても生きてゆけるというようなことを考える。
彼女はいつかボストンで一番高いハンコックタワーに昇ってみようと思う。それはこの町に馴染みアメリカ社会に同化する儀式のような位置を風子のなかで占めている。しかし、その機会はなかなか来ない。理由は彼女がその儀式の執行に熱心ではないからである。邦夫は法律を勉強していて、明るく無邪気な青年である。それだけ凡庸で、今日の平均的な日本の若者に描かれている。彼は新聞を見ないと不安になり、それでいて戦争の光景を「すげえや」と感動しながら見ることが出来る鈍さを備えている。その鈍さの特権を働かせて、今日の国際関係などに敏感に反応することなく生きることができる。だが、風子とのこうした〝体質〟の違いは二人の恋愛を壊しはしない。それは風子が、自分は何なのかまだ分っていないからのようでもあり、むきになって自己のアイデンティティを求めようとはしないからでもあるらしい。
登場人物たちの相互の、また社会との関係の不安定なズレは当り前のことに思われている。休暇が終って久し振りに行ったキャンパスは明るさに満ちている。外側から見たら、ボストンの美しい季節である。だが風子は「おかしい。腑におちない。もっと〝戦争〟を感じたい」、と苛(いら)立ち「ここはいったいどこなんだろう」と思い惑う。
風子は邦夫と同棲するようになるが、性的な関係も、人間と人間のあいだの、また社会とのあいだの不安定さを解消してはくれない。性のまじわりは愛の新しい発展としての喜び、関係の深まりを持って来てはくれない。二人の、〝交際〟は、留学が終わったら何となく別れてしまうことを前提としているような、それでいて真面目な淡々とした〝交際〟なのだ。二人にとって、別れる別れないは基本問題ではない。留学生になってはじめて分った孤立感、自分がまだ社会のなかに入りきれていないもどかしさ、男女の愛さえもが疎外感を超える力を与えてくれないこと、自分には進んでゆく目標がないという想念を逆に強めてしまうことが問題なのだ。「ふたりはただ歩いていた。何か気を引くもの、夢中になれるものを探したけれど―」
彼らの大晦日から新年にかけての街への遠征は徒労に終る。
この作品は有吉玉青の最初の小説であり、母・有吉佐和子のことを書いた『身がわり』、ニューヨーク滞在の経験をまとめた『ニューヨーク空間』に続く三冊目の著作である。
天性の、と言う他はない文学的資質は、この処女小説にも随所に顔を覗かせている。「文学とは何か」という説明しにくい存在を著者は皮膚感覚的に掴んでいると言っていいだろう。それは放っておくと不幸に繋(つな)がるから、書かなければならないのだが、現実の奥深くへと分け入り、感覚を文字によって表現してゆくのには、小説という形式がいいのか、エッセイと呼ばれる様式が適しているのか。それは題材と作者の資質によることだろう。模索しつつ歩いている著者の姿がこの作品にもよく現れていて好感の持てる処女小説であるが、それにしても現代の若者の絶望は何故このように明るいのであろうか。
恋人の邦夫も風子も試験勉強中だが、アメリカ社会の戦争への熱狂のなかでシラケてゆくばかりだ。黄色いリボンは次第に風子たちにとって一種の強迫観念の象徴になってゆく。そうなればなるほど、風子は人間はニュースなんか知らなくても生きてゆけるというようなことを考える。
彼女はいつかボストンで一番高いハンコックタワーに昇ってみようと思う。それはこの町に馴染みアメリカ社会に同化する儀式のような位置を風子のなかで占めている。しかし、その機会はなかなか来ない。理由は彼女がその儀式の執行に熱心ではないからである。邦夫は法律を勉強していて、明るく無邪気な青年である。それだけ凡庸で、今日の平均的な日本の若者に描かれている。彼は新聞を見ないと不安になり、それでいて戦争の光景を「すげえや」と感動しながら見ることが出来る鈍さを備えている。その鈍さの特権を働かせて、今日の国際関係などに敏感に反応することなく生きることができる。だが、風子とのこうした〝体質〟の違いは二人の恋愛を壊しはしない。それは風子が、自分は何なのかまだ分っていないからのようでもあり、むきになって自己のアイデンティティを求めようとはしないからでもあるらしい。
登場人物たちの相互の、また社会との関係の不安定なズレは当り前のことに思われている。休暇が終って久し振りに行ったキャンパスは明るさに満ちている。外側から見たら、ボストンの美しい季節である。だが風子は「おかしい。腑におちない。もっと〝戦争〟を感じたい」、と苛(いら)立ち「ここはいったいどこなんだろう」と思い惑う。
風子は邦夫と同棲するようになるが、性的な関係も、人間と人間のあいだの、また社会とのあいだの不安定さを解消してはくれない。性のまじわりは愛の新しい発展としての喜び、関係の深まりを持って来てはくれない。二人の、〝交際〟は、留学が終わったら何となく別れてしまうことを前提としているような、それでいて真面目な淡々とした〝交際〟なのだ。二人にとって、別れる別れないは基本問題ではない。留学生になってはじめて分った孤立感、自分がまだ社会のなかに入りきれていないもどかしさ、男女の愛さえもが疎外感を超える力を与えてくれないこと、自分には進んでゆく目標がないという想念を逆に強めてしまうことが問題なのだ。「ふたりはただ歩いていた。何か気を引くもの、夢中になれるものを探したけれど―」
彼らの大晦日から新年にかけての街への遠征は徒労に終る。
この作品は有吉玉青の最初の小説であり、母・有吉佐和子のことを書いた『身がわり』、ニューヨーク滞在の経験をまとめた『ニューヨーク空間』に続く三冊目の著作である。
天性の、と言う他はない文学的資質は、この処女小説にも随所に顔を覗かせている。「文学とは何か」という説明しにくい存在を著者は皮膚感覚的に掴んでいると言っていいだろう。それは放っておくと不幸に繋(つな)がるから、書かなければならないのだが、現実の奥深くへと分け入り、感覚を文字によって表現してゆくのには、小説という形式がいいのか、エッセイと呼ばれる様式が適しているのか。それは題材と作者の資質によることだろう。模索しつつ歩いている著者の姿がこの作品にもよく現れていて好感の持てる処女小説であるが、それにしても現代の若者の絶望は何故このように明るいのであろうか。
週刊文春 1994年11月17日
昭和34年(1959年)創刊の総合週刊誌「週刊文春」の紹介サイトです。最新号やバックナンバーから、いくつか記事を掲載していきます。各号の目次や定期購読のご案内も掲載しています。
ALL REVIEWSをフォローする