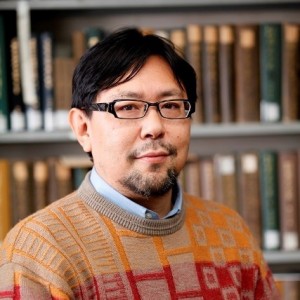書評
『戦国大名の兵粮事情』(吉川弘文館)
武士たちはいかに食べ戦ったか
戦争は戦術・戦略・兵站の3要素から成る。戦術とは戦場でどういう作戦をとるかであり、戦略とは政治や外交を含む幅広い視野のこと。対して兵站とは物資(武器や馬など)の補給であるが、その根本は食料である。「腹が減っては戦はできない」のだ。戦国の合戦を語るとき、私たちはつい戦術に目を奪われる。桶狭間の戦いは奇襲だったか否か、長篠の戦いの鉄砲三段撃ちは本当か、等々。戦略が語られることは少なく、足利義昭の信長包囲網などが辛うじて当てはまるのみ。兵站となると、もう具体的な様相がまるで分からない。これではいけない。「戦争のプロは兵站を語り、戦争の素人は戦略を語る」(石津朋之氏)というではないか。
戦国大名はどのようにして、どれくらい、兵粮を調達していたか。それを知りたければ本書を読もう。そんな感じで書評すればいいかな、と実は思っていた。だが、読み進むうちに、自らの重大な誤りに気がついた。確たる兵站の理論など、戦国時代にはなかった! いや、それが十分に成熟していないことこそが戦国の合戦、さらには戦国という社会の特色なのだ。
兵粮は時に食料としてのコメそのものであり、時に経済をまわす貨幣、カネであった。大名は戦に勝つためにコメとしての兵粮を備蓄し、富を得るためにカネとしての兵粮を流通させる。それは相反する行動だが、状況に追われてかかる矛盾を解決する余裕を与えられずに、兵粮に対処せざるを得なかった。それが戦国大名という権力であった。
著者は小田原・北条氏を中心とする様々な史料を深く読みこみ、鋭く分析することにより、従来ほとんど語られてこなかった兵粮事情の具体的なありようをみごとに復元してみせる。たいへんな労作である。戦国の軍隊はいかに食べ、戦ったか。「イメージとしての戦国」に飽き足りぬ方々に、おすすめの一冊である。
朝日新聞 2016年3月13日
朝日新聞デジタルは朝日新聞のニュースサイトです。政治、経済、社会、国際、スポーツ、カルチャー、サイエンスなどの速報ニュースに加え、教育、医療、環境、ファッション、車などの話題や写真も。2012年にアサヒ・コムからブランド名を変更しました。
ALL REVIEWSをフォローする