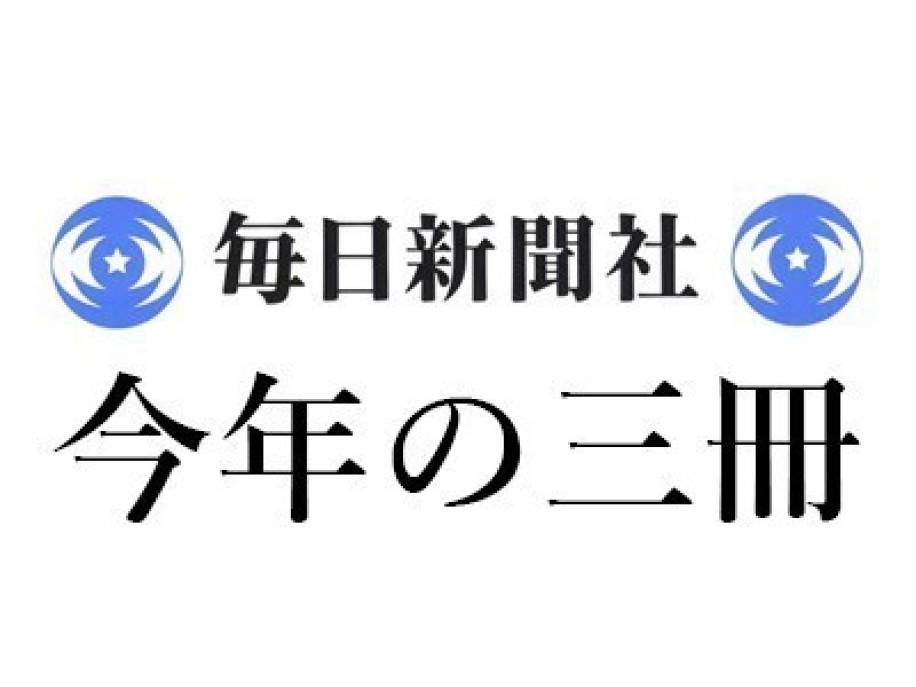解説
『山の暮れに』(集英社)
「そういえば、あの亀はどうしたやろ」と、ふと思い出された。あれは、私が幼稚園にあがる前のことだった。家の玄関のところに、一匹の大きな亀が、突然あらわれた。あらわれた、といっても、あらわれるところを目撃した家族はいない。父が帰ってきたので、母と私が出迎えた。そして三人で「あっ」。珍客は、もうずっと昔からそこにいますという風情である。でんと落ち着いて、身動きもしない。
当時家のまわりは、一面の蓮畑だった。その一角を埋め立てて、住宅が建てられていた。
だから、亀の散歩する姿は珍しくない。が、玄関まで入りこんでしまったのは、そいつだけだった。
「亀さんが来た、亀さんが来た!」と私は大騒ぎ。「なんだか、乾いているみたいね」と母は盥に水を入れて、そこに亀を放ってやった。夕食後、のぞきに行くと、石のように動かない。でも、じーっと見ていると、これはこれでなんだか愛嬌がある。私自身、どてっとして動きの鈍い子どもだったから、親しみを覚えたのかもしれない。
そして翌日。友だちと遊んで帰るなり、盥をのぞいた。
「あれぇ、亀さん、いなくなっちゃった」
出かけるときにはいたはずなのに、あとかたもなく消えていた。
「あら、気がつかなかったわ。きっと、自分のおうちへ帰ったのよ。家族のみんなを心配させちゃいけないでしょ」と母。それもそうだ。「寂しい」と思うほどの愛着をわかせる間も与えずに、その亀は、ふっとやって来て、さっといなくなってしまった。だから、思い出したのは二十何年ぶりのこと。ためしに両親に聞いてみたら、二人ともよく覚えていた。
「ああ、あの亀ね。盥は、あなたが赤ちゃんのときに行水で使っていたのを、久しぶりに出してきたのよ」
「うんうん、かなり大きな亀だった。万智の手の三倍はあったな。今はあのあたりも全部埋め立ててしまったらしいから、亀なんて見られないだろうなあ」
亀のことがきっかけで、久しぶりに当時の話に花が咲く。蓮畑も懐かしい。雨が降れば大きい葉っぱを引き抜いて、傘がわりにして遊んだ。裏の空き地で父と凧あげをしたことや、ざりがにをたくさん取ってきて母をこわがらせたことなどが、記憶のスクリーンに映し出されてくる。
それもこれも『山の暮れに』を読んだからだ。自然や生き物とふれあった思い出。それはたぶん、誰の心のなかにもあるものだろう。この本のなかで、藤堂伊作が達之に伝えるほどの、豊かな内容ではないにしても。亀のことや蓮畑のことを思い出して、いつになく私はやさしい気分になっていた。
『山の暮れに』は、まず自然への慕情を呼び覚ます。それは次に、読者の心に種を蒔くための準備でもあるようだ。種というのは、自然への意志であり愛情である。
あわただしい都会の暮らしのなかで、すっかり固い土となってしまった人の心には、いきなり種を蒔いても芽は出ない。慕情でしっとりほぐされたところに、著者は巧みに種を蒔いてゆくのだ。
私自身、都会から村へ移り住んだ藤堂伊作のことを、はじめは「ただの郷愁じいさん」
と思っていた。それが、彼とともに自然を体験してゆくなかで、心の土が柔らかくなり、いつのまにか彼の愚痴のようなつぶやきにさえ共感し、応援したい気持ちになっていた。
生き物、樹木、そして土。
では『山の暮れに』は、自然への思いだけを描いているかというと、決してそうではない。村で一人暮らしを始めた伊作にでさえ、人間関係の糸は無縁ではない。そして登場人物は、それぞれ現代の日本を反映している。離婚、不倫、あるいは非婚。在日韓国人の問題、働く母親、子どもの孤独。表現に夢を託す若者たち、いっぽうでフィリピンから来た女性たち。
そんな現代の人間群像があるからこそ、この小説に描かれた自然は、ほんものとして読者の胸に迫ってくるのだと思う。それは、かつて確かにあった自然であり、げんに失われつつある自然である。
かつて確かにあり、げんに失われつつあるもう一つのものは、村感覚のあたたかい人間関係だろう。正月の注連(しめ)飾りを、近隣の人のために伊作が作る場面など、実に印象深い。
そして著者は、ただ失われてゆくものを感傷的に書きとめているのではない。そこには達之という少年が配されている。バトンを渡される存在としての少年だ。伊作に教えられて、ぎこちない手つきで縄をなう姿は、たよりないけれど希望を感じさせてくれる。
思えば女郎蜘蛛を飼うことも蛍を育てることも、達之に伝えるというかたちだから、やさしく嚙み砕かれて、実体験のない者にまでわかりやすいのだろう。
要所要所に出てくる、伊作から孫の達之へ宛てられた手紙は、象徴的だ。自然も人間もひっくるめて、伊作から孫の達之へ伝えたい思いというものが、この小説なのだと思う。
つまりそれは、著者から読者への手紙でもある。物ばかりが豊かな時代に育ってしまった世代への、手紙である。その手紙には、豊かな自然、豊かな人間関係が、たっぷりと記されている。加えて未来へ向けての祈りのようなものが、感じられる。達之の存在は、未来そのものと言ってもいいだろう。
正直言って、伊作のことを「郷愁じいさん」と思っていた段階では、私は「これはかなり年配の人向きの小説やなあ」と思った。なんせ主人公は、リタイアした老人である。小説がはじまったかと思うと、骨壼を作りはじめたりするのである。
が、すっかり伊作ファンとなった今では、この小説は若い人にこそ向けて書かれたものなのだ、と思うようになった。もちろん年配のかたが読まれれば、私たち以上の強い共感を持たれることだろう。けれどたぶん、同年代の人よりも、より若い世代に、勧めたくなるのではないかと思う。
著者のほとんど孫の世代である私が「解説」という大役を仰せつかったのも、だからそう驚くことではないのかもしれない(はじめは、ものすごく驚いた)。なんというか、作品が呼びよせてくれたのだなあ、という気がする。
聞くところによると、『山の暮れに』を新聞連載中、著者は北京で天安門事件に出会ったそうだ。しかも旅行団の団長として、大変な苦労をされたとのこと。小説には直接の影響は見られないが、執筆の時期にそういうことがあったと知ると、感慨深い。私たち日本の若者にとっても、まことにショッキングな事件だった。
その話は、私のある記憶へとつながってゆく。福井県の高校に通っていたころ、水上勉氏の講演を聴きに行った。県民会館で催されたその会の最後のところで、氏は次のように語った。
「私は、この講演を終えて帰ったら、今書いている小説の最後の部分を書きあげます。
『金閣炎上』という小説です。それが本になって、みなさんの手に届いたら、こう思っていただいてまちがいありません。あの日の話のあと、この小説の最後の部分は書かれたのだと。これも縁ということのひとつでしょう」
後に『金閣炎上』を手にしたときの感慨は、今でも忘れられない。
縁ということで言えば、十四歳のとき、大阪から福井に移り住んだことが、私と水上文学との出会いだった。
名古屋の叔父が「福井県に住むことになったんだって?だったらぜひ、水上勉さんの作品を読まなきゃね」と勧めてくれたのである。彼は昔からのファンだったらしい。はじめの一冊として、叔父はすぐに『霧と影』を送ってくれた。福井県の若狭が、重要な舞台として登場するその小説を、私は一気に読んでしまった。
それから『雁の寺』『越前竹人形』……と、続けて読んでいった。
「越前(福井県)武生市から南条山地に向って、日野川の支流をのぼりつめた山奥に、竹神という小さな部落があった。」という一文が、『越前竹人形』の冒頭である。私は、日野川の近くに住み、武生第一中学校に通っていた。
【この解説が収録されている書籍】
当時家のまわりは、一面の蓮畑だった。その一角を埋め立てて、住宅が建てられていた。
だから、亀の散歩する姿は珍しくない。が、玄関まで入りこんでしまったのは、そいつだけだった。
「亀さんが来た、亀さんが来た!」と私は大騒ぎ。「なんだか、乾いているみたいね」と母は盥に水を入れて、そこに亀を放ってやった。夕食後、のぞきに行くと、石のように動かない。でも、じーっと見ていると、これはこれでなんだか愛嬌がある。私自身、どてっとして動きの鈍い子どもだったから、親しみを覚えたのかもしれない。
そして翌日。友だちと遊んで帰るなり、盥をのぞいた。
「あれぇ、亀さん、いなくなっちゃった」
出かけるときにはいたはずなのに、あとかたもなく消えていた。
「あら、気がつかなかったわ。きっと、自分のおうちへ帰ったのよ。家族のみんなを心配させちゃいけないでしょ」と母。それもそうだ。「寂しい」と思うほどの愛着をわかせる間も与えずに、その亀は、ふっとやって来て、さっといなくなってしまった。だから、思い出したのは二十何年ぶりのこと。ためしに両親に聞いてみたら、二人ともよく覚えていた。
「ああ、あの亀ね。盥は、あなたが赤ちゃんのときに行水で使っていたのを、久しぶりに出してきたのよ」
「うんうん、かなり大きな亀だった。万智の手の三倍はあったな。今はあのあたりも全部埋め立ててしまったらしいから、亀なんて見られないだろうなあ」
亀のことがきっかけで、久しぶりに当時の話に花が咲く。蓮畑も懐かしい。雨が降れば大きい葉っぱを引き抜いて、傘がわりにして遊んだ。裏の空き地で父と凧あげをしたことや、ざりがにをたくさん取ってきて母をこわがらせたことなどが、記憶のスクリーンに映し出されてくる。
それもこれも『山の暮れに』を読んだからだ。自然や生き物とふれあった思い出。それはたぶん、誰の心のなかにもあるものだろう。この本のなかで、藤堂伊作が達之に伝えるほどの、豊かな内容ではないにしても。亀のことや蓮畑のことを思い出して、いつになく私はやさしい気分になっていた。
『山の暮れに』は、まず自然への慕情を呼び覚ます。それは次に、読者の心に種を蒔くための準備でもあるようだ。種というのは、自然への意志であり愛情である。
あわただしい都会の暮らしのなかで、すっかり固い土となってしまった人の心には、いきなり種を蒔いても芽は出ない。慕情でしっとりほぐされたところに、著者は巧みに種を蒔いてゆくのだ。
私自身、都会から村へ移り住んだ藤堂伊作のことを、はじめは「ただの郷愁じいさん」
と思っていた。それが、彼とともに自然を体験してゆくなかで、心の土が柔らかくなり、いつのまにか彼の愚痴のようなつぶやきにさえ共感し、応援したい気持ちになっていた。
生き物、樹木、そして土。
では『山の暮れに』は、自然への思いだけを描いているかというと、決してそうではない。村で一人暮らしを始めた伊作にでさえ、人間関係の糸は無縁ではない。そして登場人物は、それぞれ現代の日本を反映している。離婚、不倫、あるいは非婚。在日韓国人の問題、働く母親、子どもの孤独。表現に夢を託す若者たち、いっぽうでフィリピンから来た女性たち。
そんな現代の人間群像があるからこそ、この小説に描かれた自然は、ほんものとして読者の胸に迫ってくるのだと思う。それは、かつて確かにあった自然であり、げんに失われつつある自然である。
かつて確かにあり、げんに失われつつあるもう一つのものは、村感覚のあたたかい人間関係だろう。正月の注連(しめ)飾りを、近隣の人のために伊作が作る場面など、実に印象深い。
そして著者は、ただ失われてゆくものを感傷的に書きとめているのではない。そこには達之という少年が配されている。バトンを渡される存在としての少年だ。伊作に教えられて、ぎこちない手つきで縄をなう姿は、たよりないけれど希望を感じさせてくれる。
思えば女郎蜘蛛を飼うことも蛍を育てることも、達之に伝えるというかたちだから、やさしく嚙み砕かれて、実体験のない者にまでわかりやすいのだろう。
要所要所に出てくる、伊作から孫の達之へ宛てられた手紙は、象徴的だ。自然も人間もひっくるめて、伊作から孫の達之へ伝えたい思いというものが、この小説なのだと思う。
つまりそれは、著者から読者への手紙でもある。物ばかりが豊かな時代に育ってしまった世代への、手紙である。その手紙には、豊かな自然、豊かな人間関係が、たっぷりと記されている。加えて未来へ向けての祈りのようなものが、感じられる。達之の存在は、未来そのものと言ってもいいだろう。
正直言って、伊作のことを「郷愁じいさん」と思っていた段階では、私は「これはかなり年配の人向きの小説やなあ」と思った。なんせ主人公は、リタイアした老人である。小説がはじまったかと思うと、骨壼を作りはじめたりするのである。
が、すっかり伊作ファンとなった今では、この小説は若い人にこそ向けて書かれたものなのだ、と思うようになった。もちろん年配のかたが読まれれば、私たち以上の強い共感を持たれることだろう。けれどたぶん、同年代の人よりも、より若い世代に、勧めたくなるのではないかと思う。
著者のほとんど孫の世代である私が「解説」という大役を仰せつかったのも、だからそう驚くことではないのかもしれない(はじめは、ものすごく驚いた)。なんというか、作品が呼びよせてくれたのだなあ、という気がする。
聞くところによると、『山の暮れに』を新聞連載中、著者は北京で天安門事件に出会ったそうだ。しかも旅行団の団長として、大変な苦労をされたとのこと。小説には直接の影響は見られないが、執筆の時期にそういうことがあったと知ると、感慨深い。私たち日本の若者にとっても、まことにショッキングな事件だった。
その話は、私のある記憶へとつながってゆく。福井県の高校に通っていたころ、水上勉氏の講演を聴きに行った。県民会館で催されたその会の最後のところで、氏は次のように語った。
「私は、この講演を終えて帰ったら、今書いている小説の最後の部分を書きあげます。
『金閣炎上』という小説です。それが本になって、みなさんの手に届いたら、こう思っていただいてまちがいありません。あの日の話のあと、この小説の最後の部分は書かれたのだと。これも縁ということのひとつでしょう」
後に『金閣炎上』を手にしたときの感慨は、今でも忘れられない。
縁ということで言えば、十四歳のとき、大阪から福井に移り住んだことが、私と水上文学との出会いだった。
名古屋の叔父が「福井県に住むことになったんだって?だったらぜひ、水上勉さんの作品を読まなきゃね」と勧めてくれたのである。彼は昔からのファンだったらしい。はじめの一冊として、叔父はすぐに『霧と影』を送ってくれた。福井県の若狭が、重要な舞台として登場するその小説を、私は一気に読んでしまった。
それから『雁の寺』『越前竹人形』……と、続けて読んでいった。
「越前(福井県)武生市から南条山地に向って、日野川の支流をのぼりつめた山奥に、竹神という小さな部落があった。」という一文が、『越前竹人形』の冒頭である。私は、日野川の近くに住み、武生第一中学校に通っていた。
【この解説が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする