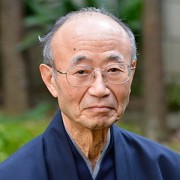書評
『荻生徂徠―江戸のドン・キホーテ』(中央公論社)
「尋常ならざる」学者の肖像
荻生徂徠は江戸中期に活躍した学者。三十一歳で柳沢吉保に召し抱えられ、トントン拍子に出世して八代将軍吉宗の政治顧問として縦横の才を振るった。誰でも知っていることだ。以後かれの名声は神話化されるほどに喧伝(けんでん)されたが、明治になってとたんに下落した。なぜなら徂徠の言動には、朝廷を抑え幕府を持ちあげる風が目立ったからだ。著者の言葉でいうと、かれは徳川絶対王権の主張者だったからということになる。だがこの徂徠のラジカリズムは実を結ぶことはなかった。「江戸のドン・キホーテ」と呼ばれる所以(ゆえん)だ。
なるほど、徂徠の学問はたしかに尋常ではない。たとえばその徹底した中国趣味。中国の古典を中国語(唐音、唐話)で読み、考え、話そうとした。いわゆる中国崇拝だが、日本近代における西欧崇拝の思想原型をそこに見る思いがする。
つぎに、かれの学問方法の骨格をなす歴史的文献学の新鮮さ。それは古文辞の学と称されたが、たとえば「論語」を解釈するのに、孔子がどういう状況のもとにどういうつもりで語ったかを、個別具体的に明らかにしようとした。「聖人」の言行を規範的に考えるのではなく、ものを「制作」する人間の主体的行為ととらえようとした。同時代のライバル、伊藤仁斎の学風とは対極に立つ徂徠の肖像が、そこからは浮かびあがってくるだろう。
さて、そこまではまず異論のないところだ。本書の目を見張るような特色は、右にあげた論点を仏教論理学やメタ言語論を借りて腑分(ふわ)けし、他方、享保改革期のかれの経済政策にふれて最新の貨幣理論をひっさげて論を立てている点であろう。本書のテーマが思想史的視角からの徂徠論であるところからすれば、当然の目くばりともいえるが、しかしいささか繁に過ぎる面がないではない。私などはむしろ、高弟、太宰春台の次のような言葉が身にしみる。「徂徠先生は、日ごろ身体を大切にされたけれども、余りに頭を使いすぎで病死せられた……」
ALL REVIEWSをフォローする