書評
『鶴屋南北』(吉川弘文館)
江戸歌舞伎の見事な抽出
2019年の学術書の賞レースを独走したのは、古井戸秀夫著『評伝 鶴屋南北』(白水社)だった。「東海道四谷怪談」で知られる歌舞伎作者をめぐる上下2冊、2段組で1600ページ超の大著で、芸術選奨文部科学大臣賞、読売文学賞、角川源義賞、日本演劇学会河竹賞の4冠に輝き、芸術・文学・学術・演劇の全方位から高い評価を得た。その著者が、並行して書き進めていたのが本書である。いわば前著『評伝』は「鶴屋南北とその時代」というべき列伝体の群像劇。本書は編年体で、南北その人だけの歩みを実証的かつ簡潔にたどる。徹底した資料博捜により、『評伝』刊行後の新たな資料も活用され、出自についての諸説や、「文盲」を自称したことをめぐる臆測など、時流をにらんだ従来の思いつきは冷静に退けられている。今後、本書が鶴屋南北伝の出発点となることは疑いない。
江戸の歌舞伎台本は、18世紀後半までは残存率が悪い。火事の多い江戸では、劇場と共に台本も焼失した可能性が高いのである。その資料的な限界をくぐり抜け、出勤記録や評判から合作制の中での分担を推定、若き南北の活動が活写される。
緻密な段取りを得意とする金井三笑(さんしょう)、華やかな趣向に富んだ桜田治助(じすけ)、上方から江戸に下って新風を巻き起こす並木五瓶(ごへい)ら、師匠や先輩に学びつつ個性的な作風を築き上げていく南北。江戸歌舞伎の作者の系譜が手に取るように分かる。
台本が現存する19世紀の名作続出時代に入ると、作品紹介は独自の形を取る。起承転結に忠実で退屈なあらすじ説明とは無縁の境地。その芝居のどこが面白いのか、どんなせりふが魅力的なのか、急所だけをズバズバと引用してゆく。論理的な帰結よりも、趣向の新鮮さを競う江戸歌舞伎らしさの見事な抽出であり、史上最も多くの歌舞伎台本に目を通した一人である著者の独壇場でもある。
歌舞伎好きにはもちろん、江戸文化の調査考証のお手本としても格好の一冊である。
[書き手] 児玉 竜一(こだま りゅういち)早稲田大学教授
初出メディア
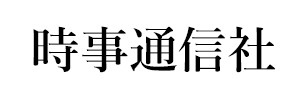
時事通信社 2020年7月
ALL REVIEWSをフォローする





























