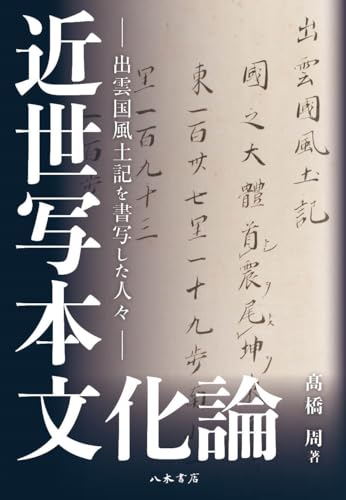書評
『陶庵夢憶』(岩波書店)
隠遁が生みだした文章
今どきはやらない言葉に「隠遁」がある。言葉がすたれるのは、その中身がからっぽになったからだ。「隠遁」はもちろん中国から来た言葉だ。隠遁する、とはいったいどこからどこに、なんのため隠れるのか。隠遁者の伝記がはじめて書きつけられたのは、『後漢書』の「逸民列伝」という。それによると、隠遁には六種ある。一、道の行われない世の中では仕えず、隠れてその志を求める。二、他の土地に避難して、己を育てその道を全うする。三、己を静かにして以てその欲望を鎮める。四、危うきを去って以てその安きを図る。五、俗を汚らわしとして、その節操を立てる。六、世の中の万事を否定して、その清らかさをはげしくする。
本家本元のそれは、日本の無常観、世捨人ふう隠遁とはだいぶ違って、たえず現実の政治世界を意識し、それに拮抗(きっこう)して選択されている。もちろん日本でそのような隠遁がなかったわけではない。例えば戦後の反体制運動に関わった人たちの一人一人にはどこか似たような隠遁志向がなかっただろうか。おおざっぱな勘でいうと、僕らの周辺から「隠遁」がその中身を失ったのは、一九七二年の連合赤軍事件を境にしてだ、という気がする。うまく言えないが、誰もがなんとなく、あれで変わった、そう感じているのではないだろうか。
ところが、僕は近ごろ急にこの「隠遁」に思いをこらすようになった。中国の友人たちとの交際を深めるにつれ、彼らは今なお、先の六つの隠遁活動の渦中にあることが切々と身に感じられるようになったのだ。
体制に抗して生きる、あるいは体制を無視して生きる。これが日本ではほとんど無意味となっているのに較べ、中国では今なお政治的にも文学的にも最も深刻なテーマなのだ。恋ひとつ成就させるにも彼らは二千年近い隠遁の系譜の中で生死を賭ける。『古井戸』の作者鄭義は、中国三千年の歴史の中で、たとえどのように苛酷な圧制者のもとにあっても、かつて農民は惨い王(ワン)地主のところから、それほど惨くない張(チャン)地主のところへ移る自由、知識人には隠遁の自由があったが、現在の体制にはその自由さえない、と書いている。しかし、それこそ、より苛烈な様々な隠遁の方法が、地下潜行、海外逃亡といったかたちで追求されている証左だ。日本人である僕はいったい何に抗して、何を無視しようとして隠遁にあこがれるのか、わからない。
明代末の大奇人・大文人で、最大の隠遁者・張岱(ちょうたい)の代表作『陶庵夢憶』を読む。
張岱は三万冊の書物と十指にあまる庭園と六つの劇団を所有していた。美女、美少年、駿馬、花火、みかん、茶に狂った。五十歳の時、明が滅び、三万冊の蔵書、豪邸、庭園を焼かれ、逃れて、家族を連れ、欠けた硯一個を持って山に入った。
隠遁が生みだした文章というものが、僕を陶然とさせる。例えば、「砎園(かいえん)は、水によって園全体が盤拠(ばんきょ)されている。しかも水を十二分に活用していながら、たくみに配置してあるので、一見水は一つもないかのようである」ではじまり、「砎園はよく水を用いてついに水の力を得た、と人はほめたたえている」で終わる。かつて張家が所有した庭園についての回想「砎園」などは、文中に盤拠する水のあふれ出る趣がある。
彼はライフワーク、明史『石匱(せっき)書』二百二十一巻を五十年かけて完成させた。没年は六十九歳、七十余歳、八十八歳、九十三歳と諸説があって不明。隠遁者の隠遁者たるゆえんか。最後に肝に銘ずべきこと。隠遁者は生活し、仕事をしている。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする