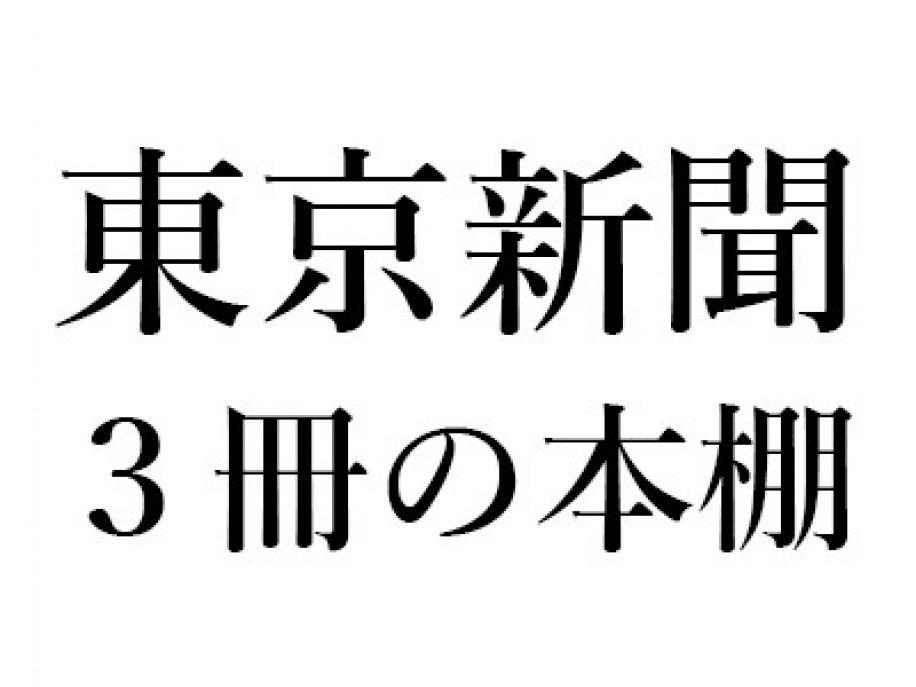書評
『バラと痛恨の日々―有馬稲子自伝』(中央公論社)
女優のなかの女優
オナラをしたんです、プロポーズのときに彼は……、それを好もしく思ってプロポーズを受けた、と中村錦之助との婚約を発表した記者会見でそのひとはいった。と、僕は強烈に覚えている。僕の記憶はあてになるだろうか。昭和三十年代がちょうど十代のはじめだった一映画少年には、山本富士子でも岸恵子でもなく、なぜかそのひとが女優のなかの女優だった。
たとえば「彼岸花」。婚期を迎えた娘と父親の心理の綾を描ききった名作中の名作だが、父親の微妙な心の揺れや小津作品ということに注意が向くのはのちのことだ。そのひとの一挙手一投足にただ目をこらした。見てはならないものを見ている心地で。
スクリーン上の女優の姿は、中空に浮かぶ幻ではなく、眼前で生々しく動く。むしろ現実の女性のほうがイメージをまぶされて幻めいた存在になる。思春期に特有の転倒だが、思春期はもともと自分の体だけがあって、他人に体があるなんて思ってもみない。
オナラ発言は少年の目を開かせた。そうか、女というのはこんなふうに口説きおとすものなのか。妙な開眼の仕方をしたせいで、のちのち深刻かつコッケイにつまずきつづけるのだが。
錦之助と出会ったころは、長いあいだつづいていた妻子ある男性との関係が先行きのないものになっていた。「有馬稲子自伝」と副題のある『バラと痛恨の日々』は、一章を使ってその苦しい日々の迷いと決断を腹蔵なく語る。
はじめて知ることなのにさして驚かずに読めたのは、面と向かって聞く打ち明け話がショックにならないのと同じ事情なのだろう。邪念を発動させるのは伝聞やゴシップだ。その意味でも、この自伝の一読をおすすめする。ここにあるのは、一女性の率直な心のヒレキだから。
梨園の御曹司との結婚生活は数年で破綻し、再婚の相手ともやがて別れる。離婚のたびに彼女はすっからかんになる。私って男運がないんだ、という調子で淡々と綴られているが、やはり書くのはつらかっただろう。
錦之助と過ごした京都鳴滝の家の庭を、離婚後三年ほどして訪ねたときのこと。
私は庭へ入るなり呆然と立ち尽くした。言葉も出なかった。私が植えたスタンダードのバラが、まるでしだれ桜のように、枝も折れんばかりにたわわに咲き乱れているではないか。……このバラが、一、二輪しかつぼみをつけていない頃に、この家を手放したのだ。
……私は、今日まで、たくさんの美しい物を失ってきた。バラも家も、美しい絵画も、師も友も、役も、愛しい人も、美しさも……。
嘆きは嘆きとして、仕事運には恵まれた。タカラヅカ、映画、商業演劇と遍歴し、そのいずれの世界でもスターだった。
スター女優なのに、彼女はことごとに自分の演技の未熟を書いている。未熟を痛感して、一からやり直そうと民芸に入ったこともある。越境入学の成果がどんなものだったかは素人にはわからないが、とにかく時の流れに素直にしたがって越境的活躍をしてきた成果はめざましい。当たり役の公演はいまでもつづいている。「はなれ瞽女おりん」は六〇〇回。「越前竹人形」は二五〇回。男の自伝ならバラと痛恨の、ではなく、バラと痛快の、とするところだ。
彼女のいまの住まいにはバラが咲いている。だがそれだけでは足りない。もう一度人に愛されたい、愛したい、という。大丈夫。腹わたまでさらけだしたグラス・フィッシュみたいないい女を、いい男がほうっておくわけがない。
【この書評が収録されている書籍】
ALL REVIEWSをフォローする