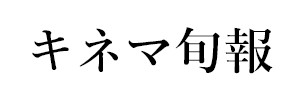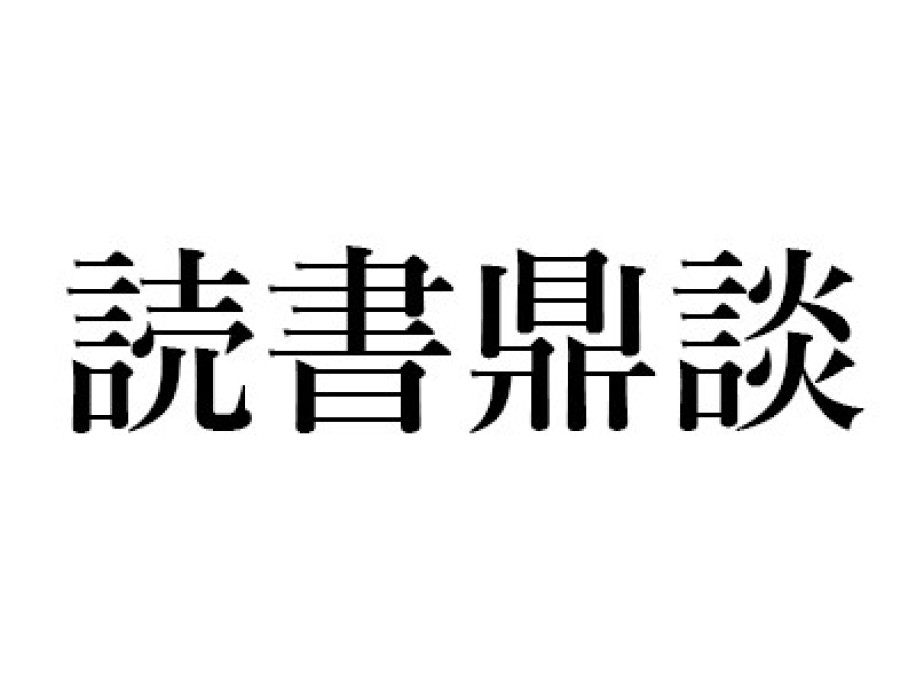書評
『影の美学―日本映画と照明―』(名古屋大学出版会)
照明が創り出す「影」の日本映画史
「日本映画の父」マキノ省三が言い始めた「一ヌケ」、その「明るさ」の希求は「明るく楽しい松竹映画」に引き継がれ、松竹の支配的モードが戦前の日本における映画製作のスタンダードになった。1920年代後半になると、刀の閃光を強調するローキーの時代劇が台頭する。その挑戦に松竹は、ハリウッドの照明テクニックに日本の歌舞伎のスタイルを融合させ、フラットで「明るい」照明と合理的スターシステムでビジネスを安定化させた。こうしたその地域固有(ヴァナキュラー)のモダニズムの潮流に登場したのが長谷川一夫だ(当初の名は林長二郎)。多くの映画ファンは、彼が長きにわたって映画史にその名を轟かせた大スターであることは知っている。だが、その甘美な艶かしさが独創的な照明の技術に支えられていることを知る者は少ない。「お延ばし」や「流し目」、銀幕の彼のイメージは、時代劇の刀の煌めきを凌駕する刺激(セックス・アピール)で女性ファンを虜にしてゆく。やがて東宝へ移籍すると、1930年代後半から現れた新たなトレンド「影の美学」と出会うことになる。
過酷な戦時下、日本はハリウッドを羨望しながら「影」を国家主義的な言説と結びつけ、技術で圧倒するアメリカに対峙する。それを「日本の美」と名指すことによって「影」の日本映画を救済しようとしたのだ。終章では、四章まで概観した作り手の歴史を再び生きるかのように配置された名カメラマン・宮川一夫の撮影美学が論じられる。学術書には珍しく面白い構成である。
本書は日本映画史に「影の美学」がいかに登場し、なぜ必要とされたのか、その複雑に絡まりあった歴史・政治・文化的背景を解き明かしていく。いわば照明の光/影から日本映画史を捉えなおす果敢な試みだ。筆者は作家主義的な研究の限界を指摘し、製作プロセスや歴史的文脈を重視しながら作り手たちの映画史を描き直す。特に長谷川一夫と宮川一夫を論じた第二章と終章は抜群に面白く、不可視だった映画史の一端が鮮明に照らされる。換言すれば、照明の映画史であると同時に優れた長谷川一夫論/宮川一夫論にもなっている。ライティングという切り口で映画史が豊かに、重層的に浮かび上がるのを実感してほしい。映画という芸術の奥深さを痛感すること間違いない。
[書き手]北村匡平(映画研究者)
キネマ旬報 2019年10月下旬号
創刊100周年映画専門誌「キネマ旬報」による映画専門サイト。最新映画紹介や俳優、監督といった数々の映画人へインタビューなど、本物志向の方のための映画情報サイト.
ALL REVIEWSをフォローする