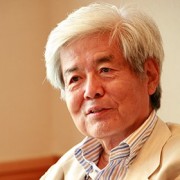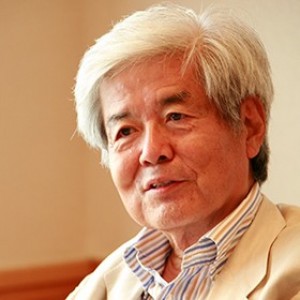書評
『患者の話は医師にどう聞こえるのか』(みすず書房)
あますところなく聞く大切さ
著者は米国最古の公立病院とされるベルビュー病院勤務で、特定分野の専門医ではなく、プライマリー・ケアにかかわる女医で、本書は医師と患者間の話し合いに長年にわたって強い関心を持ち続けた結果をまとめた研究である。とはいえ、ふつうなら統計的に行われる社会学的な研究ではなく、その種の研究は引用されているだけで、著者自身が直接にかかわった患者さんたちの印象的なエピソードが、いわば文学的に記されている。その点が一般の読者にとっても興味深く、読みやすいであろう。
本書のタイトルは逆転してもいいわけで、それなら医師の話は患者にどう聞こえるか、ということになる。医師がとくに苦労するのは、暗いニュースを伝える時で、こうした問題は、具体的にさまざまな状況を考慮すれば、医師―患者関係にとどまらず、人間―人と人との間―の一般的なコミュニケーションの問題に拡張できるはずである。つまり親と子、教師と生徒、上司と部下というような関係である。
米国は日本と違って実に多様な文化的背景を持った人々の集まりだから、医師と患者の組み合わせも多種多様になる。近年日本ではOD(オープン・ダイアローグ)が行われ、その効果が言われている(斎藤環、與那覇潤著『心を病んだらいけないの?―うつ病社会の処方箋―』新潮選書)。
これは医師、患者、看護師など、関係者が集まって、全体で話し合う場を持つというものである。本書でも示されているように、対話そのものが治療であることは、ODの場合だけではなく、一般の医療でも同じである。うまくいった医師と患者の話し合いは下手な薬以上の効果がある、というわけである。
「この本を書くまでは、コミュニケーションは息をすることとたいした違いがないとみなしていた――どちらも自動的に生じ、止まったときにだけ本気になって考える。医学の進歩に遅れないようにしようとするとき、コミュニケーションはそのうちに入っていなかった」というのが著者の反省である。
著者は「人の話をなに一つあますところなく聞くこと」というヘミングウェイの言葉を引用する。これは若い作家への忠告だということだが、医学の分野でも、他の多くの分野でも、等しく適用できる助言といえるであろう。
初診の段階で途中で止めずに患者に話をさせることを著者は重要視する。1人当たり数分しか割く余裕がない医師には、そんなことはわかっていると言われそうである。まして米国のように機能主義的で、個人主義的な社会であれば、医師と患者の人間関係の困難さは察するに余りある。こういう時には、著者は自分の偏見の存在に医師は気が付かなければならないとする。こうした偏見は無意識にとどまっていることが多い。
それにしても、いわゆる人間的な医療を回復することは、病院におけるシステム的な医療やAIが中心になりつつあり、リモート医療が喧伝される現代において、医療の基本的な目標となりうる。
その意味で本書は看過できない貴重な視点をいくつも与えてくれていると感じる。
ALL REVIEWSをフォローする