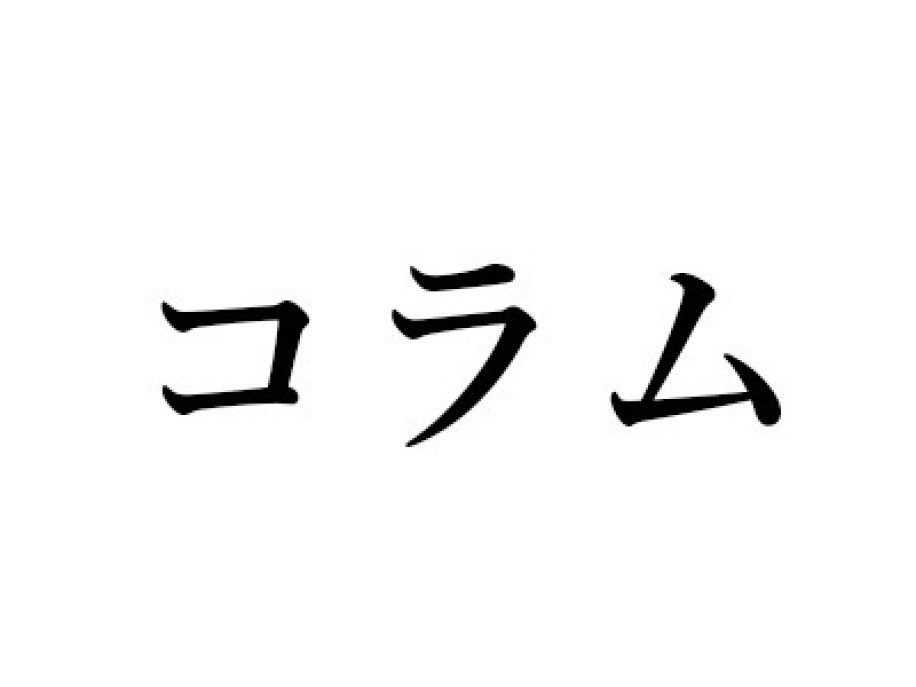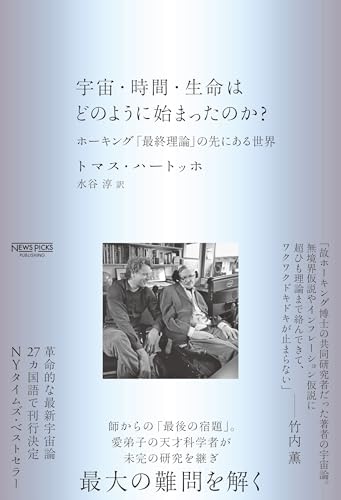書評
『医師が死を語るとき――脳外科医マーシュの自省』(みすず書房)
医療現場の実感と向き合う
新型コロナウイルスのパンデミックで社会を支えるさまざまなシステムの脆弱さが浮き彫りになったが、中でも大きな課題が医療崩壊である。メディアを通して医療現場の声を聞く機会がふえ、日頃から医療の重要性を認識してはいても、医療従事者が何を考え、どう行動しようとしているかを知ろうとしていなかったことに気づいた。当事者も生々しい声を発することは抑制してきたのではないだろうか。このような時に限らず、医療現場はさまざまな生と死とが交錯する場であり、人間として関心を持つべきところである。ロンドンの病院で三〇年以上脳外科医を務めた著者は、現場での悩み、判断、行動などを包み隠さず語る。原題は『告白』であり、日本語標題にあるように、とくに死に向き合う時の心の動きが率直に描かれ、共に考えるよう誘われる。今読む本だ。
話は辞表提出から始まる。「医師たちはいま、四〇年前には単純に存在しなかった、そして医療実践の現実にほとんど理解を示さない、官僚制度に支配されて」おり、医長までがそれに阿(おもね)るような所で働く気にはなれなくなったのだ。日本でも同じようなことが起きていはしないだろうか。
海外に仕事を求め、元同僚が病院を運営するネパール、旧知の外科医のいるウクライナという貧しい国で働くことになる。医療上の決断の多くは確率に依存し確実性はなく、患者は自分にとって何が最善かを知らないという特徴がある。医師もそれが分からないことが少なくない。そこで「臨床的な意思決定は、医師もしくは病院の金銭的利益の可能性によって簡単に歪められてしまう」。生死がそこに委ねられる事態は貧しい国でとくに顕著になる。辛い話だ。
シャワー中に倒れた二六歳の男性は動脈瘤(どうみゃくりゅう)奇形による脳内出血だ。「駄目そうだな」「そうですね」。医員との会話である。大の仲良しだったという弟との話し合いで、兄は重い障害を抱えるのは嫌だろうという言葉を引き出す。これも確率で、手術しない選択が正しいとは言えない。そのような日は眠れない夜になるとある。
次々登場する事例は、手術中のミスによる死、手の施しようもなく迎えた死、手を尽くしたが苦しみ抜いたうえでの死などであり、しかもそこには確率がある。著者は、医師たる者は患者との間に距離を保つべきとの考えから、「同情は学ばなければならないものではなく、忘れなければならないものなのだ」と若い世代に伝え、自身もそれを実践してきた。
しかし多くの体験を経た今、そう遠くはないであろう自身の死を見据えながら死について語らずにはいられなくなったと告白する。著者が特別な存在なのか、多くの医師がこのような思いを持ちながら語らずにいるのか。私には後者に思え、医療の現場を知る必要性を感じている今、この生々しさに向き合おうと思った。
「どこの国でも、医療費は制御不能なまでに急上昇している」中で、よき死とは何かを自問する著者の答えは「安楽死」なのだ。ドキッとした。ただ著者が安易にこの言葉を用いていないことは確かである。「よき生」と共に「よき死」を考える必要性を知った以上、医療関係者の実態と実感を知る努力をしながら、自分なりの答えを探すほかないと思い始めている。
ALL REVIEWSをフォローする