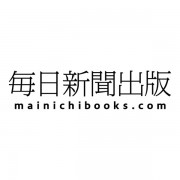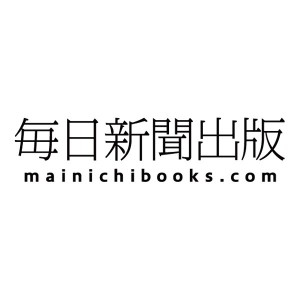前書き
『堂々と老いる』(毎日新聞出版)
田原総一朗氏は、深夜討論番組「朝まで生テレビ!」の司会者としてすっかりお馴染みの顔。直撃、追求、たたみかけ―87歳の現在もアグレッシブに、まさに命を賭けてナマ討論に挑み続けています。
そんな田原氏が、初めて「老い」について真っ向から取り組んだ書籍『堂々と老いる』が発売されます。本書の「はじめに」を特別公開します。
僕の本を何冊か担当してくれている編集者から、「田原さん、そろそろ『老い』に関する本を書かれてはいかがですか」と提案されたことをきっかけに、ここらで一度、自身の「老い」と向き合ってみようと思った次第だ。
87歳にしての初挑戦、なかなかいいじゃないか。
ただし、これまで僕が執筆してきた書籍とはテーマがだいぶ違う。
政治や経済、国際情勢、AI革命など、社会の事象に関してはいくらでも興味が湧いてくるが、「老い」というテーマで、しかも自分自身の話となると、どこから手をつければいいのやら。
一人で考えていても仕方がないので、まずは、自分の目で確かめることにした。
リサーチのため複数の書店に出かけてみると、どこに行っても、「老いの生き方エッセイ」のコーナーが設けられていた。なるほど、「老い」というのは一般の読者にとって大きな関心ごとのひとつなのだと理解した。
果たして人はエッセイに何を求めているのか。さっそく、僕もベストセラーになっている何冊かを選んで読んでみた。
いやはや、どれも興味深い。「知の巨人」と評される立命館アジア太平洋大学学長の出口治明さんや元外交官の佐藤優さんは、還暦後の人生を豊かにするのは教養であると語り、佐藤愛子さん、樋口恵子さん、下重暁子さんら女性陣は老後を楽しく自分らしく生きるための術をわかりやすく説いている。
印象に残った記述はいくつもあるが、なかでも強烈だったのは佐藤愛子さんだ。
佐藤さんは著書『九十八歳。戦いやまず日は暮れず』(小学館)のなかで、こう述べている。「前向きに生きるコツを教えてください」と聞かれ、「もう前向きもヘッタクレもあるかいな」と思われたそうだ。さらに、ご自身の執筆活動については、泳ぐのをやめると死んでしまうマグロになぞらえ、なにゆえ書くのか、いつまで書くのか考えないわけではないが、わからないから考えない、とも書かれている。実にあけすけで潔い。男性はどうしても建前を大事にするから、ここまでズバズバと本音を言うことは怖くてできない。
翻(ひるがえ)って、僕はどうか。僕自身も周囲から、「いつも前向きだ」というありがたい評価をいただくことがある。僕が前向きでいられる理由はただひとつ。好きなことだけをしているからだ。僕にとって唯一の趣味といえるのが人と話すことで、幸運にもそれが仕事につながっている。だからこの年になっても仕事をするのは少しも苦ではなく、むしろ挑戦意欲は年々高まっている。こうなったら、死ぬ間際まで現役でいようじゃないかと。
ただし、それには心身ともに健康でいることが絶対条件だ。
本文で詳述しているが、僕は還暦の年に大病を患い、生きる気力をなくしてしまったことがある。また、妻に先立たれたときは底なしの喪失感を味わい、立っていられないほど憔悴(しょうすい)した。
読者のなかには、おそらく僕と同じような経験をした人もいるだろう。
ひょっとしたら、孤独や苦悩から抜け出せない人もいるかもしれない。
「老い」を受け入れるのは容易なことではない。思うように体が動かないことも増えるし、つらい別れも経験しなければならない。それでも生きている限りは健康に留意しながら、面白いと感じられることを見つけていこうではないか。
本書は「老い」に対する心構えについて、僕自身の体験をもとに、同年代の友人の意見なども交えながらまとめてみた。健康維持のための日課に始まり、脳の活性化のために僕が実践している方法、リタイア後の社会とのつながり方の提案なども紹介している。本書が後半生を迎え、不安や迷いを抱いている人たちが堂々と生きるための一助になれば幸いだ。
[書き手]田原総一朗
そんな田原氏が、初めて「老い」について真っ向から取り組んだ書籍『堂々と老いる』が発売されます。本書の「はじめに」を特別公開します。
まだまだ老け込むわけにはいかない
僕はこれまで200冊以上の書籍を執筆してきたが、「老い」について真っ向から取り組んだのは、実はこれが初めてだ。僕の本を何冊か担当してくれている編集者から、「田原さん、そろそろ『老い』に関する本を書かれてはいかがですか」と提案されたことをきっかけに、ここらで一度、自身の「老い」と向き合ってみようと思った次第だ。
87歳にしての初挑戦、なかなかいいじゃないか。
ただし、これまで僕が執筆してきた書籍とはテーマがだいぶ違う。
政治や経済、国際情勢、AI革命など、社会の事象に関してはいくらでも興味が湧いてくるが、「老い」というテーマで、しかも自分自身の話となると、どこから手をつければいいのやら。
一人で考えていても仕方がないので、まずは、自分の目で確かめることにした。
リサーチのため複数の書店に出かけてみると、どこに行っても、「老いの生き方エッセイ」のコーナーが設けられていた。なるほど、「老い」というのは一般の読者にとって大きな関心ごとのひとつなのだと理解した。
果たして人はエッセイに何を求めているのか。さっそく、僕もベストセラーになっている何冊かを選んで読んでみた。
いやはや、どれも興味深い。「知の巨人」と評される立命館アジア太平洋大学学長の出口治明さんや元外交官の佐藤優さんは、還暦後の人生を豊かにするのは教養であると語り、佐藤愛子さん、樋口恵子さん、下重暁子さんら女性陣は老後を楽しく自分らしく生きるための術をわかりやすく説いている。
印象に残った記述はいくつもあるが、なかでも強烈だったのは佐藤愛子さんだ。
佐藤さんは著書『九十八歳。戦いやまず日は暮れず』(小学館)のなかで、こう述べている。「前向きに生きるコツを教えてください」と聞かれ、「もう前向きもヘッタクレもあるかいな」と思われたそうだ。さらに、ご自身の執筆活動については、泳ぐのをやめると死んでしまうマグロになぞらえ、なにゆえ書くのか、いつまで書くのか考えないわけではないが、わからないから考えない、とも書かれている。実にあけすけで潔い。男性はどうしても建前を大事にするから、ここまでズバズバと本音を言うことは怖くてできない。
翻(ひるがえ)って、僕はどうか。僕自身も周囲から、「いつも前向きだ」というありがたい評価をいただくことがある。僕が前向きでいられる理由はただひとつ。好きなことだけをしているからだ。僕にとって唯一の趣味といえるのが人と話すことで、幸運にもそれが仕事につながっている。だからこの年になっても仕事をするのは少しも苦ではなく、むしろ挑戦意欲は年々高まっている。こうなったら、死ぬ間際まで現役でいようじゃないかと。
ただし、それには心身ともに健康でいることが絶対条件だ。
本文で詳述しているが、僕は還暦の年に大病を患い、生きる気力をなくしてしまったことがある。また、妻に先立たれたときは底なしの喪失感を味わい、立っていられないほど憔悴(しょうすい)した。
読者のなかには、おそらく僕と同じような経験をした人もいるだろう。
ひょっとしたら、孤独や苦悩から抜け出せない人もいるかもしれない。
「老い」を受け入れるのは容易なことではない。思うように体が動かないことも増えるし、つらい別れも経験しなければならない。それでも生きている限りは健康に留意しながら、面白いと感じられることを見つけていこうではないか。
本書は「老い」に対する心構えについて、僕自身の体験をもとに、同年代の友人の意見なども交えながらまとめてみた。健康維持のための日課に始まり、脳の活性化のために僕が実践している方法、リタイア後の社会とのつながり方の提案なども紹介している。本書が後半生を迎え、不安や迷いを抱いている人たちが堂々と生きるための一助になれば幸いだ。
[書き手]田原総一朗
ALL REVIEWSをフォローする