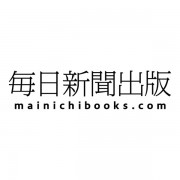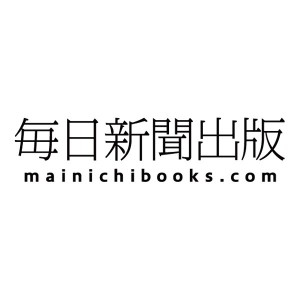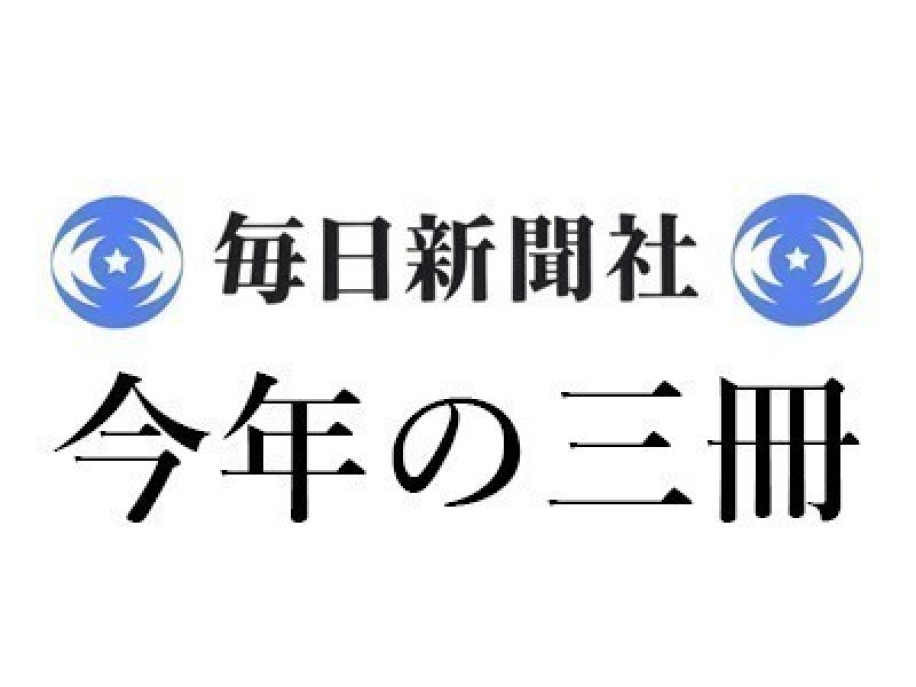前書き
『ヤングケアラー 介護する子どもたち』(毎日新聞出版)
家族を介護する子ども「ヤングケアラー」が、まだほとんど知られていなかった2020年春。毎日新聞の取材班は、そこから1年以上をかけて、独自調査やヤングケアラーたちへの取材などを通じ、その過酷な実態を世に問いかけています。彼らの暗中模索と、政府がようやく全国調査・支援へ乗り出すまでの道のりを描いた「ヤングケアラー 介護する子どもたち」(毎日新聞出版)が発売されました。
本書の「はじめに」を特別公開します。
彼は、改札近くにあるパン屋の前で待っていた。
2020年2月、冬晴れの東京は昼過ぎから強風に見舞われた。紺のジャンパーとジーンズ姿の彼は、一見どこにでもいる大学生だ。小学生の時から祖母を介護してきたなんて、誰も気づかない。通行人は彼に興味を示さず、駅の外の冷たい風に首をすくめて行き交った。
その日の朝刊は、横浜に停泊中のクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」の記事で持ちきりだった。日本で初めての新型コロナウイルスの集団感染だ。それでも街にマスク姿の人はまばら。世界が未知のウイルスの猛威を知るのはもう少し後のことになる。
1カ月ほどのメールのやりとりを経て、彼が取材の待ち合わせに指定したのは都心の市ヶ谷だった。丁寧な文面には目印の店の写真も添えられ、律儀な人柄を思わせた。
毎日新聞特別報道部の向畑泰司は、取材場所になりそうな喫茶店を下見してから、約束の午後2時に彼と駅で落ち合った。互いに自己紹介をすませると、彼が言った。
「風が強くて寒いのに、長い時間お待たせしませんでしたか」
この場所わかりにくくなかったですか、と彼はこちらを気遣った。メールの通り真面目そうな子だな。
喫茶店まで歩く道すがら、彼の緊張をほぐそうと近況を尋ねた。大学の卒業を控えて、卒業論文やアルバイト、3年前から施設に入った祖母の見舞いにと、彼は多忙だった。
「スーパーに就職が決まって、何とか卒論も終わって」。歩きながら彼は安堵の表情を浮かべた。それはおめでとう、と向畑はあいづちを打った。
実のところ、向畑の方が普段より緊張していた。相手は、幼少期から介護の大きな責任と負担を抱えてきたという。「家族を介護した体験を自分の中で整理できない子は多いんです。彼らの思いを大切にしてあげてください」。専門家や支援団体はそう助言をくれた。
事件の取材経験が豊富な向畑だが、今回はいつもと違う繊細さと配慮が必要だった。風の吹き荒れる街はどこか騒々しく、平常心を乱されて少し鬱陶しくもあった。
そもそも半信半疑だった。自分のおばあさんの「主介護者」を小学生から10年近く引き受ける子なんて本当にいるのかなあ。お手伝い程度ならともかく……。
だが、いわゆるヤングケアラーの当事者に直接話を聞く、またとない機会だ。
「僕は記者なので、もしかすると思い出したくないこと、聞かれたくない質問も聞いてしまうかもしれない。その時は無理に答える必要はないですよ」
喫茶店に着いた。彼は向かい合って座るなり、笑って答えた。
「何でも聞いてください。話せることは全部お話しします」
取材は2時間に及んだ。
小学6年生から祖母の介護を始め、毎日、朝と夜の食事を用意したこと。
大人であるケアマネジャー、ヘルパーとのやりとりを全部担当したこと。
携帯電話を野放図に鳴らす祖母を、学校のトイレに隠れて電話口でなだめたこと。
放課後はすぐに家に帰って、祖母と一緒に歌ったり話し相手になったりしたこと。
祖母の認知症が進み、きつい言葉を浴びるようになったこと。
やりきれなくて部屋の壁に物を投げつけたこと。
だけど、祖母に物を投げつけることだけは絶対にしなかったこと。
彼に下の世話をされて祖母が泣いたこと。
小学6年から大学1年まで続いた彼の介護は、周囲からほとんど顧みられていなかった。その孤独を、彼は悲観するでもなく、さも当たり前のように、時に冗談を交えて話した。その態度はどこか超然として、実年齢よりもはるかに大人に見えた。無数のエピソードは具体的で、詳細で、リアルだった。間違いなく本物のヤングケアラーの物語だった。
今までの境遇に後悔はないのか、と彼に尋ねた。
「介護をやっている時は疎ましくもあったけど、介護をしていたから得た物も多かったと、今は思えます」
彼はメディアの取材を初めて受けたという。
「どうして受けてくれたんですか?」
「やっぱり、知ってほしいなって思います。僕たちのような子どもがいることを。どういう支援が必要なのか、とかはわからないけど、たくさんの人に理解してほしいなって思います。僕が話すことで、今、つらい思いをしている他のヤングケアラーの子が、少しでも救われるのならと思って」
2人で喫茶店を出ると、強風はやんでいた。丁寧に別れのあいさつをする彼を、駅の改札で見送った。
向畑は「これは記事になる」と確信していた。記者なら誰しも、取材が成功した時はうれしいものだ。だがそれより、不安と重圧が胸にあった。
本当は他人に語りたくなかっただろう辛苦の日々を、さりげない勇気と覚悟をもって話した彼に応える記事が書けるか? 自分にその資格があるのか? 記事がかえって彼らの心や家庭を乱し、不幸にするのではないか?
世間をにぎわす事件でも、特ダネをつかんだわけでもない。そもそもヤングケアラーという、わかったようなわからないような言葉は、世間に全くと言っていいほど知られていなかった。
それでも、彼のような家庭環境を持った子どもが他にいないとは、もう思えなかった。彼のようなヤングケアラーが日本には相当な数、いるのではないか。少子高齢化と核家族化が進むこの国と、ヤングケアラーの存在が切っても切り離せない時代が来る。否、もうすでにその時かもしれない。限られた時間の中で調べることはいくらでもあった。
冬の陽が傾き始めるのは早い。彼が去った薄暮の街は落ち着きを取り戻していた。
彼の本名は、事情があってここには書けない。
仮の名を谷村純一と呼ぶ。
[書き手]毎日新聞取材班
本書の「はじめに」を特別公開します。
彼は、改札近くにあるパン屋の前で待っていた。
2020年2月、冬晴れの東京は昼過ぎから強風に見舞われた。紺のジャンパーとジーンズ姿の彼は、一見どこにでもいる大学生だ。小学生の時から祖母を介護してきたなんて、誰も気づかない。通行人は彼に興味を示さず、駅の外の冷たい風に首をすくめて行き交った。
その日の朝刊は、横浜に停泊中のクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」の記事で持ちきりだった。日本で初めての新型コロナウイルスの集団感染だ。それでも街にマスク姿の人はまばら。世界が未知のウイルスの猛威を知るのはもう少し後のことになる。
1カ月ほどのメールのやりとりを経て、彼が取材の待ち合わせに指定したのは都心の市ヶ谷だった。丁寧な文面には目印の店の写真も添えられ、律儀な人柄を思わせた。
毎日新聞特別報道部の向畑泰司は、取材場所になりそうな喫茶店を下見してから、約束の午後2時に彼と駅で落ち合った。互いに自己紹介をすませると、彼が言った。
「風が強くて寒いのに、長い時間お待たせしませんでしたか」
この場所わかりにくくなかったですか、と彼はこちらを気遣った。メールの通り真面目そうな子だな。
喫茶店まで歩く道すがら、彼の緊張をほぐそうと近況を尋ねた。大学の卒業を控えて、卒業論文やアルバイト、3年前から施設に入った祖母の見舞いにと、彼は多忙だった。
「スーパーに就職が決まって、何とか卒論も終わって」。歩きながら彼は安堵の表情を浮かべた。それはおめでとう、と向畑はあいづちを打った。
実のところ、向畑の方が普段より緊張していた。相手は、幼少期から介護の大きな責任と負担を抱えてきたという。「家族を介護した体験を自分の中で整理できない子は多いんです。彼らの思いを大切にしてあげてください」。専門家や支援団体はそう助言をくれた。
事件の取材経験が豊富な向畑だが、今回はいつもと違う繊細さと配慮が必要だった。風の吹き荒れる街はどこか騒々しく、平常心を乱されて少し鬱陶しくもあった。
そもそも半信半疑だった。自分のおばあさんの「主介護者」を小学生から10年近く引き受ける子なんて本当にいるのかなあ。お手伝い程度ならともかく……。
だが、いわゆるヤングケアラーの当事者に直接話を聞く、またとない機会だ。
「僕は記者なので、もしかすると思い出したくないこと、聞かれたくない質問も聞いてしまうかもしれない。その時は無理に答える必要はないですよ」
喫茶店に着いた。彼は向かい合って座るなり、笑って答えた。
「何でも聞いてください。話せることは全部お話しします」
取材は2時間に及んだ。
小学6年生から祖母の介護を始め、毎日、朝と夜の食事を用意したこと。
大人であるケアマネジャー、ヘルパーとのやりとりを全部担当したこと。
携帯電話を野放図に鳴らす祖母を、学校のトイレに隠れて電話口でなだめたこと。
放課後はすぐに家に帰って、祖母と一緒に歌ったり話し相手になったりしたこと。
祖母の認知症が進み、きつい言葉を浴びるようになったこと。
やりきれなくて部屋の壁に物を投げつけたこと。
だけど、祖母に物を投げつけることだけは絶対にしなかったこと。
彼に下の世話をされて祖母が泣いたこと。
小学6年から大学1年まで続いた彼の介護は、周囲からほとんど顧みられていなかった。その孤独を、彼は悲観するでもなく、さも当たり前のように、時に冗談を交えて話した。その態度はどこか超然として、実年齢よりもはるかに大人に見えた。無数のエピソードは具体的で、詳細で、リアルだった。間違いなく本物のヤングケアラーの物語だった。
今までの境遇に後悔はないのか、と彼に尋ねた。
「介護をやっている時は疎ましくもあったけど、介護をしていたから得た物も多かったと、今は思えます」
彼はメディアの取材を初めて受けたという。
「どうして受けてくれたんですか?」
「やっぱり、知ってほしいなって思います。僕たちのような子どもがいることを。どういう支援が必要なのか、とかはわからないけど、たくさんの人に理解してほしいなって思います。僕が話すことで、今、つらい思いをしている他のヤングケアラーの子が、少しでも救われるのならと思って」
2人で喫茶店を出ると、強風はやんでいた。丁寧に別れのあいさつをする彼を、駅の改札で見送った。
向畑は「これは記事になる」と確信していた。記者なら誰しも、取材が成功した時はうれしいものだ。だがそれより、不安と重圧が胸にあった。
本当は他人に語りたくなかっただろう辛苦の日々を、さりげない勇気と覚悟をもって話した彼に応える記事が書けるか? 自分にその資格があるのか? 記事がかえって彼らの心や家庭を乱し、不幸にするのではないか?
世間をにぎわす事件でも、特ダネをつかんだわけでもない。そもそもヤングケアラーという、わかったようなわからないような言葉は、世間に全くと言っていいほど知られていなかった。
それでも、彼のような家庭環境を持った子どもが他にいないとは、もう思えなかった。彼のようなヤングケアラーが日本には相当な数、いるのではないか。少子高齢化と核家族化が進むこの国と、ヤングケアラーの存在が切っても切り離せない時代が来る。否、もうすでにその時かもしれない。限られた時間の中で調べることはいくらでもあった。
冬の陽が傾き始めるのは早い。彼が去った薄暮の街は落ち着きを取り戻していた。
彼の本名は、事情があってここには書けない。
仮の名を谷村純一と呼ぶ。
[書き手]毎日新聞取材班
ALL REVIEWSをフォローする