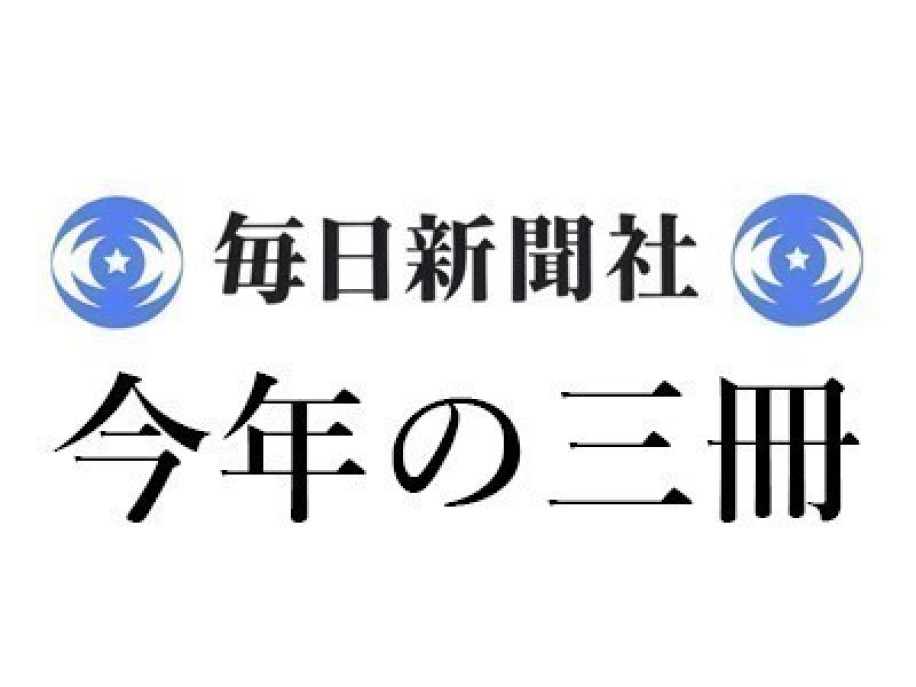書評
『山本五十六』(吉川弘文館)
名提督の戦略的思想を解明
日露戦争時の連合艦隊司令長官東郷平八郎と並び、日本人の心にある種の誇りと親しみを感じさせる提督は太平洋戦争時の連合艦隊司令長官山本五十六以外にはいないといえよう。本書は著者の永年(ながねん)の疑問「なぜ山本は東郷に並び称される名提督か?」に対し読者にあらゆる示唆を与える教養書でもある。本書は真珠湾攻撃作戦の成功に名声を博した山本が、日本の敗戦によって、むしろ逆にアメリカに一矢を報いた提督として価値付けられ賞賛(しょうさん)の的になったとの視点から、その理由を史実に語らせている。山本は幼少の頃(ころ)から何事にも課題をもって取り組み、このことが海軍士官の職務において常に最もよい選択肢を見つけるという判断力を培わせた。他方、山本が陸軍や文官の独善を嫌っていたことからすれば、真珠湾奇襲は、山本が主導する海軍単独による緒戦として、早くから研究し計画した結果であったが、反面、国家的な戦争指導という視座に立って考察すれば、海軍・陸軍・政府間の緊密な協同・調整の体制で対米戦争計画を起案したわけでもなく、陸海軍による並列的な作戦の積み上げで戦争が推移していたことを物語っている。
果たして米国の戦意喪失が可能であったのであろうか。対米戦全局にわたって冷徹にその結果を見通したものではなく、やはり山本は連合艦隊司令長官という海軍軍人の立場に留(とど)まり、大所高所に立つ政戦略眼を確かに備えていたとはいい難いであろう。山本の戦略的思想に関する史料が少ないにもかかわらず、本書は著者の永年の研究蓄積を駆使した精緻(せいち)な分析によってその解明を試みている。
因(ちな)みに山本の軍縮に対する潜在的な反米感情と、山本が海軍軍人としていち早く開発に着手した軍縮条約規定外の航空機に対する兵器としての価値が一体化し、これが日米関係の悪化とともに真珠湾への奇襲作戦が発想され、具現化されていった。しかし、対米戦に関する終結構想を欠いたままであり、結局アメリカに真正面に対峙(たいじ)していなかったことが読み取れる。
これらの背景には、海軍がロンドン軍縮締結を機に強硬化したこと、情勢判断の独善性、常識的判断に必要な感性の喪失、空想と現実の峻別(しゅんべつ)や対応の杜撰(ずさん)さ等が存在していたことを本書は指摘している。敗戦の苦渋を体験した日本人はかつてのその知的頽廃(たいはい)を知るが故に勝利していた頃を代表している山本を、日本海海戦の栄光の東郷と並ぶ名提督として受け止めているといえよう。ぜひ一読を勧めたい。
[書き手] 影山好一郎(かげやま こういちろう)1942年生まれ。元帝京大学文学部史学科教授。
ALL REVIEWSをフォローする