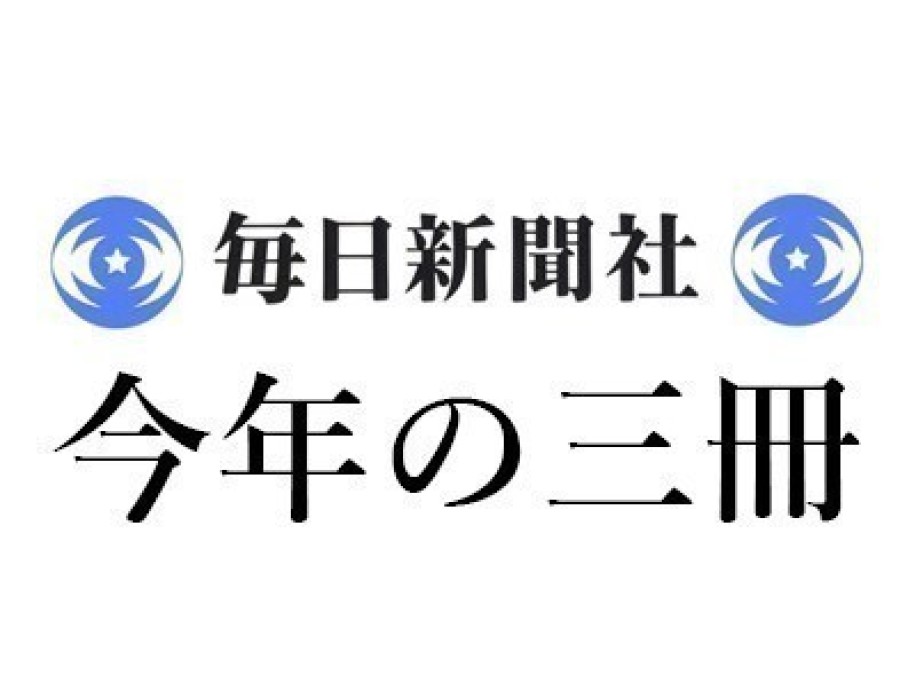前書き
『戦争孤児たちの戦後史1: 総論編』(吉川弘文館)
空のベビーカー109台。
ウクライナ・リビウ市中心部で撮られた1枚の写真は、戦禍に巻き込まれ亡くなった子どもたちの追悼と抗議の意とともに、弱い者が真っ先に犠牲となる戦争の本質を世界に伝えた。
しかし、戦争の犠牲者は亡くなった人だけにとどまらない。
太平洋戦争で両親を亡くし、戦後を孤児として生き抜いた人たちの証言を、『戦争孤児たちの戦後史1』の一部より紹介する。
中国残留孤児だったら、国・厚労省が子どもの身元を責任もって探してくれるので、どれだけうらやましかったか、そう思っていたとのことであった。
私が戦争孤児の方々への聴き取り調査をしているなかでも、「『孤児であったことはしゃべってはいけないよ』とみんなから言われた」という方が少なくなかった。私たちが踏み込めない、踏み込んではいけない戦争孤児たちの戦後史を肌で感じることがいく度となくあった。
これらの言葉は戦争に巻き込まれ、戦争孤児として暮らしながら、希望を胸に生き抜いてきた人たちの声である。そうした人たちとともに、沈黙を貫いて生き、亡くなった方々もどれだけいるのであろうか。私たちの研究は、そうした沈黙の海のなかにある声を聴き取ることも使命であると感じている。
[書き手] 浅井 春夫(あさい はるお・立教大学名誉教授) 著書に『沖縄戦と孤児院』(吉川弘文館 2016)、『戦争をする国・しない国』(新日本出版社 2016)など多数。
ウクライナ・リビウ市中心部で撮られた1枚の写真は、戦禍に巻き込まれ亡くなった子どもたちの追悼と抗議の意とともに、弱い者が真っ先に犠牲となる戦争の本質を世界に伝えた。
しかし、戦争の犠牲者は亡くなった人だけにとどまらない。
太平洋戦争で両親を亡くし、戦後を孤児として生き抜いた人たちの証言を、『戦争孤児たちの戦後史1』の一部より紹介する。
戦争孤児の体験を聴く
「中国残留孤児の人たちを、ず~とうらやましく思った時期がありました」
東京大空襲で火の海のなかを逃げ惑い、母親が死亡する直前に、近くにいた名前も知らない女性に本人があずけられたことで生きのびた方の言葉である。どうにかして母親の名前と亡くなったときのことを知りたいと、その方は長い間探し続け、行政資料にある個人情報についての情報開示請求をした戦争孤児体験者であった。中国残留孤児だったら、国・厚労省が子どもの身元を責任もって探してくれるので、どれだけうらやましかったか、そう思っていたとのことであった。
「そんなことをあなたに答える必要はない!」
聴き取りも後半に差しかかったとき「どのような職業で暮らしてこられたのですか」という問いに、急に声を荒げて、即座にこのような言葉を投げ返された。誠実で温厚な方であったが、このときには異様に感じるほど、語気を強くした。戦後を生きのびるためにどんな職業についてきたのかはわからないが、この方にとって戦後がいかに困難のなかにあったのかを感じた瞬間であった。このように、戦争孤児体験者の記憶の底にしまってある“痛み”に無自覚なままに土足で踏み入れてしまうことがあった。「履歴書を書くことがいやだったなあ。だって書くことがないんですから」
大手企業で仕事をしてきた方で、戦争孤児のなかでは“社会的地位を築いた人”とみられている人の言葉である。父母・家族の欄、親戚関係、生い立ちの記録など、自らのプライバシーに関する情報を持たないで、青年期を生き、そして定年退職まで仕事をまっとうされた人が、気持ちを押し込んで生きてきた戦後の歴史なんだと実感した。私が戦争孤児の方々への聴き取り調査をしているなかでも、「『孤児であったことはしゃべってはいけないよ』とみんなから言われた」という方が少なくなかった。私たちが踏み込めない、踏み込んではいけない戦争孤児たちの戦後史を肌で感じることがいく度となくあった。
「孤児院での記憶は、コンクリートで固めて、沖縄の海に沈めたい!」
沖縄戦後に建てられた孤児院で暮らした経験を、この男性は吐き捨てるように語った。私には孤児院での生活をそれ以上聴くことはできなかった。戦争を生きのびて、少年期の一時期を孤児院で暮らした彼にとって、そこでの生活体験はトラウマとなって記憶のなかに住みついているのだと思った。まさに記憶の断面を吐きだすような言葉のなかに、生き抜いてきた人の強さを想う。心の傷は、折り合いをつけることはできるが、何十年たっても癒えることがないのだろう。これらの言葉は戦争に巻き込まれ、戦争孤児として暮らしながら、希望を胸に生き抜いてきた人たちの声である。そうした人たちとともに、沈黙を貫いて生き、亡くなった方々もどれだけいるのであろうか。私たちの研究は、そうした沈黙の海のなかにある声を聴き取ることも使命であると感じている。
[書き手] 浅井 春夫(あさい はるお・立教大学名誉教授) 著書に『沖縄戦と孤児院』(吉川弘文館 2016)、『戦争をする国・しない国』(新日本出版社 2016)など多数。
ALL REVIEWSをフォローする