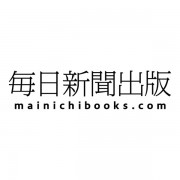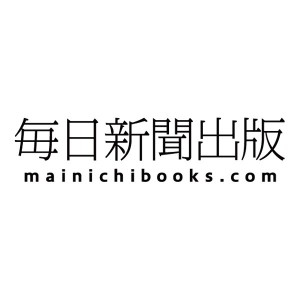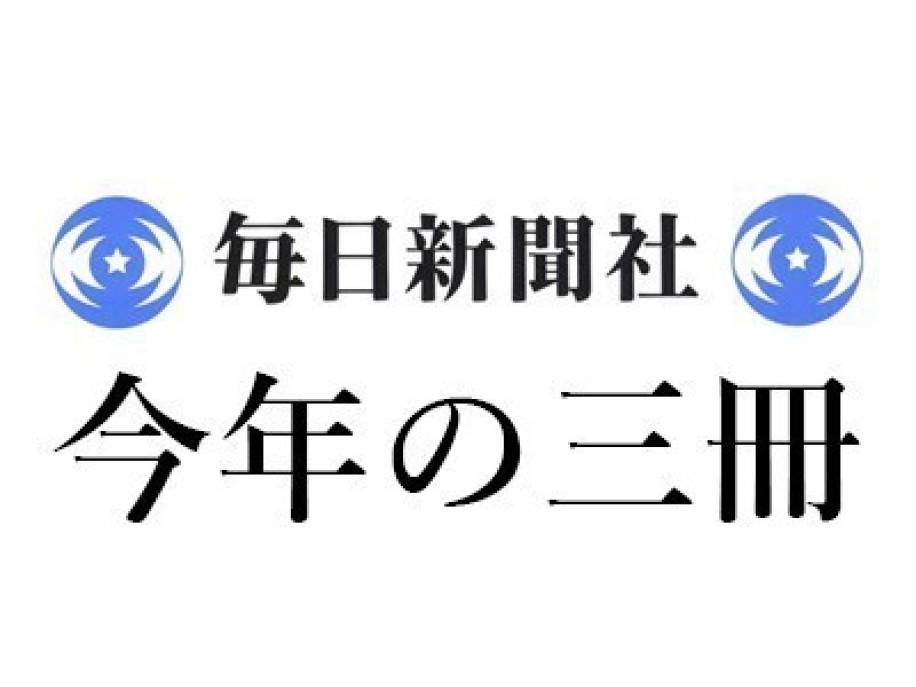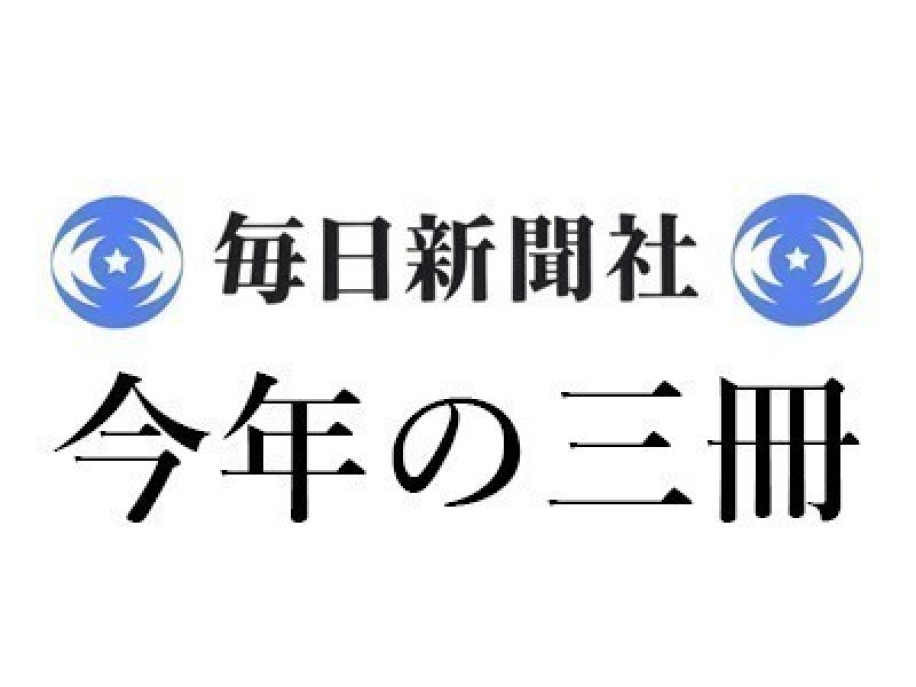書評
『世界を手で見る、耳で見る ――目で見ない族からのメッセージ』(毎日新聞出版)
毎日新聞社が発行する点字新聞「点字毎日」が創刊されて、今年で100年。これまで点字読者に様々な話題を提供してきた同紙に、2011年から8年間にわたって掲載された連載記事が書籍化されました。『世界を手で見る、耳で見る――目で見ない族からのメッセージ』(毎日新聞出版)は、2歳の時に光を失った、言語学者によるエッセイです。日々の生活の中で、著者・堀越喜晴さんが感じたことを、ユーモアを交えながら、率直な言葉でつづります。障害を持つ人がいて、なお幸せであるような社会こそが、本来あるべき社会の姿ではないか? そんな問いを投げかける本書の「はじめに」を特別公開します。
ここにお送りする小著は、私が「点字毎日」紙上で、2011年1月から2019年4月まで月に一度連載した記事の内からいくつかを選び、それらに多少の修正を加えて編んだものである。「点字毎日」は、毎日新聞社から発刊されている週刊の点字新聞である。1922年の創刊以来、戦時中も一度の休刊もなく発行を続け、今年2022年に創刊100年を迎えた。この記念すべき年に本書を世に送ることができたことは、私にとっては奇跡とも言えるほどに望外の光栄である。
この連載のちょうど20年前、私はやはり同じぐらいの期間、NHKラジオ第2放送の「視覚障害者のみなさんへ」という番組に、月に一度出演していた。後にそれを、『バリアオーバーコミュニケーション 心に風を通わせよう』という小著にまとめたが、あの時と同じことを、今度は紙上でやるようにというのが、この連載のご依頼であった。
ところで、いうまでもなく点字は突点を指で触って読む文字である。だったら、私のしゃべりが「耳障り」なら、当然私が書くような、なんとも読みづらい文章は「指障り」というのがふさわしいだろう。なので私は、連載の通しタイトルを、「堀越喜晴のちょいと指障り」ではどうかと提案した。ところが、この「障り」の字が、最近「障害者」の表記がらみで微妙だ、ということで、やむなく「指触り」としたのだった。
もとより私は、「障害者」の表記法にも、また呼称にも、さほどこだわりを持たない。しかし、障害者との対比でよく用いられる「健常者」という言葉には、どうにもなじめない。だいたい、この世に常に健康だなんていう人が果たしているだろうか。「いや、健康なのが常態である人という意味だ」、あるいはそう言うかもしれない。ならば、私だって「健常者」だ。視力がないことが常態である私にとっては、目が見えないことをひっくるめて「健康」なのである。なので、私の中では「障害者」と「健常者」とは、決して対立概念ではない。それで、本書を通じて私は、「健常者」という言葉には必ずかぎかっこを付した。
その代わりに私は、副題にもあるように、本書ではしばしば「目で見る族」と「目で見ない族」という言葉を使った。これは、本書でご登場願った、作家で、盲学校時代の私の友人が考案した呼び名である。それこそなじみのない言葉だろう。でも、このように呼んでみると、目が見える人たちの中でも、目で見る以外の感覚に興味を持つ人、持たない人、それから目が見えない人たちの中でも、目で見る感覚に興味を持つ人、持たない人、またいろいろな見え方、「見えない」方、という具合に、「見る」ということが様々なグラデーションをなして立ち現れてこないだろうか。
そう、私たちは世界をただ「目で」見ているばかりではない。触って見る。聞いて見る。味わって見る。嗅いで見る。私が本書で皆さんと分かち合いたいのは、そのような「見る」のグラデーション効果なのである。
さあ、ここから生まれつき目で見ない族の私の水先案内で、目くるめく五感のグラデーションの世界の旅に出発しよう!
[書き手]堀越喜晴
ここにお送りする小著は、私が「点字毎日」紙上で、2011年1月から2019年4月まで月に一度連載した記事の内からいくつかを選び、それらに多少の修正を加えて編んだものである。「点字毎日」は、毎日新聞社から発刊されている週刊の点字新聞である。1922年の創刊以来、戦時中も一度の休刊もなく発行を続け、今年2022年に創刊100年を迎えた。この記念すべき年に本書を世に送ることができたことは、私にとっては奇跡とも言えるほどに望外の光栄である。
この連載のちょうど20年前、私はやはり同じぐらいの期間、NHKラジオ第2放送の「視覚障害者のみなさんへ」という番組に、月に一度出演していた。後にそれを、『バリアオーバーコミュニケーション 心に風を通わせよう』という小著にまとめたが、あの時と同じことを、今度は紙上でやるようにというのが、この連載のご依頼であった。
ところで、いうまでもなく点字は突点を指で触って読む文字である。だったら、私のしゃべりが「耳障り」なら、当然私が書くような、なんとも読みづらい文章は「指障り」というのがふさわしいだろう。なので私は、連載の通しタイトルを、「堀越喜晴のちょいと指障り」ではどうかと提案した。ところが、この「障り」の字が、最近「障害者」の表記がらみで微妙だ、ということで、やむなく「指触り」としたのだった。
もとより私は、「障害者」の表記法にも、また呼称にも、さほどこだわりを持たない。しかし、障害者との対比でよく用いられる「健常者」という言葉には、どうにもなじめない。だいたい、この世に常に健康だなんていう人が果たしているだろうか。「いや、健康なのが常態である人という意味だ」、あるいはそう言うかもしれない。ならば、私だって「健常者」だ。視力がないことが常態である私にとっては、目が見えないことをひっくるめて「健康」なのである。なので、私の中では「障害者」と「健常者」とは、決して対立概念ではない。それで、本書を通じて私は、「健常者」という言葉には必ずかぎかっこを付した。
その代わりに私は、副題にもあるように、本書ではしばしば「目で見る族」と「目で見ない族」という言葉を使った。これは、本書でご登場願った、作家で、盲学校時代の私の友人が考案した呼び名である。それこそなじみのない言葉だろう。でも、このように呼んでみると、目が見える人たちの中でも、目で見る以外の感覚に興味を持つ人、持たない人、それから目が見えない人たちの中でも、目で見る感覚に興味を持つ人、持たない人、またいろいろな見え方、「見えない」方、という具合に、「見る」ということが様々なグラデーションをなして立ち現れてこないだろうか。
そう、私たちは世界をただ「目で」見ているばかりではない。触って見る。聞いて見る。味わって見る。嗅いで見る。私が本書で皆さんと分かち合いたいのは、そのような「見る」のグラデーション効果なのである。
さあ、ここから生まれつき目で見ない族の私の水先案内で、目くるめく五感のグラデーションの世界の旅に出発しよう!
[書き手]堀越喜晴
ALL REVIEWSをフォローする